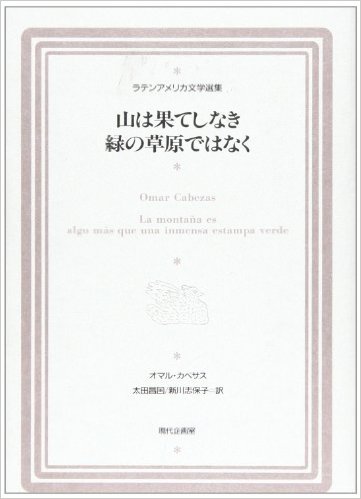◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者、秘密保護法違憲訴訟原告)
「国破れて山河在り」。でも、「山河」さえ壊したこの国の政治家と官僚に、「国の安全」を語る資質も資格もあるのだろうか。先の見えないこの国に行く末…。私は「杜甫」(とほ)の詩の1節を思い出しつつ、暗澹たる思いで三重県の伊勢湾河口から岐阜県にかけて長良川堤を歩いた。
「無駄な公共事業の典型」と言われた長良川河口堰。「本州で唯一、ダムのない川の環境を壊すな」との激しい反対運動が繰り広げられたのは1980年代後半から90年代。それを押し切り、国が堰の水門が閉じ、長良川を海から隔絶したのは、1995年7月だった。
それから20年。「豊かな恵みをもたらす『母なる川』の長良川を元に戻せ」と、あきらめずに堰の開門を求める人たちが地元には多く残っている。そんな人たちが5日に岐阜市で開いた集会「よみがえれ長良川、開門調査実現を」に、河口堰とは浅からぬ関係にある私も参加した。
◇死の川と化した長良川
前日の4日、「今の長良川の現状を見てください」と、地元の人たちが堰のある伊勢湾河口を出発点に上流に向けて案内してくれた。河口付近では、背割り堤一つ隔てて揖斐川と並行して流れている。船に乗り、まず堰のない揖斐川の底をすくうと、砂地でシジミも何個か取れた。
次に堤を回り込み、長良川側に出た。底にはヘドロがびっしり溜まり、異臭を放っていた。低酸素状態で、もちろんシジミはいない。堰で流れが止まったら堰の上流でヘドロがたまることは、私にも容易に想像出来た。しかし、水門下流の海側でこれほどとは…。満潮時、逆流したごみが堰で止められて沈み、ヘドロ化するのだという。
堰を超え、上流側に回り込んだ。もちろんそこにも大量のヘドロが溜っていた。「清流」「唯一の自然河川」と多くの人から親しまれた長良川は、堰で海と隔絶されたことで、自然の営みが出来ず死に絶えていた。
堰建設前はアユ、サツキマス、ボラ、スズキ…。潮の干満で海と川の水が混じる汽水域を通って多くの魚が行き来した。海で育った魚が川に上り、また川を下って海に出た。その魚を狙う漁師の小舟が浮かぶのが、日本の原風景でもあった。しかし、魚の棲まない川に舟も浮かんでいなかった。
ヨシハラ堰から上流に向けて10キロ余り、背割り堤の上を走った。
右に長良川、左に揖斐川。堰のない揖斐川には青々と育ったヨシ原が続く。しかし、長良川河原はヨシの姿が消え、セイタカアワダチソウなどの雑草や雑木が生い茂る。
揖斐川のヨシ原に降りた。ベンケイガニがうようよ。あっという間にバケツ一杯採取出来た。一方、長良川河原にも棲んでいたこのカニの姿はなく、以前見られない赤い脚のカニが数匹取れただけ。
◇長良川の天然アユが準絶滅危惧種に
堰がなく、満潮・干潮の影響を受けて水位が上下する揖斐川は、ヨシの根にも酸素が供給され、元気に育つ。一方、長良川は堰で隔絶さえ潮の干満による水位の変化さえなくなった。ヨシも育たず、よどんだ巨大な溜池と化していた。
ヨシの根っこには多くの魚が卵を産み付け、孵化した幼魚にとっては、外敵に狙われにくい恰好の棲家。ヨシ原のなくなった長良川で生物の営みが消えたのは当然だったのだ。
岐阜市は今年、鵜飼で知られる長良川の天然アユを準絶滅危惧種に指定した。アユは、春から夏海から、上・中流部に遡上。岩に着いたコケを食べて成長し、秋に河口堰のある下流部に降りて産卵。孵化した稚魚は海に出て、春になると、また川を上る。
しかし、堰から上流30キロほどまでが「溜池」になった長良川では、川底の岩はヘドロで覆われ、アユの食べるコケも生えない。ヨシ原がなくなれば、安全に過ごす棲家もない。せっかくアユが卵を産んでも死滅する。今は「溜池」までアユが降りて来たとき、漁師がすくって堰の下までトラックで運んでいる。もう、人間の手をかけてやらないと、アユは「自然」では生きられなくなっていた。
木曽、長良、揖斐。木曽三川の流れが集まる伊勢湾河口部の河原には、週末になると多くの家族連れが訪れる。バーベキューに興じ、たっぷりの自然エネルギーをもらって帰っていく。
でも、命の息吹がなくなった長良川には、もらうべきエネルギーがない。古代から水辺で生きて来た「人」という種族は、そのことを敏感に感じるのだろう。堰建設以来、元気に遊ぶ子供たちの声は、揖斐,木曽の河原からは聞こえても、長良からは途絶えた。
◇長良川の開門を求める人々
翌5日、岐阜市の国際会議場での集会。広い大会議室が満員になった。多くの人がまだまだ長良川をいとおしく思い、蘇らせることに執念を燃やしている表れだ。
80歳を超える今まで漁師として長良川とともに生きて来た大橋亮一さん。「堰が出来て3年ほどは、普通に魚が獲れ、堰は心配したほどではないと思った。だが、4年後あたりからみるみる魚が減った。堰が出来ても、それまで棲んでいた魚は何とか生きられた。
でも、産卵の環境がなくなり、稚魚が育たない。海につながっての川だ。自然の循環がなくなり、私たちが育った長良川は死んだ」と語り、改めて生態系を人間が壊したことに怒りを込めた。
今は鵜飼舟の船頭。大橋さんのような川漁師にあこがれる30代の平工顕太郎さん。「漁で妻、子供を養えるようにしたい。自然の長良川が蘇えるように開門実現にぜひ皆さんの力を貸して下さい」と、熱い思いで訴えた。
◇国土交通省、「無駄な公共事業でなかった」
堰で長良川が死ぬことは、多くの人が恐れ、警告して来た。しかし、「将来、必ず水が足らなくなる」「堰を造らないと、水害の心配がある」と強引にその声を封じて、建設に突き進んだのは、この国の官僚と政治家。その周りに利権目当ての人が巣食っていた。住民が最後の砦として、司法に判断を委ねても、裁判官は聞く耳さえ持たなかった。
しかし、水需要は増えるどころか、この20年間ますます減った。河口堰の水など一滴も必要としていないのだ。だが、国土交通省は河口堰で溜めた水が1部使われていることを理由に、「無駄な公共事業でなかった」と強調する。
確かに河口堰で生まれる毎秒22.5トンの水のうち、愛知県知多半島の水道用に2.95トン。三重県津地域と合わせ3.5トン余りが供給されている。知多半島へはわざわざ多額の費用をかけて、導水路まで造った。
しかし、そのカラクリを知多半島に住み、「河口堰の水を考える住民の会」世話人の宮崎武雄さんが教えてくれた。
「知多半島には、『工業用水』として確保した木曽川の水が大量に余り、『暫定』として水道用に供給されて来た。しかし、『河口堰が出来たから』として、強引に『暫定利用』をやめさせ、河口堰の水に切り換えさせた。
しかし、工業用水は使うあてがなく、その分大量に伊勢湾に垂れ流している。何のことはない。国交省のアリバイ作りにされただけです」
「知多半島の住民は、堰が出来たことで、それまでの美味しかった木曽川の水が飲めなくなった。代わりに河口堰に溜った臭い水を飲まされている。しかも、堰の建設負担に加え導水路を作ったことで水道料金は大幅値上げになった」。
治水も同様だ。国交省では2004年、想定を超える毎秒8000トンの大雨が降っても、堤防下2メートルの安全ラインをさらに1.5メートル以上下回ったとして、堰の治水効果を強調する。しかし、この事実こそ実は、「治水のために、堰は不可欠」との宣伝が大ウソだったことの何よりの証明なのだ。
◇長良川河口堰問題の再検証
この点は私の著書「報道弾圧」(東京図書出版)を読んでもらえば分かる。当時の建設省は堰建設前の1990年、堰がなくても長良川は想定される最大大水、毎秒7500トンが流れても、水位は安全ラインの下しか来ず、治水上堰が不要なことを水位計算で十分承知していた。
しかし、私の取材が進み、この計算結果が露見するのを恐れた。なんとしても堰を建設しようと、計算を左右する川底の摩擦の値(粗度係数)を操作。あたかも最大大水では、堤防の安全ラインを超えるかのデッチ上げ水位図を描いて見せ、「治水上、堰が必要」と宣伝、着工に漕ぎつけた。
しかし、この時、建設省がデッチ上げた係数の値が本当に正しいなら、2004年の大雨での水位は、安全ラインぎりぎりか、少し上回らなければならない。しかし、1.5メートル以上下だったということは、この係数の値がウソだったことの証明、治水上過剰投資だったことを物語っている。
つまり、多額の税金を投入し、ウソと言い訳に塗り固めて造った河口堰は、無駄であるだけでなく、人々の川での営みまで壊した。集会では、「河口堰がなくなっても誰も困りはしない。とにかく一刻も早く堰のゲートを開門し、海とつながった長良川に戻してほしい」との声が相次いだ。
◇記事は没に、記者職は剥奪
官僚と政治家のウソを暴く私の河口堰取材は、建設省の極秘資料の入手により、完璧に裏付けが取れていた。しかし、記事にならないまともな理由すら説明しないまま、朝日幹部は止めた。裏によほど後ろめたい理由があったのだろう。ほとんどの記事はボツにされ、異論を唱えた私は記者の職を追われた。
もし、私に朝日を辞める勇気があり、真実を明らかに出来たなら、河口堰工事は止められたかも知れない…。私は何より長良川にすまないとの思いで、ずっと気にかかっていた。
でも、官僚や政治家、住民の声も聴かず着工にお墨付きを与えた裁判官。国民・住民の「知る権利」を裏切った朝日幹部…。彼らの中に、長良川の現状に心を痛めている人はいるのだろうか。もう頭の片隅にも多分、河口堰のことはないはずだ。
もちろん、結果に責任を取ろうとする人は一人もいない。政治、行政、司法、メディアのすべてが壊れたら国・国土がどうなるか、河口堰は身をもって教えてくれた。
「国破れて山河在り 城春にして草木深し 時に感じては花に涙を注ぎ
別れを恨んでは鳥にも心を驚かす」。中国・唐時代の詩人・杜甫は理想の政治を夢見て仕官の道を志す。だが、政治は腐敗し、戦争も絶えない。追われるように都を出て、失意の中で山河に心を癒された。
◇自然破壊から国土破壊へ
今、この国では、「国を守る」として集団的自衛権容認・安全保障法制で、憲法9条基軸の「平和国家」から大きく転換しようとしている。しかし、身近な「自然」すら守らない政治家・官僚が、「国を守る」と言って、誰が信用するのだろうか。
何の利点も工事をして自然破壊だけを進めて、結果に責任を取らない人たちが、この安保法制で戦争に突き進み、多くの国民の命が失われても責任を取ることはない。それも長良川が教えてくれた。
本当に「国を守る」とは、川とともに生きた大橋さんのような人たちが自分たちに身近な自然を守ることが原点にあるはずだ。「外国の脅威」などと言う人がいる。しかし、いかに邪悪な外国があったしても、長い目で見れば、美しい自然さえ残っていれば、こうした人々をその自然から引き離すことは出来ない。
安保法制が制定され、この国の軍隊が連携する国と一緒に戦うことになれば、相手国からは「敵」とみなされる。場合によっては核攻撃の脅威に直面する。杜甫はまだ美しい「山河」に癒された。でも、この国の「山河」が核攻撃で壊されるとしたら…。私たちは今後、何によって癒されたらいいのだろうか。
≪筆者紹介≫ 吉竹幸則(よしたけ・ゆきのり)
フリージャーナリスト。元朝日新聞記者。名古屋本社社会部で、警察、司法、調査報道などを担当。東京本社政治部で、首相番、自民党サブキャップ、遊軍、内政キャップを歴任。無駄な公共事業・長良川河口堰のウソを暴く報道を朝日から止められ、記者の職を剥奪され、名古屋本社広報室長を経て、ブラ勤に至る。記者の「報道実現権」を主張、朝日相手の不当差別訴訟は、戦前同様の報道規制に道を開く裁判所のデッチ上げ判決で敗訴に至る。その経過を描き、国民の「知る権利」の危機を訴える「報道弾圧」(東京図書出版)著者。特定秘密保護法違憲訴訟原告。