【書評】新聞社の「営業秘密」を暴露した清水勝人著、『新聞の秘密』
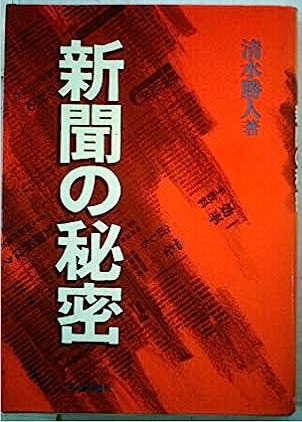
『新聞の秘密』(日本評論社)は、半世紀前に出版された本である。執筆者は新聞社販売局の社員だったと聞いている。「清水勝人」という著者名は匿名らしい。
この本には、新聞社の営業秘密が詳細に記されている。「押し紙」を隠すために、新聞社がどのような裏工作をしているのかなどが、詳細に述べられている。新聞社の営業上の秘密は、清水氏を皮切りに、多くの人々が問題視してきたが、隠蔽状況はほとんど変わっていない。裁判所も、営業秘密を隠蔽する方向で新聞社に協力している。
たとえはABC部数をかさ上げするために、新聞社が販売店に「押し紙」を搬入すると同時に、損害を補填するための補助金を支給している事実は、新聞社にとっての重大な営業秘密である。公になってしまうと、新聞の信用が失墜してしまうからだ。
しかし、「押し紙」は新聞ジャーナリズムの信用にかかわる根本的な問題なので、極めて公益性が高い。
『新聞の秘密』は、新聞社の営業秘密をはじめて暴露した素晴らしい本である。残念ながら現在では書店で入手できない。国会図書館では入手可能だ。
新刊の『新聞と公権力の暗部』-(「押し紙」問題とメディアコントロール)、書店販売が開始
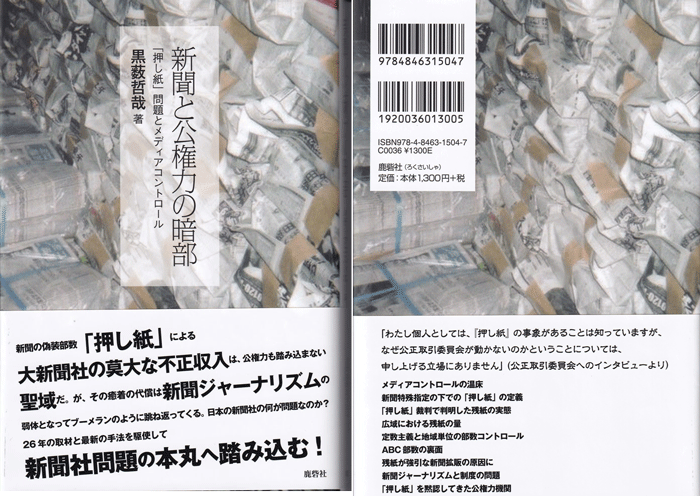
新刊の『新聞と公権力の暗部』-(「押し紙」問題とメディアコントロール)《鹿砦社》の書店販売が開始された。
この本は新聞ジャーナリズムが機能しなくなった原因が、新聞社のビジネスモデルの中にあることを論じたものである。新聞社は「押し紙」によって莫大な利益を得ている。わたしの試算では、業界全体で年間に少なくとも932億円の不正な金が新聞社に流入している。
公権力機関がこの点に着目して、故意に「押し紙」問題を放置すれば、暗黙のメディアコントロールが可能になる。新聞は世論誘導の巧みな道具に変質する。
このあたりのからくりをわたしは本書で容赦なく暴露した。
とかく新聞が堕落した原因を、記者個人の資質や職能の問題と捉える風潮があるが、本書はその原因を新聞のビジネスモデルの中に潜む客観的な問題に求めた。
またこれまでわたしが著した「押し紙」問題の書籍の反省点も踏まえて、バブル期における「積み紙」の存在を認めるなど、新聞業界の実態をより客観的に把握している。「押し紙」問題を扱いながらも、本書のテーマは、公権力機関によるメディアコントロールのからくりである。
【書評】ガルシア=マルケス『ママ・グランデの葬儀』、独裁者の死をめぐる民衆の心、悲しみからフェスタへへ
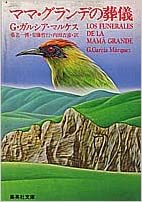
『ママ・グランデの葬儀』は、コロンビアのノーベル文学賞作家、ガルシア=マルケスの短編小説である。わたしがこの本を読んだのは20年以上もまえで手元に書籍はなく、記憶を頼りに書評を書いているので、内容を誤解している可能性もあるが、おおむね次のような内容だった。
200歳になる村の長老格の老婆が他界する。この200歳という設定は、前世紀までラテンアメリカの政治を語る際のひとつのキーワーになっていた絶対に権力の座を降りない独裁者の比喩である。魔術的リズムと呼ばれる手法で、誇張法のひとつである。
この老婆の死は村を喪の空気に包む。大規模な葬儀が執り行われる。次々と人が集まってきて、葬列は大群衆に膨れ上がる。するとあちこちに屋台が現れる。人々の談笑がはじまる。すると長老を失った悲しみが薄れ、陽気な空気が流れはじめる。そして最後には、悲しみの葬列が独裁者の死を祝うフィエスタに変質する。民衆の歓喜が爆発する。
【新刊案内】『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』、スラップ訴訟への警鐘、まもなく販売開始
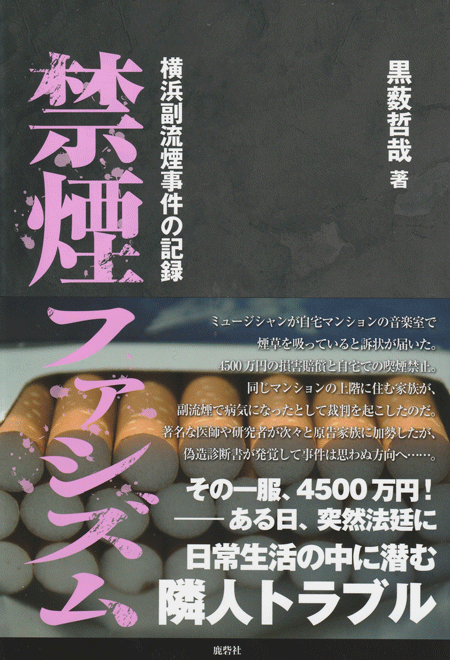
『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)の書店販売が2月1日に始まる。この本はメディア黒書で繰り返し取り上げてきた横浜副流煙事件をコンパクトにまとめたものである。
煙草の副流煙で「受動喫煙症」になったとして、同じマンションの隣人が隣人を訴えた4500万円訴訟の発端から結末までを読みやすく構成している。スラップ訴訟の中身と加害者の自滅を詳しく記録した。内容は次の通りである。
1章、隣人トラブルから警察沙汰に
2章、事件の発覚を警戒する二人の弁護士
3章、本人訴訟とジャーナリズムの選択肢
4章、神奈川県警介入のグレーゾーン
5章、3通の診断書から浮上した疑惑
6章、診断書をメール電送した異常
7章、「受動喫煙」外来への潜入取材
8章、医師法第20条違反を認定した1審判決
エピローグ
本のキャッチフレーズも紹介しておこう。
「その一服、四五〇〇万円!、ある日、突然に法廷に。日常生活に潜む隣人トラブル」
「ミュージシャンが自宅マンションの音楽室で煙草を吸っていると訴状が届いた。4500万円の損害賠償と自宅での喫煙禁止。同じマンションの上階に住む家族が、副流煙で病気になったとして裁判を起こしたのだ。著名な医師や研究者が次々と原告家族に加勢したが、偽造診断書が発覚して事件は思わぬ方向へ・・・。日常生活の中に潜む隣人トラブル。
タイトル:『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)
価格:1200円+税
著者:黒薮哲哉
出版社:鹿砦社
【書評】『抵抗と絶望の狭間』掲載の「佐藤栄作とヒロシマ」、浮き彫りになる被害者の視点と第三者の視点

理論的に物事を理解することと、感覚として物事を受け止めることは、性質が異なる。前者は、「象牙の塔」の世界であり、後者は実生活の世界である。両者が結合したとき、物事の本質が具体像となって浮上してくる。それゆえに筆者のような取材者は、両者の距離を縮めるために、現場へ足を運ぶことがなによりも大切なのだ。
『抵抗と絶望の狭間』に収録された「佐藤栄作とヒロシマ」を執筆した田所敏夫氏は、みずからの家系について次のように書いている。
「広島市内で多量の被爆をした3人の伯父は五十代を迎えると、申し合わせたようにがんで亡くなった。発症から逝去までが短かったことも共通している。母は、数年前、『百万人に一人の割合』で発症すると医師から診断を受けた珍しいがんに罹患した」
田所氏自身もその翌年に癌に罹患していることが判明した。とはいえ田所氏は、1965年生まれで、直接、ヒロシマの閃光を浴びたわけではない。が、それにもかかわらず脳裏には、「広島の空に沸き上がった巨大なキノコ雲と、その下で燃え上がった町や、焼かれたたんぱく質の匂いが現実に経験したかのように刻み込まれている」。
広島の悲劇から76年を経て、田代氏は自らも世代を跨いだ原爆の被害者になったからにほかならない。身近に被爆者がいたことも、関係している。
家系に短命な人が多いわけではなかった。しかし、癌の世代間連鎖の当事者になり、田所氏の記憶の中で、1971年は特別な年になった。この年の8月6日、佐藤栄作が首相として初めて広島を訪れた。それ以来、平和記念式典で首相が「台本」を読み上げる儀式が定着した。菅義秀は、その台本を読み間違えた。しかし、原爆の被害者は、それを単なる知性の問題として受け止めることはできない。誤読は枝葉末節であって、「台本」そのものが、被爆者に対する耐え難い侮辱なのだ。
【書評】『抵抗と絶望の狭間』、半世紀を経た現在の視点、連合赤軍事件は日本の「組織思想」が招いた悲劇

本書の冒頭インタビューで中村敦夫氏は、思い立ったらとにかく現場へ行く重要性について、次のように述べている。
「そこへ行くと行かないでは大違いで、行って目的が失敗したとしても、損ということはないですよね。もの凄く学ぶっていうことが残るわけです。だから、行動するときは迷わないですよね。反省はあとですればいいんだから、最初から反省してやらないというのは、人間が全然発展しないですよ。痛い目に遭うのだって勉強ですから。」
『抵抗と絶望の狭間』は、1960年代後半から1970年代にかけた時代を検証するシリーズの第4弾である。(関連図書を含めると第5弾)。戦後史の中で、この時期に津波のように日本列島に押し寄せた社会運動の高まりと、その後の衰退現象の検証を避けて通ることはできない。当時の社会運動やそれに連想した文化を肯定するにしろ、否定するにしろ、社会が激しく動いていたことは紛れない事実であるからだ。当時、小学生だった筆者も、テレビを通じて、日本でなにか新しい流れが生まれている予感を持ったものだった。
その激動の現場へ飛び込んだ人々が、半世紀を経た現在から、当時を検証したのが本書である。時代が執筆者たちの現在の生き方に何らかの影響を及ぼしていることが読み取れる。
2021年12月08日 (水曜日)
【書評】加藤やすこ著『スマートシティの脅威』、地上から宇宙へ、エスカレートする電磁波公害の新しい視点を提供
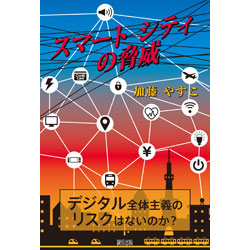
電磁波の工業利用に歯止めがかからない。かつて電磁波問題といえば、高圧電線や変電所、あるいは携帯電話基地局の直近に住む住民が受ける人体影響の検証が主流を占めていた。家電からもれる電磁波も議論の的になっていた。
しかし、このところ電磁波問題の全体像が変化してきた。宇宙を飛行する無人の基地局が電磁波の放射源となり地球全体を汚染する時代の到来が秒読み段階に入り、その安全性を検証することが電磁波問題の新しい視点として登場した。従来とは比較にならないほど、広い視野が求められるようになってきたのだ。
本書はそんな時代を見据えて、電磁波による健康被害はいうまでもなく、プライバシーの危機なども総括的に捉え、新世代公害に警鐘を鳴らしている。
【書評】『一流の前立腺がん患者になれ』、治療方法を選ぶための手引き、客観的なデータで構成された患者のためのやさしい専門書

東洋人は、90歳を超えると約半数が前立腺がんになるといわれている。前立腺がんの患者は年々増えている。患者数はいまや胃がんを上回っている。
2019年の冬、わたしは『一流の前立腺がん患者になれ!』の著者である安江博さんを、茨城土浦市にあるつくば遺伝子研究所に訪ねたことがある。滋賀医科大付属病院事件を取材することが目的だった。これは、前立腺がん治療の著名な開発者・岡本圭生医師を病院から追放した事件で、当時、岡本医師の患者だった安江さんも影響を受けた。
わたしは事件の経緯だけではなく、前立腺がん治療そのものについても尋ねた。何を根拠として安江さんは、岡本医師の治療法を選択したのかを尋ねたのである。
【書評】『暴力・暴言型社会運動の終焉』、反差別運動の表と裏、師岡康子弁護士の危険な思想「師岡メール」を公開、マスコミが報じない事件の特徴を浮き彫り
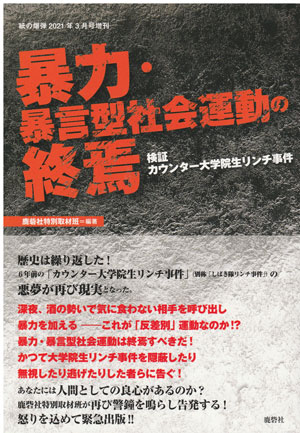
ジャーナリズム活動を評価する最大の要素は、テーマと視点の選択と設定である。とりわけテーマの選択は決定的だ。それを決めるのが編集者の感性であり、問題意識なのである。
同時代で起きている事件から、どの事件をクロースアップするかが決定的な鍵になる。たとえばこのところ、マスコミは森喜朗氏の女性差別発言を重視して徹底取材を行い、ニュース番組はいうまでもなく、ワイドショーでも連日のように差別問題の報道を続けている。森氏の発言内容そのものはおかしいが、相対的に見ると炎上させるほどのレベルではない。完全にスタンピード現象を起こしている。
その一方で、同じ五輪・パラがらみの事件でも、時価にして約1300億円の選手村建設用地(公有地)を、東京都が約130億円で開発業者へ「たたき売り」した事件は、ほとんど報じない。この事件は住民訴訟にまで発展している。しかし、森失言ほど重要ではないと判断して、沈黙しているのである。
日本のマスコミの能力は、実はこのレベルなのである。
差別表現をめぐる部落解放同盟との論争、『紙の爆弾』(12月号)

『紙の爆弾』(2020年12月)の最新号は、筆者が寄稿した「徒(いたずら)に『差別者』を発掘してはならない」と題する一文を掲載した。内容については、同誌で確認してほしい。
この寄稿は、『紙の爆弾』の先月号から始まった「『士農工商ルポライター』は『差別を助長する』のか?」と題する連載企画の第2回の原稿である。
企画の発端は、同誌9月号が掲載した昼間たかし氏のルポの中で、昼間氏が使った次の表現に対して、部落解放同盟が鹿砦社側に釈明を求めたことである。
【書評】『一九七〇年 端境期の時代』、よど号の元メンバーが近くて遠い祖国へ届けた言葉
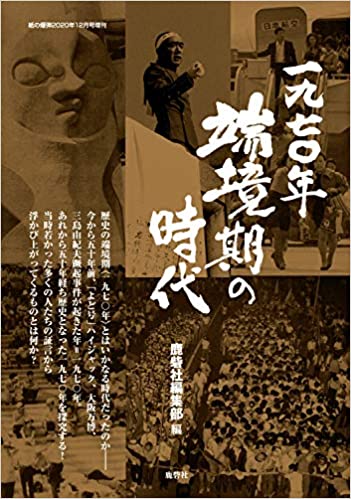
ノンフィクション作品の質を決める最大の要素は、テーマの重さである。さらに欲を言えば実体験。そして表現という点では、第3者がそれを取材して書くよりも、当事者が綴る方が説得力が何倍にも増す。若林盛亮氏の「『よど号』で飛翔五十年、端境期の闘いは終わっていない」は、これらの条件を兼ねそなえた傑作だ。著者は、ピョンヤンから、同時代の日本へメッセーを送っている。
若林氏についてインタネットで検索して、筆者は次の経歴をみつけた。
滋賀県草津市生まれ。滋賀県立膳所高等学校を経て同志社大学経済学部に入学。在学中、1970年によど号ハイジャック事件を起こし、北朝鮮に亡命。 1976年に結婚し、妻である若林佐喜子と平壌に在住している。(ウィキペディア)
【書評】『生保レディのリアル』、 職場での巧みな洗脳の実態

職場を舞台としたノンフィクションは多い。広く知られている書籍としては、タクシードライバーの日常を描いた『タクシー狂躁曲』(梁石日、ちくま文庫)やトヨタの労働現場を潜入取材で告発した『自動車絶望工場 』(鎌田慧、講談社文庫)などがある。わたし自身もメキシコのホンダ技研の労働実態を取材した『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室)を書いた体験がある。
『生保レディのリアル』は、女性の生命保険外交員の日々を内部から鮮明に記録したルポルタージュである。具体的な事実を通じて、そこで進行している洗脳による「会社人間」の養成と搾取の実態が読み取れる。
週刊新潮が横浜副流煙裁判を報道、この裁判の何が問題なのか?

本日(13日)発売の『週刊新潮』が、横浜・副流煙裁判について報じている。タイトルは、『「反たばこ訴訟」で認定された「禁煙学会理事長」の医師法違反』。日本禁煙学会の作田学医師の医療行為が医師法20条に違反していることが認定された経緯を伝えている。
ところでこの裁判は、原告による訴権の濫用である可能性がある。周知のように、原告が被告に請求した金額は4500万円だった。請求額としては極めて高額だ。しかし、高額訴訟であれば、特にめずらしくはない。わたしも読売新聞社から総額で約8000万円請求されたことがある。
