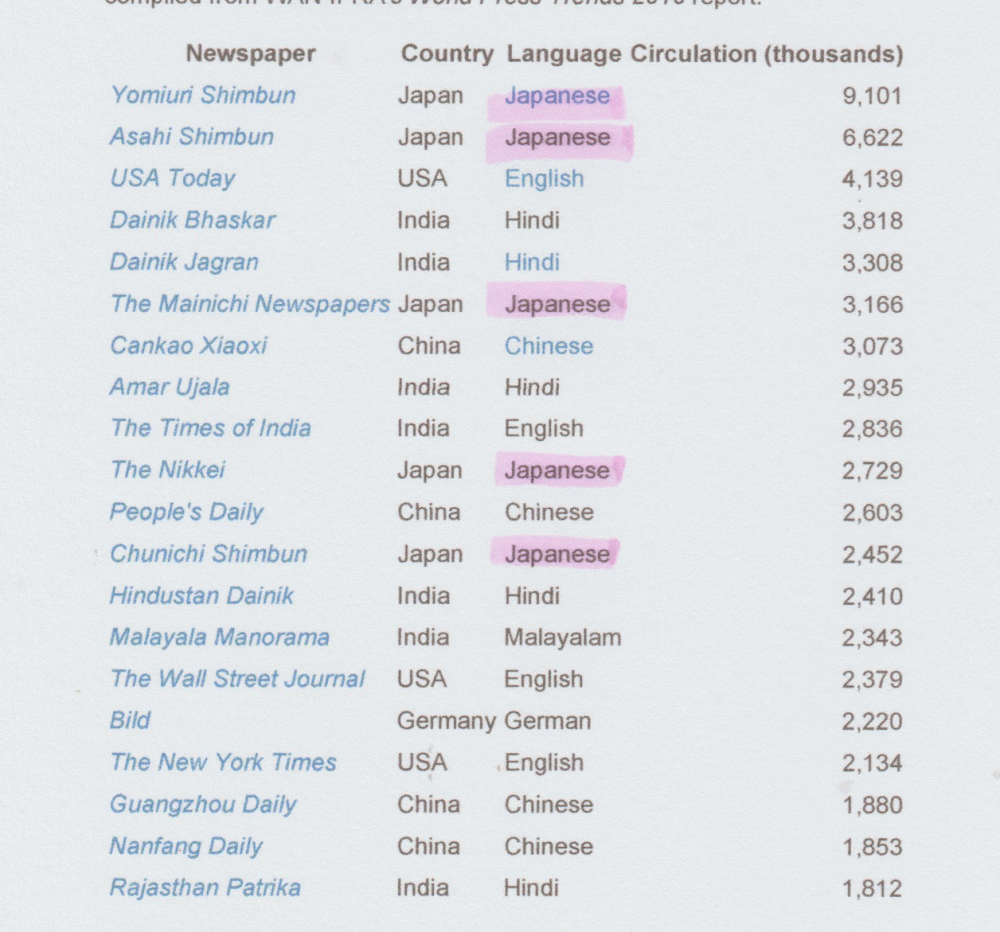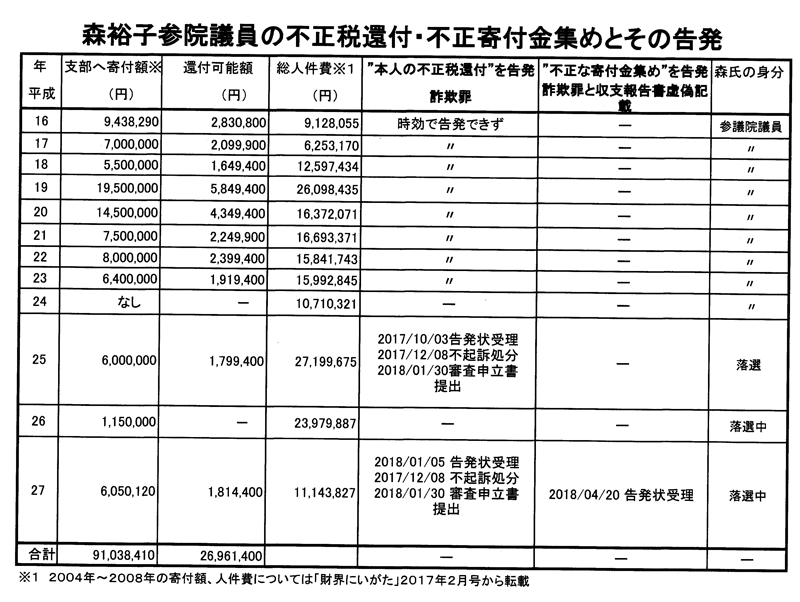世界新聞発行ランキング、読売・朝日が1位と2位を独占するも、「注釈」で「押し紙」に言及、NYTの著しい台頭

英語版のウィキペディアに掲載されている新聞発行部数(2016年度)ランキングに、日本の新聞社が慣行化してきた「押し紙」についての注釈があることが分かった。ランキングは、世界新聞協会(WAN-World Association of Newspaper)が発表したデータを転載したもの。日本の新聞社がこれまでどおりに上位を占めているが、次のような注釈がついている。
【注1】
幾つかのデータについては議論の余地がある;日本の新聞の発行部数は、「押し紙」、取引先に過剰な新聞を供給することによる(数字の)誇張の影響下にあるとの主張もある。■出典(Notes 1)
海外でも、日本の新聞社の「押し紙」が問題視されはじめているのだ。
◇10位内に日本から4社
ちなみにランキングは次の通りである。
◇ニューヨークタイムズが台頭
 興味深いのは、ニューヨークタイムズの部数変動である。筆者が初めて海外の新聞発行部数を調査した約20年前、1996年の時点でニューヨークタイムズの発行部数は107万部だった。
興味深いのは、ニューヨークタイムズの部数変動である。筆者が初めて海外の新聞発行部数を調査した約20年前、1996年の時点でニューヨークタイムズの発行部数は107万部だった。
ところが2016年に213万部に、2018年9月末の段階では、同紙の電子版有料会員数が254万人を超えている。(共同通信などの報道による。)これは「紙」から「電子」への流れを象徴する現象だろう。
筆者の推測になるが多くの読者を獲得できた背景に、英語が世界の共通言語になっている事情があるようだ。対象となる市場が日本語と比較にならないほど大きいのがその要因だろう。インターネットのない時代は、日本でニューヨークタイムズを読む人は、ほんの限られた層だった。ところがいまは誰でも、電子版で読める。
もちろんジャーナリズムの評価が高いことは、改めて念を押すまでもないが。
「紙」新聞が崩壊へのカウントダウン、年間で読売41万部減、朝日は36万部減、毎日は31万部減、中央紙だけで京都新聞社3社分の部数が消えた、最新のABC部数

新聞の没落傾向に歯止めがかからない。新聞の発行部数を示すABC部数(2018年10月度)によると、朝日新聞は前年同月比で約36万部減、読売新聞は約41万部、日経新聞は約30万部減、毎日新聞は約31万部減、産経新聞は約11万部減となった。
中央紙5紙のABC部数は次の通りである。()は前年同月比である。
朝日 5,763,923(-357,682)
毎日 2,646,202(-314,076)
読売 8,328,646(-406,279)
日経 2,398,162(-297,093)
産経 1,465,842(-112,190)
合計 20,602,775(-1,487,320)
これら5紙で、総計約149万部が減ったことになる。これは京都新聞(発行部数約43万部)クラスの地方紙が、3社消えたに等しい。新聞業界の深刻な内情が改めて浮彫になった。
ちなみにABC部数には、「押し紙」が含まれている。「押し紙」とは、新聞社がノルマとして新聞販売店に買い取りを強要する新聞のことで、昔から業界内で大きな問題になってきた。新聞ばなれが進み、販売店の経営が悪化してくると、「押し紙」の負担が重くなる。そこで新聞社は、販売網を維持するためにやむなく「押し紙」を減らすことがある。その結果、ABC部数も減る。
このところの極端な部数減の背景には、単に新聞ばなれだけではなく、新聞社が「押し紙」を減らさざるを得なくなっている事情もあるようだ。それだけ経営悪化が深刻になっているのだ。
なお、折込広告の販売店への割り当て枚数は、ABC部数に準じる基本原則がある。従ってABC部数の中に「押し紙」が含まれていれば、それとセットになっている折込広告も、配達されないまま「押し紙」と一緒に廃棄されている可能性が高い。
◇見えざるメディアコントロール
こうした商取引の「闇」が業界の汚点となり、仮にそれを政府が逆手に取れば、合法的な摘発の口実になる。ここに日本の新聞ジャーナリズムの決定的な弱点があるのだ。それは「忖度」の温床であり、メディアコントロールの見えざるからくりなのである。
新聞販売店の整理統合は恐ろしい勢いで進んでいる。朝日新聞と読売新聞の販売店が統合されるケースも生まれている。
倒産する新聞社がでるのは時間の問題だろう。「紙」新聞の崩壊は秒読み段階に入った。
この1年の減部数、朝日は約34万部、読売は約37万部、日経は約31万部 西日本新聞は宮崎県と鹿児島県で休刊、埼玉県で朝日と読売の合売店が誕生

2018年9月度のABC部数を紹介しよう。新聞の没落傾向にはまったく歯止めがかかっていない。朝日はこの1年で約34万部、読売は約37万部、日経は約31万部の減部数となった。
繰り返し述べてきたように、ABC部数には「押し紙」が大量に含まれているので、ABC部数の減部数がそのまま読者数の減少を意味するわけではない。読者は減っているが、同時に「押し紙」を減らさなければ、販売網が維持できないほど、経営が悪化していると考えるのが妥当だ。
中央紙のABC部数は次の通りである。
朝日:5,793,425(342,912)
毎日:2,699,790(242,457)
読売:8,346,122(367,863)
日経:2,393,195(309,389)
産経:1,495,586(60,059)
◇進む販売店の統合
極端な部数減の下で新聞販売店の整理統合が進んでいる。業界紙によると埼玉県の西部地区にある朝日新聞と読売新聞の販売店が統合され、毎日、産経、日経を含む全紙を配達する体制になったという。
専売店単独では、経営が成り立たなくなってきたのである。
販売店の合売店化は、今後、急激に進みそうだ。
一部の新聞社が関東北部で近々に夕刊を廃止するのではないかという情報も飛び交っている。
西日本新聞はこの4月から宮崎県と鹿児島県での発行を休止した。また、日経新聞は、やはり4月に沖縄県で夕刊を休止した。
日本新聞協会に記事の訂正を申し入れ、同協会が掲載した対読売裁判の記事

筆者は、15日、日本新聞協会に対して、同協会が『新聞協会報』に掲載し、その後、ウエブサイトに転載した、「読売への損害賠償、黒藪氏の請求棄却 福岡地裁」と題する記事の訂正を申し入れた。
6年前の2012年7月19日付け(ウエブサイト)の記事で、前日に知人から記事の存在を知らされ、内容を確認したところ、事実関係に誤りがあったからだ。少なくとも読者に誤解を招き、それが記録として残ってしまう懸念があったからだ。
交渉の結論を先に言えば、日本新聞協会は暫定的に筆者が指摘した記事を削除した。筆者から削除を求めたのではなく、編集部の判断で削除したのである。次の記事である。
フリージャーナリストの黒藪哲哉氏が言論抑圧を目的に不当に裁判を起こされたなどとして、読売の東京・大阪・西部各本社などに損害賠償を求めた訴訟の判決が7月19日、福岡地裁であった。田中哲朗裁判長は、「紛争の解決を裁判所に求めるのは法治国家の根幹で、訴えを提起するのが違法行為になることはない」として請求を退けた。
黒藪氏は2007年、自身のウェブサイトに西部本社法務室からの文書を掲載。これに対し読売西部は削除を求め、削除しない場合は法的手段をとると文書で通知した。黒藪氏は文書によって脅迫を受けたなどと主張した。
読売側は、法的手段をとるとの記載を通常、脅迫と受け取ることはないと反論していた。
読売新聞グループ本社広報部は「当方の主張が全面的に認められており、妥当な判決と考える」とのコメントを出した。
◇「一連一体の言論弾圧」
読売との係争は、記事の通り2007年に始まった。読売の江崎法務室長が筆者に対して、メディア黒書(当時は新聞販売黒書)に掲載した読売の内容証明文書(名義は江崎氏)の削除を求めてきたのが発端だ。その後、この事件は著作権裁判にエスカレートした。
ちなみに筆者は、この著作権裁判を皮切りに読売から、約1年半の間に3件の裁判を起こされた。請求額は総計で約8000万円。本来であれば、廃業に追い込まれていたが、福岡県の江上武幸弁護士らが弁護団を結成して、全くの無報酬で、東京地裁や埼玉地裁まで支援に来てくれて、危機を乗り切ったのである。
読売が仕掛けてきた3件の裁判の結果は次の通りだった。
1,著作権裁判:地裁から最高裁まで筆者の勝訴
2,名誉毀損裁判(メディア黒書の記事):地裁、高裁は筆者の勝訴。最高裁で読売が逆転勝訴。
3,名誉毀損裁判(週刊新潮の記事):地裁から最高裁まで読売の勝訴。
これら3件の裁判に対して、筆者は、「一連一体の言論弾圧」という観点から、読売3社を提訴したのである。
◇内容証明文書の名義を偽って黒薮を提訴
筆者が問題とした新聞協会の記事で事実関係が誤っているのは、第2段である。再度、引用しておこう。
黒藪氏は2007年、自身のウェブサイトに西部本社法務室からの文書を掲載。これに対し読売西部は削除を求め、削除しない場合は法的手段をとると文書で通知した。黒藪氏は文書によって脅迫を受けたなどと主張した。
この段落は、著作権裁判についての記述である。「黒藪氏は文書によって脅迫を受けたなどと主張した」と書かれているが、私が恫喝だと主張したのは、読売による3件の「一連一体裁判」に対してである。
著作権裁判で筆者が問題にしたのは、「恫喝」や「脅迫」ではなく、読売が虚偽の事実を前提に裁判を起こしたことである。
読売の江崎法務室長は、メディア黒書に筆者が掲載した文書(筆者あての内容証明文書)は、自分が書いたみずからの著作物であるから、削除するように求めてきたのである。(厳密に言えば、著作者人格権を理由に文書の削除を主張したのである。)
ところが裁判の中で、問題の内容証明文書は、江崎氏が執筆したものではなく、読売の代理人の喜田村洋一自由人権協会代表理事の執筆である高い可能性が認定されたのだ。それを根拠に、門前払いのかたちで江崎氏らは敗訴したのである。江崎氏が著作者人格権の所有者ではないので、もともと、著作者人格権を根拠とした提訴権はなかったのだ。
著作権裁判で筆者が脅迫を受けたと感じたかどうかは、枝葉末節であって本質的なことではない。筆者の主張は、内容証明文書の作成者が江崎氏であるという虚偽の事実を前提に裁判を起こした行為を断罪すべきだというものだった。そのための「反訴」だったのだ。
著作権裁判で地裁判決が出た後、筆者の弁護団が発表した声明を再度紹介しておこう。江崎氏や喜田村氏が何をやったかがよく分かる。
◇弁護士懲戒請求
その後、喜田村弁護士に対して弁護士懲戒請求を行った。次のような内容である。
【参考記事】喜田村洋一弁護士らによる著作権裁判提起から10年、問題文書の名義を偽って黒薮を提訴、日弁連はおとがめなし①
【参考記事】喜田村弁護士に対する懲戒請求、第2東京弁護士会の秋山清人弁護士が書いた議決書の誤り②
新聞没落が加速、読売が年間で約39万部の減部数、朝日は約33万部減、2018年7月度の新聞のABC部数

2018年7月度の新聞のABC部数が明らかになった。それによると、読売新聞が年間で約39万部を減らしたのを筆頭に、朝日新聞も約33万部の減部数、毎日新聞も約23万部の減部数と、軒並み大幅に部数を減らしている。新聞の没落に拍車がかかっている。
日刊紙全体でみると、1年間で162万部の減部数。地方紙は、中央紙ほど減部数を招いてはいないが、それでも低落傾向に変わりはない。
中央紙の部数は次の通りである。()は前年同月比である。
朝日:5,841,951(-325,986)
毎日:2,733,053(-225,206)
読売:8,386,497(-385,198)
日経:2,407,722(-292,840)
産経:1,464,724(-56,991)
なお、ABC部数には、「押し紙」が含まれているので、実際に配達されている部数(実配部数)はABC部数よりもはるかに少ない可能性が高い。また、減部数の原因は、読者の減少に加えて、新聞社が「押し紙」を減らした結果である可能性が高い。それだけ新聞販売店が経営難に陥っているといえるだろう。
福岡高裁が認定した読売の「押し紙」を考える

「押し紙」は、日本の新聞社の恥部だが、今だにその存在を新聞人が認めていないことを読者はご存じだろうか? 「押し紙」問題を指摘すると、必ず次のようなニュアンスの言葉が返ってくる。
「あなたが言っている『押し紙』とは、残紙のことだろう」
新聞販売店が自分の意思で新聞の仕入れ部数を決めているので、「押し紙」ではないという恐るべき詭弁である。たしかに帳簿上は、販売店が仕入れ部数を決めたことになっているが、その背景に新聞社による優越的地位の濫用がある。
2016年7月、『月刊Hanada』に「押し紙」についての記事を掲載したところ、読売の滝鼻太郎広報部長が編集部に抗議文を送付してきた。次に紹介するのは、抗議に対する筆者の反論である。背景を知らない人にも理解できるように反論文を構成している。
滝鼻氏の抗議の中身は、究極のところ真村訴訟の福岡高裁判決が読売の「押し紙」を認定したとするわたしの判例解釈は間違っているというものだ。
【反論文の全文】
貴殿から送付されました抗議書に対して、記事の執筆者である黒薮から回答させていただきます。まず、貴殿が抗議対象とされている箇所を明確にしておきます。と、言うのも貴殿の抗議書は、故意に問題の焦点を拡大しており、そのために議論が横道へそれ、本質論をはずれて揚げ足取りに陥っているきらいが多分に見うけられるからです。
貴殿が問題とされている箇所は、枝葉末節はあるものの、おおむね『月刊Hanada』 (7月号)に掲載された「公取が初めて注意『押し紙』で朝日も崩壊する」(黒薮執筆)と題する記事の次の引用部分です。この点を確認し、共有する作業から、わたしの反論を記述します。
「裁判の結果は、真村さんの勝訴でした。2007年12月に、最高裁で判決が確定しました。裁判所は「真村さんが虚偽報告をしていたのは批判されるべきだが、その裏には読売の強引な販売政策があった」との見解を示し、真村さんの地位を保全したのです。この裁判で裁判所は、新聞史上初めて、押し紙の存在を認定したのです」
抗議書によると、貴殿は、2007年12月に最高裁で確定した第1次真村裁判の判決(西理裁判長)が貴社による「押し紙」政策を認定しているとするわたしの判例解釈は誤りだという見解に立ち、抗議の書面を送付されたわけです。
さらに貴殿は第2次真村裁判についても抗議書の中で言及されておりますが、これについてはわたしは本件記事の中ではまったく言及しておらず、貴殿の主観によって導かれた議論のすり替えに該当しますので、補足的に後述するにとどめ、まず、第1次真村裁判の判決が、なぜ貴社の「押し紙」政策を認定したと解釈し得るのかを説明させていただきます。
◇真村事件とは
貴殿もご存じのように真村裁判は、貴社がYC広川(福岡県広川町)の営業区域を隣接店へ譲渡する方針を打ち出されたことに端を発する事件です。その隣接店の店主は、暴力事件を起こしたこともあるSという人物の弟でした。Sは〝大物店主〝でした。Sについては、S尋問調書(平成17年○月○日)にも記録されております。この人物の存在なくして、貴社西部本社の新聞販売政策を語ることはできません。
第1次真村裁判は、真村店主が貴社の方針に抗議したのに対抗して、貴社が強制改廃を言い渡し、それを受けて、真村氏がやむなく提訴するに至った経緯があります。
◇「押し紙」と「積み紙」
この裁判の最大の争点となったのは、YC広川にあった「残紙」の性質をどう解釈するのかという点でした。具体的に言えば、「押し紙」と解釈するのが妥当なのか、それとも「積み紙」と解釈するのが妥当なのかという論点です。これについても、貴殿は本件議論の前提事実として認識されているものと思います。
「押し紙」とは、貴殿も抗議文の中で示されているように、「新聞発行業者が、正当かつ合理的理由がないのに、販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給」する結果として発生する「残紙」のことです。端的に言えば、手口の差こそあれ、「押し売り」された新聞のことです。
これに対して「積み紙」とは、販売店の側が、販売(配達)部数を超えた数量の新聞を注文した結果として発生する「残紙」を意味します。販売店が販売予定のない新聞をあえて注文する行為に走る背景には、次のような特殊な事情が存在します。販売店に割り当てられる折込広告の枚数は、新聞の搬入部数に一致させる基本原則がある。当然、残紙に対しても折込広告はセットとして割り当てられる。
このような構図のもとでは、折込広告による収益が、「押し紙」による損害(「押し紙」分の新聞の卸代金)を相殺し、さらに水増し利益を生むことがままある。これこそが販売店が販売予定のない新聞をあえて注文する最大の理由にほかなりません。他にもありますが、本論からはずれるので言及は控えます。
「押し紙」と「積み紙」のバランスを取りながら、時には販売店主との談合により、広告主を欺きつつ、販売店と新聞社の経営安定を図る戦略が、貴殿ら日本の新聞人が構築されたビジネスモデルになっていることは、貴殿も十分に認識されているものと思います。それがいま、大きな世論の批判を受けていることも周知の事実です。それゆえに本件記事は、極めて公益性の高いテーマで貫かれているといえます。
真村裁判で貴社は、YC広川の残紙(約130部)は「積み紙」であり、それが貴社の信用を失墜させる要因なので、同店の懲罰的な改廃には正当な理由があるという趣旨の主張を展開されました。一方、原告真村氏の弁護団は、同店の残紙は、優越的地位の濫用のもとで生じた「押し紙」なので改廃理由には該当しないと主張しました。つまりこの裁判の最大の争点は、YC広川の残紙がどのような性質のものであるかという点でした。裁判所はこの点を検証したのです。
福岡高裁判決は、貴社の行為を次のように認定しています。引用文中の「定数」とは新聞の搬入部数のことです。
「このように、一方で定数と実配数が異なることを知りながら、あえて定数と実配数を一致させることをせず、定数だけをABC協会に報告して広告料計算の基礎としているという態度が見られるのであり、これは、自らの利益のためには定数と実配数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢であると評されても仕方のないところである。そうであれば、一審原告真村の虚偽報告を一方的に厳しく非難することは、上記のような自らの利益優先の態度と比較して身勝手のそしりを免れないものというべきである。」
判決のこの箇所では、貴社が実配部数と搬入部数の間に齟齬があることを認識していながら、正常な取引部数に修正しなかった事実が認定されています。つまり貴社が注文部数を決めていたのです。さらに裁判所は、その背景に、貴社の部数への異常とも言える執着があることを、次のように認定しています。
「販売部数にこだわるのは一審被告(黒薮注:貴社のこと)も例外ではなく、一審被告は極端に減紙を嫌う。一審被告は、発行部数の増加を図るために、新聞販売店に対して、増紙が実現するよう営業活動に励むことを強く求め、その一環として毎年増紙目標を定め、その達成を新聞販売店に求めている。このため、『目標達成は全YCの責務である。』『増やした者にのみ栄冠があり、減紙をした者は理由の如何を問わず敗残兵である、増紙こそ正義である。』などと記した文章(甲64)を配布し、定期的に販売会議を開いて、増紙のための努力を求めている。
米満部長ら一審被告関係者は、一審被告の新聞販売店で構成する読売会において、『読売新聞販売店には増紙という言葉はあっても、減紙という言葉はない。』とも述べている。」
ここでは貴社が販売店に新聞部数を押し付けるために実施した具体的な言動が記録として刻印されています。貴社の米満部長が、「読売新聞販売店には増紙という言葉はあっても、減紙という言葉はない」と公然と発言している事実。これなどは販売店が注文部数を決定できない貴社の販売政策をずばりと突いています。
◇自由増減を宣言する前は?
さらに判決は、貴社が販売店に対して新聞部数の「自由増減」を認めていなかった事実にも言及しています。「自由増減」とは、販売店が自由に注文部数を決定する権利を保証する制度を意味します。
貴社は皮肉にも真村店主に対して「自由増減」を言い渡しましたが、その経緯は次の通りです。
既に述べたように真村氏は、自店の営業区域を防衛しようとして貴社の方針に服従しなかったために、貴社から販売店の改廃を宣告されました。この改廃宣告に先立つ段階で貴社は、YC広川を「死に店」扱いにすると真村氏に通告しました。
「死に店」扱いとは、癌などの「死病」に例えて説明すると、患者本人ではなく医師が自分の判断で、延命措置をとらないことを意味します。つまり担当員の販売店訪問は取りやめ、販売政策に関する指示も提示しなければ、補助金も支給しない。さらに福利厚生を受ける権利も剥奪する方針を意味します。要するに情け容赦なく、販売店を「自然死」に追い込むことです。
真村氏は池本担当員から決別宣告のように、「死に店」扱いを明記したメモを突きつけられました。そこには、池本氏の自筆で、新聞に関しては「供給持続する」、ただし「自由増減」と明記されていたのです。貴社の「押し紙」を柱にしたビジネスモデルから真村店主を「村八分」にするがゆえに、真村氏に関しては、例外的に自由増減が適用されたのです。
このメモは、「池本メモ」と呼ばれ、後に裁判所へも「押し紙」政策の証拠として提出されました。
貴社がYC広川に対して「自由増減」を宣告する前の時期、そもそも真村店主には自由に注文部数を決める権限がなかったわけですから、貴社が「注文部数」を決めていたことになります。従ってYC広川の残紙は、貴社が真村氏の意思とは無関係に、販売政策に従って部数を決めた結果発生した「押し紙」にほかなりません。この事実ひとつを見ても、貴社の販売政策は独禁法の新聞特殊指定に抵触しております。
実際、福岡高裁判決は、「池本メモ」について次のように貴社の優越的地位の濫用を認定しております。
「池本は、同一審原告に対し、今後、新聞供給は継続すること、注文部数その他につき自由に増減できること、増紙業務は依頼しないこと、読売会活動には不参画とすること、業務報告は不要であるし、池本ら担当員も訪店を遠慮すること、平成14年1月からは増紙支援をしないこと、所長年金積立は中止し、従業員退職金の補助等をしないこと、セールス団関係は、一審原告真村が直接処理すべきこと、特別景品は可能な限り辞退されたいこと、などを申し渡した。」
真村店主は「池本メモ」を突きつけられ、貴社の「鎖」を解かれ、貴社による「押し紙」を柱としたビジネスモデルの歯車から除外されたわけです。従って貴社本来の販売政策は、「押し紙」を前提としたものであるという結論になります。
以上が、本件記事の中でわたしが「この裁判で裁判所は、新聞紙上初めて、押し紙の存在を認定した」と記した理由です。
◇PC上の架空の配達地区
なお、貴殿も抗議書の中で言及されているように、裁判所が判決の中で真村氏による虚偽報告を批判しているのは事実です。「押し紙」を経理処理するためにPC上の「帳簿」に26区と呼ばれる架空の配達地区を設けていたのも事実です。
しかし、それは貴社を独禁法違反から守るために行った「押し紙」隠しの行為にほかなりません。事実、裁判所もこの点を批判した上で、次のような重要な記述を追加していますが、貴殿は最も肝心なこの追加部分を抗議書の中では故意に隠しています。それは次の記述です。判決は、真村店主の虚偽報告を批判した上で、次のように述べています。
「しかしながら、新聞販売店が虚偽報告をする背景には、ひたすら増紙を求め、減紙を極端に嫌う一審被告の方針があり、それは一審被告の体質にさえなっているといっても過言ではない程である。」
ここでも貴社の部数至上主義を上段にかかげた体質が厳しく批判されております。
なお、福岡高裁判決は、貴社に対して真村氏へ慰謝料200万円を支払うように命じています。この200万円という額が慰謝料としていかに破格の高額であるかは、貴社の顧問弁護士にご確認ください。裁判所が高額な慰謝料支払いを命じた背景には、貴社の「押し紙」政策など、優越的地位の濫用によって真村店主が多大な損害を受けたことを裁判所が認めた事情があることは論を待ちません。
◇「一般の読者の普通の注意と読み方」が基準
ちなみに「押し紙」の定義について、参考までに補足しておきます。一般の人々は「押し紙」、あるいは「積み紙」という業界用語の背景にある特殊なビジネスモデルのからくりを知るよしもありません。従って彼らは、販売店の残紙を広義に「押し紙」と呼んでいます。新聞以外の商取引では、売り手が販売予定のない商品を購入する状況はおおよそ想像できず、商品が店舗に多量に余っていれば、それはすなわち「押し売り」の結果と判断するのが自然だからです。それが社会通念です。
貴殿は抗議書の中で、「本件記述は全く事実に反する誤った内容であり、読売新聞の名誉を著しく毀損しています」と述べておられますが、「ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである(31年7月20日、最高裁第二小法廷判決)となっており、一般の読者が「押し紙」という言葉が狭義に定義する意味を理由に、名誉毀損を主張するのはまったく的外れです。
たしかに「押し紙」というその字面、その語感から「押し売り」を連想する人は多いですが、一般の人々が問題にしているのは、販売店で過剰になっている新聞の存在そのものです。従って販売店主に批判の矛先が向けられることもあります。
「押し紙」とは、社会通念上では、漠然と残紙全般を意味しており、業界の特殊用語としての狭義の「押し紙」とは若干区別しなければなりません。
たとえ残紙が狭義の「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、広告主を欺いている事実に変わりはありません。
貴社の販売店、たとえばYC久留米文化センター前やYC大牟田中央、それにYC大牟田明治に約40%から約50%の残紙があった事実は、裁判のプロセス中でも明らかになっております。確かにこれらの残紙は狭義の「押し紙」とは認定されていませんが、少なくとも残紙であることは事実であり、広告主に対する貴社の責任は免れません。
第2次真村裁判について、わたしは本件記事の中ではまったく言及しておりません。それにもかかわらず貴殿の抗議書には、第2次真村裁判に関する記述があります。しかし、2つの裁判を繋ぐうえで不可欠な論理的な整合性が完全に欠落しております。
◇第2次真村裁判
それを踏まえたうえで、ここでは真村氏の名誉のために、次の点にだけ言及しておきます。第2次真村裁判は、真村氏が起こした裁判であることは事実ですが、その原因はすべて貴社にありました。貴殿は、このあたりの事情を正確に取材されたでしょうか。あまりにも事実認識が誤っています。
2007年12月に第1次真村裁判の判決が最高裁で確定した半年後、貴社は真村氏が「黒薮」に読売の販売政策に関する情報を提供したなどと言いがかりをつけて、YC広川を強制改廃しました。これに対して真村氏は再び貴社に対して地位保全裁判を提訴せざるを得ませんでした。そして裁判は、つい先日まで続いたのです。
何の権力も持たない無辜の一個人を法廷に15年近く法廷に縛り付け、人生を台無しにした貴殿たちの行為は、司法制度を濫用した著しい人権侵害です。それを言論機関が断行したことは、日本の新聞史の大きな汚点として記録されています。
貴殿も周知のように、第2次真村裁判は、仮処分申立てと本訴が同時進行しました。仮処分は1審から4審まで真村氏の勝訴でした。裁判所は貴社に対して、YC広川の営業を再開するように命じました。ところが貴社は、この司法命令に従わず、1日に3万円の間接強制金を徴収される事態となりました。資金力で司法命令を踏み倒したのです。
一方、本訴は地裁から最高裁まで貴社の勝訴でした。しかし、仮処分裁判の判決内容と本訴の判決内容が、正面から対立する不可解な現象が裁判記録として書面で残っております。たとえば仮処分裁判の第2審と本訴高裁判決のケースはその典型といえるでしょう。仮処分裁判の第2審で木村元昭裁判長は、真村氏を全面勝訴させました。
その直後、木村判事は、なぜか沖縄県の那覇地裁に転勤になりました。そして再び福岡市へ戻ってくると、今度は福岡高裁へ異動となり、なぜか真村裁判の本訴第2審の裁判長に、裁判長交代のかたちで就任しました。そして今度は、真村氏の主張を情け容赦なく切り捨てたのです。
当然、木村判事が仮処分裁判で書いた判決と本訴で書いた判決を対比し、検討してみると、同じ人物が書いたものとはとても思えないまったく正反対の記述内容となっております。矛盾だらけで支離滅裂の論理性、仮処分判決と本裁判決との整合性などどこにも確認することができません。それが記録として、福岡地裁に永久保存されております。
しかし、この点に関しては、貴殿が抗議書で指摘され、名誉毀損を主張されている本件記事の記述とはまったく関係がないことなので、ここでは言及を避けます。同様に、第1次真村裁判の福岡高裁判決で西裁判長が貴社の「押し紙」を認定した事実と、第2次真村裁判で木村裁判長が、「押し紙」に対する自分の見解を示したことを、貴殿が抗議書の中で無理やりに関連付けられたことも、整合した論理の欠落と言わなければなりません。
本件記事でも書いたように、2007年に福岡高裁が初めて「押し紙」が認定された事実を削除することは出来ません。
つまり第1次真村裁判で初めて狭義の「押し紙」政策が認定されたのは、客観的な事実であり、この事実は、第2次真村裁判で木村裁判官が認定した「押し紙」に関する見解により、変化する性質のものではありません。
貴殿の事実認識の方法が極めて主観的で、事実認識の方法が誤っているというのが、わたしの見解です。
以上が抗議書に対するわたしの回答です。繰り返しになりますが、不明な点などありましたら、真村裁判の裁判資料をもとに、分かりやすく説明しますのでご連絡ください。
読売のポダムと朝日のポカポン 新聞人を世論誘導に悪用したCIAの大罪

坂道を転げ落ちるようにABC部数を減らしている読売新聞に対して、最近、「あれは本当にジャーナリズム企業なのか」という声があがっている。原発推進を煽ったり、異常なまでに新聞拡販に熱をあげたり、新聞社でありながらプロ野球球団を経営したり、首相と会食を繰り返したり、さらには次々と裁判を起こしたりと、歴史的に見ても同時代的に見ても好奇心を刺激する集団だ。
もちろん新聞の発行部数も尋常ではない。ギネスに登録されている。読売とは何か?
次に紹介するバックナンバーは、2013年1月23日付けのものである。
//////////////////////////
23日付け東京新聞が「シリーズ日米同盟と原発」で、原発を導入した読売新聞の正力松太郎を取り上げている。「新聞王 原発の父に 豪腕で初の建設へ」と題するルポである。
ルポの中身は、米国が正力松太郎を利用して、原子力の「平和利用」を日本に持ち込もうとしたというものである。
名誉欲か、それとも政治的野心か、今となってはほとんど知るすべはない。が、マスコミ界から政界入りし、原子力の平和利用で旗振り役を務める正力は、米国にとって頼もしい存在だった。日本の反核世論封じ込めを狙う米国の対日戦略に沿うものだったからだ。
米国公文書館に保管されている文書によると、CIAは読売の正力を「ポダム」と呼び、朝日の緒方(竹虎)を「ポカポン」と呼んでいたという。米国がメディア戦略として新聞を利用していたことを示唆する事実である。
CIAの文書は、読売のポダムを高く評価している。
ポダムは協力的だ。親密になることで、彼が持つ新聞やテレビを利用できる。ポダムとの関係ができてきたので、メディアを使った反共工作を提案できる。
読売新聞や日本テレビを利用した反共宣伝の戦略が、CIAから提案された背景には、国際社会の中でソ連が影響力を強めていた事情もある。その結果、日本では、メディアを世論誘導に利用する戦略が、国民が知らないところで進行していたのである。その先兵となったのが、読売の正力である。
このような事実について、読売は反省しているのだろうか。
最近、読売の主筆兼会長で新聞文化受賞者の渡邉恒雄氏が『反ポピュリズム論』(新潮新書)を出版した。著書の内容については、改めて言及する機会があるかも知れないが、わたしの関心をひいたのは反ポピュリズム論よりも、むしろ渡邉氏がみずから政界を動かしているエピソードを独白している点である。
たとえば「自自連立で小沢・野中の橋渡し」を行ったことを告白している。有権者から選挙で選ばれていない者が、日本の政治を動かしているのである。 新聞人が政界工作の役割を演じる是非は別として、新聞人としての誇りなど捨ててしまったのかという思いにかられる。
ちなみに渡邉氏が率いる読売グループは、最近、読売の方針にそぐわない者に対して次々と裁判を起している
このような人物が新聞業界に君臨していることに対して、強い批判の声が上がらないのも不思議だ。戦いを回避する傾向すらある。それどころか出版業界全体が再販問題や消費税問題で渡邉氏の政治力に期待しているとの説もある。
正力・渡邉といったタイプの人物が日本のメディア界に君臨してきた事実は重大だ。
【写真】正力松太郎
6月度の新聞のABC部数、読売は年間約36万部の減、朝日は約31万部の減、新聞産業の衰退に歯止めかからず

2018年6月度の新聞のABC部数が明らかになった。ABC部数の激減傾向にまったく歯止めがかかっていないことが分かった。年間で朝日は約31万部を、読売は約36万部を失った。もともとABC部数が少ない毎日も、年間で約20万部を減らしている。
中央紙のABC部数の詳細は次の通りである。
朝日:5,884,764(-314,046)
毎日:2,769,159(-202,353)
読売:8,419,052(-359,829)
日経:2,421,882(-296,674)
産経:1,464,355(-55,177)
ちなみにABC部数は、新聞の印刷部数であって、必ずしも実配部数と一致しているわけではない。ABC部数には、「押し紙」(新聞社がノルマとして、販売店に買い取らせた部数)が大量に含まれているというのが、常識的な見方である。
従ってABC部数の減部数そのものを根拠に、新聞離れ現象を説明するのは正確ではない。それよりも「押し紙」の負担に販売店が耐えられなくなり、新聞社が自主的に「押し紙」を減らさざるを得ない状況に追い込まれている実態が新聞産業の衰退を示していると考える方がより実情に即している。
新聞購読者は、確かに減り続けているが、新聞を読まない層は、すでに何年も前に購読を中止していると考えうる。
◇日経電子版は好調
今後、新聞社は、「紙」から「電子」への切り換えを進め、しかも、購読料を徴収するビジネスモデルを構築しなければならない。
業界紙の報道によると、日経新聞の電子版単体の会員数は、7月の時点で384,015人。これは前年比で+56,458人である。日経の場合、企業情報に特化しているので、有料にしても需要があると考えうる。
2018年07月02日 (月曜日)
東京オリンピックのスポンサー・リストに朝日、読売、毎日、日経の社名、選手村用地の「1200億円値引き事件」を報じない理由

メディア黒書でたびたび取りあげてきた東京オリンピック・パラリンピックの選手村建設予定地(中央区晴海5丁目)が、地価の約10分の1、約1200億円の値引きで大手ディベロッパーに廉売された事件を、大手新聞がほとんど報じない決定的な理由が明らかになった。
【参考記事】東京都内にこんなに安い土地はない、東京オリ・パラの選手村建設用地、元東京都職員が三井や住友へ続々と天下り
報じない理由は、オリンピックの歓迎ムードに水を差したくないといった心理から来る自粛の問題ではない。もっと決定的な理由がある。
それは、新聞社が自らオリンピックのスポンサーになっているからである。スポンサー企業のリストを調べたところ、朝日、読売、毎日、日経の4社が、「東京2020オリンピックオフィシャルパートナー」になっていることが判明した。
これではオリンピックに関連した問題を取りあげることはほぼ不可能だ。ジャーナリズム企業がオリンピックのスポンサーになるという常識では考えられないことが、現実に起こっているのである。日本の新聞人は、ここまで堕ちたのである。
ちなみに東京都から土地を地価の10分の1で譲り受けたデベロッパーの関連会社の名前もスポンサーのリストにある。次に示すのがスポンサー一覧である。
◇民間へ丸投げの商業オリンピック
オリンピックは、ロサンゼルス大会から、民間主導の商業オリンピックになった。そのためにスポンサーを募る。スポンサーになると、オリンピック関連のロゴやエンブレムを使用する権利を得る。スポンサーになっていない企業が、勝手にオリンピックに便乗した宣伝活動をすることは禁止されている。
スポンサーの種類は、契約金などの金額の違いにより、次の4段階がある。
①ワールドワイドオリンピックパートナー
②東京2020オリンピックゴールドパートナー
③東京2020オリンピックオフィシャルパートナー
④東京2020オリンピックオフィシャルサポーター
①の場合、年間契約額は25~30億円。国際規模で宣伝活動を展開することが出来る。ちなみに25~30億円という額は、大企業にとってはほとんど負担にならない。たとえば、トヨタ自動車の年間の広告宣伝費は4487億円(2016年4月~2017年3月)だから、全体の0.5%にも満たない。
「投資」が少ない割には、大きな宣伝効果が期待できるのだ。
②③④は、年間契約額は安くなるが、活動範囲も国内に限定されるなど、権利行使の範囲も限定される。
元読売弁護団のメンバーが九州各地を転々、「押し紙」裁判で同業他社を支援、「押し紙」隠しのノウハウを伝授か?、業界ぐるみの「押し紙」隠蔽が明らかに
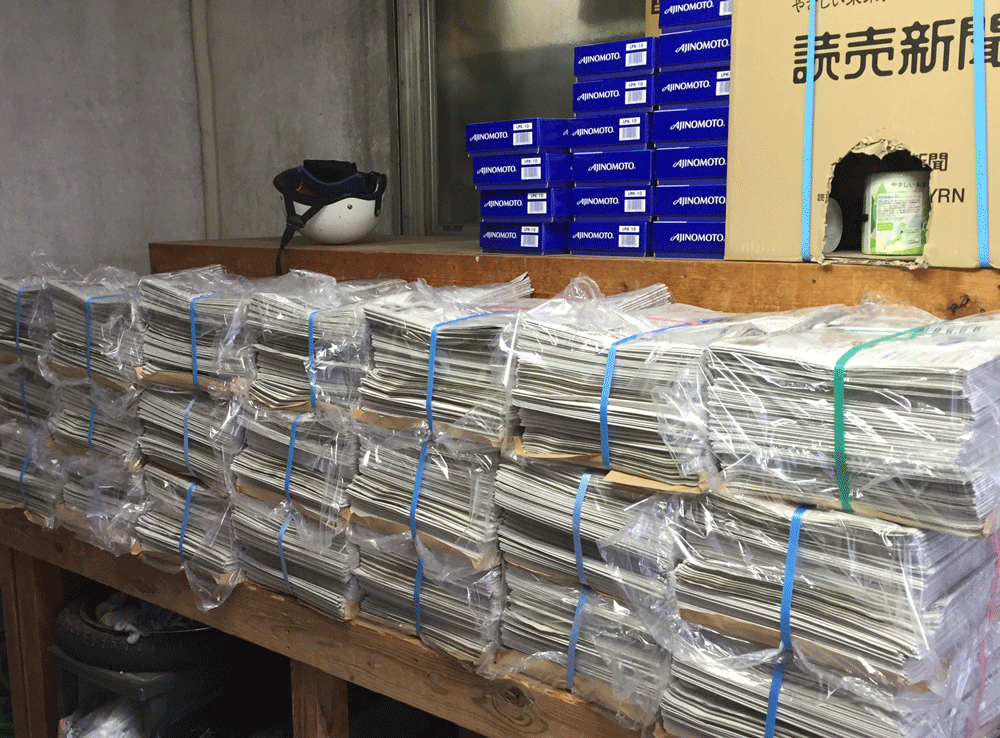
読売弁護団(西部本社)のメンバーの一部が、「押し紙」裁判を起こされた同業他社を支援するために、九州各地の裁判所を転々としてきたことが分かった。「押し紙」隠しのノウハウを新聞業界ぐるみで共有している実態が明らかになった。
九州各地を転々としてきたのは福岡国際法律事務所の近藤真弁護士ら3名である。近藤弁護士らは、2008年ごろに喜田村洋一・自由人権協会代表理事らと共に読売弁護団を結成して読売の主張を代弁してきた。「押し紙」は1部も存在しないと主張してきたのである。
筆者が2008年に読売に対して起こしたスラップ認定裁判でも読売の代理人として登場した。この裁判は、読売が筆者に対し短期間に次々と起こした3件の裁判(約8000万円を請求)が、「一連一体の言論弾圧」にあたるとして、5500万円の損害賠償を求めたものである。
同じ時期、近藤弁護士らは、宮崎市の朝日新聞販売店が起こした「押し紙」裁判でも、朝日新聞社の代理人に就任した。この裁判では、「押し紙」を「予備紙」と強弁し、裁判所もこの主張を認めた。以後、「押し紙」の中味は「予備紙」だという詭弁が広がったのである。
◇西日本新聞と佐賀新聞でも
その後、福岡地裁で西日本新聞社の店主が「押し紙」裁判を起こすと、西日本新聞社の弁護団に加わった。さらに今月になって、やはり「押し紙」裁判に巻き込まれている佐賀新聞社の弁護団に加わっていたことが分かった。
なぜ、こんな現象が起きているのだろうか?以下、筆者の推測になる。
「押し紙」政策は、社会通念からすれば、誰が見ても異常だ。その異常な実態を正当化することは、普通の正義感がある弁護士であればできない。それを無理やりに正当化するための理論を組み立てるためには、独特の詭弁術が必要になる。そこで読売裁判の経験がある近藤弁護士ら3人が適任との評判が広がり、九州各地を転々とすることになった可能性が高い。
「押し紙」は存在しないという主張が真実だったのか、それとも嘘だったのか、これから明らかになることは間違いない。それによって裁判官や弁護士の評価も決まるのではないだろうか。
※なお、第1次真村裁判から第2次真村裁判へ至る過程、筆者が読売裁判に巻き込まれた過程などは、拙著『新聞の危機と偽装部数』(花伝社)に詳しく記録している。
読売新聞の元販売店主がメディア黒書に内部告発、「使途不明金を弁済させられた」

読売新聞の元店主からメディア黒書に内部告発があった。内容は、会計に関する不当な処理を強要されたというものである。現時点では、「告発された側」の言い分を聴取するに至っていないので、ここでは告発者側の主張だけを紹介しておこう。その上で「告発された側」の言い分を取材することにする。
この事件の背景を説明しておこう。読売に限らず、新聞販売店は地域ごとに「会」を組織している。たとえば、神奈川連合読売会。その下に地域ごとの会がある。さらにその下に支部がある。つまりピラミット状の組織になっているのだ。
この事件は、神奈川県内のあるYCの支部(8店で構成)で起きた。
今年2月にYCを廃業したKさんは、それまで支部会の会計を担当していた。ところが「平成21年4月から平成29年3月」(始末書)の会計で、不正経理が発覚した。その額は、推定で「3,690,000円」。(始末書)その責任をKさんが取ることになり、会計処理に誤りがあったことを認め、謝意を表す始末書を書かされた上で、使途不明金をポケットマネーから弁済させられたというものである。
Kさんは、始末書に捺印したが納得しておらず内部告発に踏み切ったのである。
「自分が使い込んだわけではありません。古い領収書がなかったので、どうすることも出来ませんでした」
・・・・会費はおもに何に使っていましたが?
「飲食費が多かったです」
・・・・2月に自主廃業されましたが、この事件と何か関係ありますか?
「それはまったく別問題です。経営が悪化したことが原因です」
内部告発された支部側の言い分については、取材後に紹介したい。
2018年05月03日 (木曜日)
毎日新聞、読売新聞、新潟日報が森裕子議員に対する3度目の刑事告発受理を報道

4月20日付けで新潟地検が受理した森裕子議員に対する刑事告発を、毎日新聞、読売新聞、新潟日報の3紙が報じた。新潟知事選を前に、どのような影響が生じるのか注目される。この事件の背景には、政治資金の還付金制度がある。
分かりにくい記事なので、以下、解説しておこう。
【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。この条項を無視して、議員が自らの政党支部に寄付すれば、マネーロンダリングになってしまう。1000万円を寄付すれば、資金が1300万円にふくれあがることになる。
引用文にも明記されているように、「還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。森氏のケースがこれに該当するという判断で、志岐武彦氏と筆者が、過去2度にわたって刑事告発した。そして2度とも受理された。
しかし、ある事情で不起訴になった。以下、推測になるが、事情を説明しておこう。筆者らは、高市早苗議員に対しても同じ容疑で奈良地検に刑事告発した。奈良地検もこれを受理した。
筆者らは当然、高市・森の両氏は、起訴されるものと考えていた。ところが急激に検察をはじめ国家公務員の腐敗が進むなかで、安倍内閣の総務大臣だった高市氏は、不起訴になるのではないかという懸念が生じてきた。
検察が高市氏を不起訴にするためには、森議員も不起訴にしなければ整合性が取れない。そこでまず森氏を不起訴にし、続いて高市氏も不起訴としたのである。志岐氏が管理している新潟地検との会話記録によると、同地検は起訴の方向だったようだ。それを前提に上級機関の承諾を得る手続を進めていたのである。
◇不起訴に対する対抗策
不起訴の決定に対して筆者らは対抗策を講じた。高市氏に対する容疑を「詐欺」から、「所得税法違反」に切り替えて、再び刑事告発した。詳細は次の通り。
■検察審査会へ申し立て、新たに刑事告発、高市早苗議員によるマネーロンダリング疑惑
一方、森氏に対しては、志岐氏が単独で、別の罪名で刑事告発を行った。そして、4月20付けで、受理されたのである。この内容については、次の記事に詳しい。ただし、書類を提出した後、告発内容の一部を変更したので、リンクを張った告発状は、修正前のものと、修正後のものと2種類ある。読者には後者の方を参考にしてほしい。
■志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで
◇菊田真紀子衆議院も675万円の還付金
なお、メディア黒書で既報したように、森氏と高市氏が手を染めたマネーロンダリングの手口は、政治家の間で広まっており、来る新潟知事選で野党共闘の候補者として名があがっている菊田真紀子衆議院も、2016年度までに675万円の還付金を受けている。
■新潟知事選の候補・菊田真紀子衆院議員がマネーロンダリングの手口で675万円の還付金を受け取っていた、同じ新潟の森裕子議員と共通の手口
◇森氏によるマネーロンダリング一覧
参考までに森議員のマネーロンダリングの詳細を表にしたものを紹介しておこう。作成は、『財界にいがた』と志岐氏である。
2018年2月度の新聞のABC部数、朝日は年間で31万部減、読売は29万部減、朝日が高いジャーナリズム性を発揮できる背景に「押し紙」政策の廃止

2018年2月度の新聞のABC部数が明らかになった。ABC部数の低落傾向にはまったく歯止めがかかっていない。この1年間で、朝日新聞は約31万部減、毎日新聞は約17万部減、読売新聞は約29万部減である。さらに日経も、約28万部を減らしている。
詳細は次の通りである。()内は、前年同月比である。
朝日:5,989,345(-308,108)
毎日:2,840,338(-173,444)
読売:8,560,861(-285,287)
日経:2,445,373(-275,347)
産経:1,516,574(-46,299)
◇読者の減というよりも、「押し紙」の減
メディア黒書で新聞のABC部数を紹介するたびに、繰り返し説明していることであるが、ABC部数の減少が必ずしも読者数の減少を意味するものではない。と、いうのもABC部数には、大量の「押し紙」が含まれており、新聞社が自主的に「押し紙」を減らした結果、ABC部数が減少した可能性もあるからだ。
むしろABC部数の減部数は、「押し紙」を減らした結果であると解釈するほうが正しい。新聞社が「押し紙」を減らす理由は、販売店の経営が悪化して、「押し紙」の負担に耐えきれなくなっているからだ。販売網が崩壊すれば、肝心の新聞を宅配できなくなるからだ。
筆者が販売店を取材した限りでは、朝日新聞の販売店では、大幅に「押し紙」が減っている。全店を調査したわけではないが、筆者と接触を持っている店は、全店で「押し紙」がゼロになった。それがABC部数の激減を招いているのだ。
◇朝日が高いジャーナリズム性を発揮している理由
このところ朝日新聞は安倍内閣批判で高いジャーナリズム性を発揮している。その背景には、「押し紙」の排除があると筆者は考えている。「押し紙」は独禁法違反であるから、「押し紙」があれば、公権力はそれを口実に報道内容に暗黙の圧力をかけてくる。それゆえに「押し紙」を排除すれば、ほぼ経営上の大きな汚点はなくなり、正面から政府に対峙する条件が生まれるのだ
逆説的に言えば、政府は「押し紙」を放置することで、メディアコントロールを続けてきたといえる。朝日は、「押し紙」を廃止したことで、ジャーナリズム企業としての条件を整えたのである。