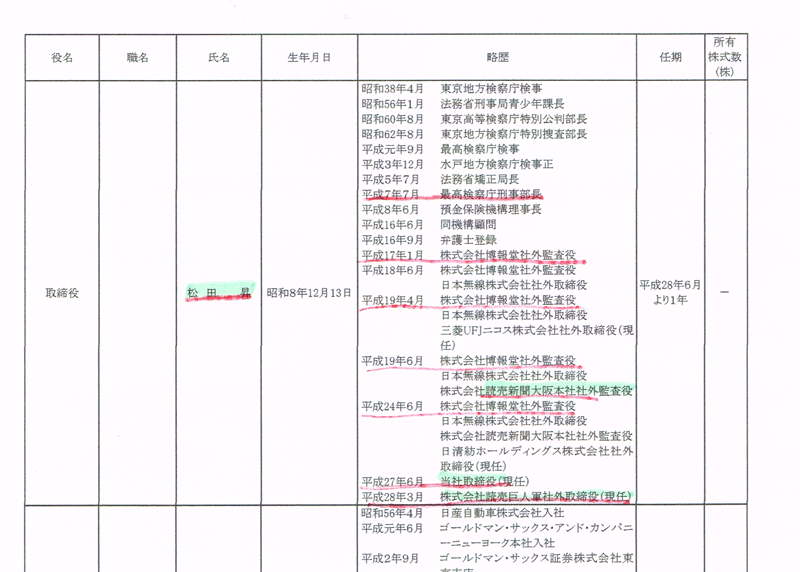読売新聞が1年で36万部減、朝日は27万部減、新聞の凋落に歯止めはかからず

2016年11月の新聞のABC部数が明らかになった。朝日新聞は約636万部で、前年同月比で約-27万部である。読売新聞は約900万部で、前年同月比で、-36万部だった。中央紙全体では、約82万部が減った。
新聞の凋落に歯止めがかかっていないことが明らかになった。
ABC部数の詳細は次の通りである。
朝日新聞 6,360,646(-273,799)
読売新聞 9,004,769(-363,735)
毎日新聞 3,027,684 (-176,882)
日経新聞 2,724,779(-4,241)
産経新聞 1,566,580(-1,836)
なお、ABC部数には、「押し紙」(正常な新聞販売店経営に不要な部数)が含まれており、ABC部数の減少がかならずしも、新聞の購読者が減ったことを意味しない。
ABC部数の減少を解析する場合、購読者の減少と「押し紙」の減少の両面を考慮しなければならない。
読売・喜田村洋一・自由人権協会代表理事らによる口封じ裁判から9年目に、今後も検証は続く

12月21日は、読売新聞社(西部本社)の江崎徹志法務局長がメディア黒書(旧新聞販売黒書)に対して、ある文書の削除を求める仮処分を申し立てた日である。代理人弁護士は、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。2016年の12月21日は対読売裁判が始まって9年目にあたる。
江崎氏の申し立ては、わたしがメディア黒書に掲載した江崎名義の1通の催告書の削除を求めるものだった。しかし、江崎氏は法務室長という立場にあり、実質的には、江崎氏個人ではなく、読売新聞社との係争の始まりである。
事実、その後、読売から3件の裁判、わたしから1件の裁判と弁護士懲戒請求を申し立てる事態となった。
◇真村事件から黒薮裁判へ
この裁判の発端は、福岡県広川町にあるYC広川(読売新聞販売店)と読売の間で起こった改廃(強制廃業)をめぐる事件だった。当時、わたしは真村事件と呼ばれるこの裁判を熱心に取材していた。
係争の経緯については、長くなるので省略するが、2007年の12月に真村氏の勝訴が最高裁で決定した。日本の裁判では、地裁と高裁で連勝すれば、最高裁で判決が覆ることはめったにない。そのために最高裁の判断を待つまでもなく、高裁判決が出た6月ごろから真村氏の勝訴確定は予想されていた。
そのためなのか、読売も真村氏に歩み寄りの姿勢を見せていた。係争になった後、中止していた担当員によるYC広川の訪店を再開する動きがあった。そして江碕氏は、その旨を真村氏に連絡したのである。
しかし、読売に対して不信感を募らせていた真村氏は即答を控え、念のために代理人の江上武幸弁護士に相談した。訪店再開が何を意味するのか確認したかったのだ。江上弁護士は、読売の真意を確かめるために内容証明郵便を送付した。これに対して、読売の江崎法務室長は、次の書面を返信した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、メディア黒書で係争の新展開を報じ、その裏付けとしてこの回答書を掲載した。何の悪意もなかった。むしろ和解に向けた動きを歓迎していた。
しかし、江崎氏(当時は面識がなかった)はわたしにメールで次の催告書(PDF)を送付してきたのである。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
わたしは削除を断った。先に引用した、
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
と、いう回答書は著作物ではないからだ。催告書の形式はともかく、書かれた内容自体はまったくのデタラメだった。著作権法によると、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」。上記の回答書は、著作物ではない。催告書の内容そのものが間違っている。
そこで、今度はこの催告書をメディアで公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権に基づいて、削除するように求めてきたのである。
そして喜田村弁護士を立てて、催告書の削除を求め、仮処分を申し立てたのである。(回答書の削除は求めてこなかった。)
こうして江崎氏名義の催告書が、著作物かどうかが争点となる係争が始まったのだ。書かれた内容の評価とは別に、催告書が著作物かどうかという点に関しては、一応は議論の余地があった。書かれている内容そのものがデタラメであっても、それに著作物性があるかどうかは、別問題である。
結論を先に言えば、仮処分申立は、江崎氏の勝訴だった。催告書が著作物と認めれらたのだ。
判決に不服だったわたしは、本訴に踏み切った。代理人は江上弁護士ら、真村裁判の弁護団が無償で引き受けてくれた。わたしは東京・福岡間の交通費もふくめて、1円の請求も受けなかった。
◇重大な疑惑の浮上
本訴の中で重大な疑惑が浮上した。
既に述べたように、この裁判は、江崎氏が書いたとされる奇妙な内容(例の回答書が著作物であるという内容)の催告書が争点だった。内容が奇妙でも催告書が江崎氏の著作物であると認定されれば、わたしは削除に応じなければならない。
仮処分では負けたわたしだが、裁判の途中から様相が変わってきた。特に江崎本人尋問を機に流れが変わった。
確かに催告書の名義は江崎氏になっているが、催告書は喜田村弁護士が作成したものではないかという疑惑が浮上してきたのだ。
著作者の権利は、著作権法では、「著作者人格権(公表権などが含まれる)」と「著作者財産権」に別れるのだが、前者は他人に譲渡することができない。一身専属権である。
江崎氏は、著作者人格権を根拠に、わたしを提訴したのである。と、なれば江碕氏が催告書の作者であることが、提訴権を行使できる大前提になる。仮に他人が書いたものなら、それはたとえば、わたしが村上春樹氏の作品を自分のものだと偽って、著作者人格権による権利を求める裁判を起こすのと同じ原理である。
催告書の本当の作成者が喜田村弁護士だとすれば、喜田村氏らは催告書の名義を「江碕」偽り、それを前提にして、著作者人格権を主張する裁判を起こしたことになる。
◇東京地裁・知財高裁の判決
東京地裁は、わたしの弁護団の主張を全面的に認めて、江崎氏の訴えを退けた。喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフが催告書の本当の作者である可能性が極めて強いと認定したのである。
このあたりの事情については、地裁判決直後の弁護団声明を参考にしてほしい。弁護団は、この事件を「司法制度を利用した言論弾圧」と位置づけている。
次の引用するのは、知財高裁判決の重要部分である。催告書の名義人偽り疑惑について、次のように言及している。
上記の事実認定によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は、原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)である可能性が極めて強い。
繰り返しになるが、江崎氏は、元々、著作者人格権を主張する権利がないのに、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴し、それを主張したのである。
喜田村弁護士は、自分の行為が弁護士としてあるまじき行為であることを自覚していたはずだ。弁護士職務基本規定の第75条は、次のようにこのような行為を禁止している。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
ところが名義を偽った催告書を前提にして、裁判所へ資料を提出し、自己主張を展開したのだ。
裁判が終わった後、今度はわたしの方が攻勢に転じた。喜田村弁護士が所属する第2東京弁護士会に対して、喜田村弁護士の懲戒請求を申し立てた。2年後に、申し立ては却下されたが、多くの法律家が前代未聞のケースだとの感想を寄せた。弁護士会の判断は誤りだと話している。現在、再審を検討している。
曖昧な決着はしないのが、わたしの方針だ。
参考までに、懲戒請求の中身を次の書面で紹介しておこう。
今後も検証は続く。
1年間の減部数、朝日は35万部、読売は16万部、毎日は19万部、ネットメディアとの世代交代が顕著に

2016年度9月度のABC部数が明らかになった。朝日新聞は前年同月比で約35万部減、読売新聞は約16万部減、さらに毎日新聞は約19万部減である。3社あわせて70万部の減部数である。
これは中堅規模の地方紙2社分の部数に該当する。新聞の没落に歯止めがかかっていない実態を示している。
朝日新聞 6,433,159(-348,120)
毎日新聞 3,049,397(-188,808)
読売新聞 8,942,131(-160,267)
日経新聞 2,725,261(-6,284)
産経新聞 1,568,848(-31,339)
しかし、ABC部数には、「押し紙」(広義の残紙)が含まれているので、ABC部数が実際に配達されている新聞部数を示しているわけではない。わたしが新聞販売店を取材した限りでは、これだけ大きな規模で部数が激減していながら、なお、「押し紙」が搬入部数の2割も3割もある販売店が複数存在する。
これらの「押し紙」を排除すれば、新聞社の販売収入はさらに減る。それにともない紙面広告の媒体価値も低下していく。販売収入と広告収入という新聞社経営の2本柱があやうくなってきたのである。
ネットメディアとの世代交代が顕著になってきたといえよう。
風化せぬ読売・真村事件、ひとりの販売店主を14年間も法廷に立たせた事実をどう評価するのか
読売新聞の販売政策が争点となった真村裁判が始まったのが、2002年だから、今年で14年になる。裁判は先日、ようやく終わった。この事件には、読売から3件の裁判を起こされたわたしを含めて、さまざまな人々が登場する。
読売側の弁護団も、初期とは完全に入れ替わった。途中からは、喜田村洋一自由人権協会・代表理事も東京から福岡へかけつけ、読売のために働くようになった。
読売は、弱小のYC広川を経営する真村氏を相手に必死の戦いを繰り広げたのである。
10月2日、「新聞の偽装部数『押し紙』を考える」と題する集いが、東京板橋区の板橋文化開会で開かれ、真村弁護士団の江上武幸弁護士が真村事件について講演した。
◇真村事件とは
事件の発端は、読売が真村氏にYC広川の営業区域の一部を返上するように求めたことである。その背景に筑後地区の“大物店主”S氏の存在があった。S氏の弟がYC広川の隣接区にあるYCを経営しており、YC広川の営業地区を縮小する一方で、それを隣接店に組み込むというのが読売の方針だった。
久留米市など筑後地区にある他のYCでも、S氏がかかわった類似事件が続いて発生し、真村氏ら3人の販売店主が、地位保全の裁判を起こした。これが俗にいう真村裁判である。3人の原告のうちひとりは、既にYCの経営権を剥奪されていたので、和解解決した。他のひとりのケースは、あまり争点にはならなかった。中心的な争点になったのは、真村氏の事件だった。
結果は地裁から最高裁まで真村氏の勝訴だった。2007年12月に真村氏の販売店主としての地位は保全されたのだ。真村氏の勝訴に刺激されて、新たに3人のYC経営者が、江上弁護士に「押し紙」(広義の残紙)問題を相談した。2007年の秋のことだった。これら3店主が経営するYCには、約40%から50%の「押し紙」(残紙)があった。
◇喜田村弁護士に対する弁護士懲戒請求
こうした状況の下、真村事件を取材していたわたしに対する裁判攻勢が始まった。喜田村洋一自由人権協会・代表理事を代理人として、2008年2月から2009年7月までの約1年半の間に3件の裁判を起こしたのである。請求額は、約8000万円。
このうち最初の著作権裁判では、読売側が、虚偽の事実(催告書の名義人の偽り)をでっちあげ、それを根拠に提訴に及んだ強い可能性が司法認定され敗訴した。もともと提訴する権利がなかったのだ。前代未聞のケースだ。
そこで喜田村弁護士に対して、弁護士懲戒請求を行ったが、2年にわたる審理の末、日弁連は、喜田村弁護士に対する処分を行わない決定を下した。つまりでっち上げ裁判が許されるということになる。この事件と日弁連の判断が再検証を要することは言うまでもない。
2件目の裁判は、地裁、高裁はわたしの勝訴。最高裁が口頭弁論を開いて、判決を高裁に差し戻し、わたしの敗訴となった。わたしに110万円の支払いを命じた判決を下した加藤新太朗裁判官は、退官後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に再就職(広義の天下り)している。
3件目はわたしの完全敗訴だった。この裁判で喜田村弁護士らは、自社(読売)に「押し紙」は1部も存在しないと主張し、裁判所もそれを認めた。
◇第2次真村裁判
一方、真村氏は最高裁で判決が確定した7ヶ月後に、YC広川を改廃された。
そこで再び地位保全の裁判を起こさざるを得なくなった。
第2次裁判の結果は次の通りである。舞台は福岡地裁である。
1、仮処分 真村勝訴
2、仮処分(異議審) 真村勝訴
3、仮処分(抗告?高裁) 真村勝訴
4、仮処分(特別抗告) 真村勝訴
1、地裁本訴 読売勝訴
2、高裁本訴 読売勝訴
3、最高裁 読売勝訴
このうち仮処分の異議審で真村さんを勝訴させたのは、木村元昭裁判官だった。仮処分としては、異例の25ページにも及ぶ判決文で、読売の主張を退けたのである。
さらに真村氏の後任者としてすでに販売店経営に着手している店主とも話し合って、真村氏に営業権を移譲するように命じている。
木村裁判官は、この判決を下した2週間後の2月1日に那覇地裁へ所長として赴任した。
その後、真村さんは仮処分裁判を勝ち進む。ところが抗告(高裁)で勝訴した数日後に本訴(地裁)判決があり、意外にも敗訴した。
そこで真村さんは高裁へ控訴した。控訴審が始まって間もなくすると、裁判官の交代があった。1年半前に仮処分裁判(異議審)で、真村氏を勝訴させた木村元昭裁判官が、那覇から福岡へ戻り、真村裁判を担当することになったのである。
そして真村氏を敗訴させたのだ。仮処分では真村氏を勝訴させ、経営権を取り戻せるように、後任店主との話し合いを勧めていた同じ裁判官が、今度は180度異なった判決を下したのである。
この件は最高裁事務総局による「報告事件」の疑惑があり、今後、情報公開などを通じて、調査する必要がある。
真村氏が敗訴した理由は、さまざまだが、その中のひとつに、わたしに対して真村氏が情報提供を行ったというものがある。メディア企業・読売がこうした主張をしたこと自体が議論の的になる。読売の記者は、この件をどう考えるのだろうか。
◇自宅の仮差し押さえ
第一次、真村裁判の判決が最高裁で確定したころ、「押し紙」について江上弁護士に相談した3人の販売店主のうち、2人は読売側に寝返った。もう1人は、販売店を強制改廃され、地位保全の裁判を起こしたが、地裁、高裁と敗訴。その後、病死された。
真村氏は、第2次真村裁判の仮処分申し立てで、勝訴していたが、読売が新聞の供給を再開しなかったので、1日に3万円の間接強制金(累積で約3600万円)を受けていた。ところが本訴で敗訴したので、読売は真村氏に対して間接強制金の返済を求める裁判を起こした。自宅も仮差し押さえした。
これら一連のプロセスにも、自由人権協会の喜田村洋一代表理事がかかわった。
裁判の開始から終結まで14年。ひとりの販売店店主を14年もの間、法廷に縛りつけたこと自体が、重大な人権問題である。
真村裁判の検証はこれから始まる。真村事件は、記録として歴史の壁に刻まれていく。
2日に「押し紙」を考える全国集会、江上武幸弁護士が読売裁判の14年を語る
 明日(10月2日)に、「押し紙」問題を考える全国集会が開催される。集会では、江上武幸弁護士が読売裁判について講演する。
明日(10月2日)に、「押し紙」問題を考える全国集会が開催される。集会では、江上武幸弁護士が読売裁判について講演する。
読売裁判は2002年に始まり、先日、ようやく終結した。この間、筆者(黒薮)を含む、多数の人々が事件にかかわった。筆者だけに限っても、4件の裁判と、1件の弁護士懲戒請求(対象弁護士は、読売の代理人・喜田村洋一自由人権協会代表理事)を経験している。
また、パネルディスカッションでは、江上弁護士の他、評論家の天木直人氏、行橋市議の小坪慎也氏がメディアについて意見を述べる。
場所:板橋文化会館(大会議室・東京都板橋区)《地図》
日時:10月2日(日) 午後13時開場、13:30開演
入場は無料
詳細は、次のリンク先で。
元最高検察庁刑事部長の松田昇氏の再就職先、博報堂DYホールディングスだけではなく、3月から読売巨人軍にも、官民汚職の温床に
裁判官や検察官などの国家公務員が退官後に民間企業に再就職するケースが後を絶たない。このような行為を広義に「天下り」と呼ぶ。目的は、現役の国家公務員に対して、先輩の影響力を発揮し、自らの再就職先のために便宜を図ることであると言われている。
官民汚職の温床にほかならない。「天下り」は前近代的な悪しき慣行のひとつであると言えよう。
縦の人間関係が支配的な日本では、退職者を部外者として扱う習慣もない。
◇司法改革の障害
博報堂DYホールディングスの有価証券報告書によると、同社には元最高検察庁刑事部長の松田昇氏が再就職している。同報告書によると、同氏の経歴は次の通りである。
興味深いのは、「平成」28年、つまり今年の3月から、野球賭博などの不祥事に揺れている読売巨人軍の外部取締役に就任していることだ。これで野球賭博や覚醒剤の捜査が徹底して行われるのか、注視する必要がある。
過去に松田氏は、読売新聞大阪本社の社外監査役にも就任している。読売が、元最高検察庁・刑事部長を受け入れた背景は不明だが、メディア企業としてのあり方としては尋常ではない。ジャーナリズムの役割は、権力の監視であるからだ。権力と一体化してしまえば、旧ソ連、北朝鮮、それに大本営に依存していたかつての日本の新聞社とかわらない。
ちなみに大手弁護士事務所へは、最高裁判事の「天下り」が目立つが、これについては、別の機会に氏名と所属事務所を公表しよう。彼らは判決に影響を与えかねない存在で、日本の司法の公平性を脅かす存在と言っても過言ではない。司法改革の障害となる。こちらは、全面的に法律で禁止すべきだというのが筆者の考えだ。
6月度のABC部数、「読売1000万部」の時代は過去に、前年同月比で朝日が-26万部、読売が-13万部
2016年6月度の新聞のABC部数が明らかになった。それによると中央紙(朝、読、毎、産、日)はいずれも、前年同月よりも部数を減らしている。
朝日が-26万部、読売が-13万部、毎日が-19万部、産経が-4万部、日経が-1万部となっている。
新聞部数の低落傾向には依然として歯止めがかかっていない。
6月度のABC部数は次の通りである。
朝日:6,505,026(-285,927)
読売:8,982,568(-125,510)
毎日:3,058,129(-191,799)
産経:1,565,858(-38,257)
日経:2,728,912(-10,115)
◇ABC部数は「押し紙」を含む
ちなみに実際に配達されている新聞部数(実配部数)とABC部数との間には乖離がある。ABC部数に「押し紙」が含まれているからだ。
「押し紙」とは、広義には新聞社が新聞販売店に対して供給する過剰な新聞部数を意味する。残紙ともいう。たとえば2000部しか配達していない販売店に対して3000部を搬入すれば、差異の1000部が「押し紙」である。この1000部に対しても、新聞社は卸代金を徴収する。普通の新聞とまったく同じ扱いにしているのだ。
かりにジャーナリストが「押し紙」問題で新聞社を追及しても、新聞社は自分たちは一度も「押し紙」をしたことはないと真面目な顔で反論してくる。
しかし、「押し紙」隠しの実態は、2002年に提起された真村訴訟の中で完全に暴露された。しかも、それが裁判で認定された。
■真村裁判福岡高裁判決の全文
【冒頭の画像】「押し紙」の回収場面。広告のスポンサーに対する背信行為である。
読売の滝鼻広報部長からの抗議文に対する反論、真村訴訟の福岡高裁判決が「押し紙」を認定したと判例解釈した理由

『月刊Hanada』(7月号)に掲載した筆者(黒薮)の記事に対して、読売新聞の滝鼻太郎広報部長が抗議文を送りつけてきた。これに対する筆者の反論を作成した。反論は形式上は滝鼻氏に宛てたものになっているが、読者にも理解できるように構成した。
滝鼻氏の抗議の中身は、究極のところ真村訴訟の福岡高裁判決が読売の「押し紙」を認定したとするわたしの判例解釈は間違っているというものだ。わたしはかねてから、社会の「木鐸」といわれる新聞社がかかわってきた(広義の)「押し紙」問題のように公共性が極めて強い問題は、公の場で論争するのが、係争の理想的な解決方法だと考えている。とりわけ言論人にはそれが求められる。
従って、滝鼻氏にもメディア黒書のサイト上で、あるいは自社・読売新聞の紙上で自分の意見をより詳しく公表してほしい。反論権は完全に保証する。
もちろん滝鼻氏には、近々、公式に「押し紙」問題についての論争を申し入れる。
本来、論争に先立って滝鼻氏の抗議文を公開するのが、相手に対する配慮であるが、実は2008年、読売の法務室長がわたしに送付した催告書をメディア黒書で公開したところ、著作権違反で提訴された経緯があるので、今回は滝鼻氏の承諾を得られれば公開する。ひとには公表を控えたい文書もあるものなのだ。
■参考記事:喜田村洋一弁護士が作成したとされる催告書に見る訴権の濫用、読売・江崎法務室長による著作権裁判8周年①
なお、滝鼻氏が問題としている真村訴訟の判決は、次のリンク先で閲覧できる。読者は、判決の中で読売の「押し紙」、あるいは「押し紙」政策が認定れていないとする滝鼻氏の見解の是非を自身で検証してほしい。
【反論文の全文】
貴殿から送付されました抗議書に対して、記事の執筆者である黒薮から回答させていただきます。まず、貴殿が抗議対象とされている箇所を明確にしておきます。と、言うのも貴殿の抗議書は、故意に問題の焦点を拡大しており、そのために議論が横道へそれ、本質論をはずれて揚げ足取りに陥っているきらいが多分に見うけられるからです。
貴殿が問題とされている箇所は、枝葉末節はあるものの、おおむね『月刊Hanada』 (7月号)に掲載された「公取が初めて注意『押し紙』で朝日も崩壊する」(黒薮執筆)と題する記事の次の引用部分です。この点を確認し、共有する作業から、わたしの反論を記述します。
「裁判の結果は、真村さんの勝訴でした。2007年12月に、最高裁で判決が確定しました。裁判所は「真村さんが虚偽報告をしていたのは批判されるべきだが、その裏には読売の強引な販売政策があった」との見解を示し、真村さんの地位を保全したのです。この裁判で裁判所は、新聞史上初めて、押し紙の存在を認定したのです」
抗議書によると、貴殿は、2007年12月に最高裁で確定した第1次真村裁判の判決(西理裁判長)が貴社による「押し紙」政策を認定しているとするわたしの判例解釈は誤りだという見解に立ち、抗議の書面を送付されたわけです。
さらに貴殿は第2次真村裁判についても抗議書の中で言及されておりますが、これについてはわたしは本件記事の中ではまったく言及しておらず、貴殿の主観によって導かれた議論のすり替えに該当しますので、補足的に後述するにとどめ、まず、第1次真村裁判の判決が、なぜ貴社の「押し紙」政策を認定したと解釈し得るのかを説明させていただきます。
◇真村事件とは
貴殿もご存じのように真村裁判は、貴社がYC広川(福岡県広川町)の営業区域を隣接店へ譲渡する方針を打ち出されたことに端を発する事件です。その隣接店の店主は、暴力事件を起こしたこともあるSという人物の弟でした。Sは〝大物店主〝でした。Sについては、S尋問調書(平成17年○月○日)にも記録されております。この人物の存在なくして、貴社西部本社の新聞販売政策を語ることはできません。
第1次真村裁判は、真村店主が貴社の方針に抗議したのに対抗して、貴社が強制改廃を言い渡し、それを受けて、真村氏がやむなく提訴するに至った経緯があります。
◇「押し紙」と「積み紙」
この裁判の最大の争点となったのは、YC広川にあった「残紙」の性質をどう解釈するのかという点でした。具体的に言えば、「押し紙」と解釈するのが妥当なのか、それとも「積み紙」と解釈するのが妥当なのかという論点です。これについても、貴殿は本件議論の前提事実として認識されているものと思います。
「押し紙」とは、貴殿も抗議文の中で示されているように、「新聞発行業者が、正当かつ合理的理由がないのに、販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給」する結果として発生する「残紙」のことです。端的に言えば、手口の差こそあれ、「押し売り」された新聞のことです。
これに対して「積み紙」とは、販売店の側が、販売(配達)部数を超えた数量の新聞を注文した結果として発生する「残紙」を意味します。販売店が販売予定のない新聞をあえて注文する行為に走る背景には、次のような特殊な事情が存在します。販売店に割り当てられる折込広告の枚数は、新聞の搬入部数に一致させる基本原則がある。当然、残紙に対しても折込広告はセットとして割り当てられる。
このような構図のもとでは、折込広告による収益が、「押し紙」による損害(「押し紙」分の新聞の卸代金)を相殺し、さらに水増し利益を生むことがままある。これこそが販売店が販売予定のない新聞をあえて注文する最大の理由にほかなりません。他にもありますが、本論からはずれるので言及は控えます。
「押し紙」と「積み紙」のバランスを取りながら、時には販売店主との談合により、広告主を欺きつつ、販売店と新聞社の経営安定を図る戦略が、貴殿ら日本の新聞人が構築されたビジネスモデルになっていることは、貴殿も十分に認識されているものと思います。それがいま、大きな世論の批判を受けていることも周知の事実です。それゆえに本件記事は、極めて公益性の高いテーマで貫かれているといえます。
真村裁判で貴社は、YC広川の残紙(約130部)は「積み紙」であり、それが貴社の信用を失墜させる要因なので、同店の懲罰的な改廃には正当な理由があるという趣旨の主張を展開されました。一方、原告真村氏の弁護団は、同店の残紙は、優越的地位の濫用のもとで生じた「押し紙」なので改廃理由には該当しないと主張しました。つまりこの裁判の最大の争点は、YC広川の残紙がどのような性質のものであるかという点でした。裁判所はこの点を検証したのです。
福岡高裁判決は、貴社の行為を次のように認定しています。引用文中の「定数」とは新聞の搬入部数のことです。
「このように、一方で定数と実配数が異なることを知りながら、あえて定数と実配数を一致させることをせず、定数だけをABC協会に報告して広告料計算の基礎としているという態度が見られるのであり、これは、自らの利益のためには定数と実配数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢であると評されても仕方のないところである。そうであれば、一審原告真村の虚偽報告を一方的に厳しく非難することは、上記のような自らの利益優先の態度と比較して身勝手のそしりを免れないものというべきである。」
判決のこの箇所では、貴社が実配部数と搬入部数の間に齟齬があることを認識していながら、正常な取引部数に修正しなかった事実が認定されています。つまり貴社が注文部数を決めていたのです。さらに裁判所は、その背景に、貴社の部数への異常とも言える執着があることを、次のように認定しています。
「販売部数にこだわるのは一審被告(黒薮注:貴社のこと)も例外ではなく、一審被告は極端に減紙を嫌う。一審被告は、発行部数の増加を図るために、新聞販売店に対して、増紙が実現するよう営業活動に励むことを強く求め、その一環として毎年増紙目標を定め、その達成を新聞販売店に求めている。このため、『目標達成は全YCの責務である。』『増やした者にのみ栄冠があり、減紙をした者は理由の如何を問わず敗残兵である、増紙こそ正義である。』などと記した文章(甲64)を配布し、定期的に販売会議を開いて、増紙のための努力を求めている。
米満部長ら一審被告関係者は、一審被告の新聞販売店で構成する読売会において、『読売新聞販売店には増紙という言葉はあっても、減紙という言葉はない。』とも述べている。」
ここでは貴社が販売店に新聞部数を押し付けるために実施した具体的な言動が記録として刻印されています。貴社の米満部長が、「読売新聞販売店には増紙という言葉はあっても、減紙という言葉はない」と公然と発言している事実。これなどは販売店が注文部数を決定できない貴社の販売政策をずばりと突いています。
◇自由増減を宣言する前は?
さらに判決は、貴社が販売店に対して新聞部数の「自由増減」を認めていなかった事実にも言及しています。「自由増減」とは、販売店が自由に注文部数を決定する権利を保証する制度を意味します。
貴社は皮肉にも真村店主に対して「自由増減」を言い渡しましたが、その経緯は次の通りです。
既に述べたように真村氏は、自店の営業区域を防衛しようとして貴社の方針に服従しなかったために、貴社から販売店の改廃を宣告されました。この改廃宣告に先立つ段階で貴社は、YC広川を「死に店」扱いにすると真村氏に通告しました。
「死に店」扱いとは、癌などの「死病」に例えて説明すると、患者本人ではなく医師が自分の判断で、延命措置をとらないことを意味します。つまり担当員の販売店訪問は取りやめ、販売政策に関する指示も提示しなければ、補助金も支給しない。さらに福利厚生を受ける権利も剥奪する方針を意味します。要するに情け容赦なく、販売店を「自然死」に追い込むことです。
真村氏は池本担当員から決別宣告のように、「死に店」扱いを明記したメモを突きつけられました。そこには、池本氏の自筆で、新聞に関しては「供給持続する」、ただし「自由増減」と明記されていたのです。貴社の「押し紙」を柱にしたビジネスモデルから真村店主を「村八分」にするがゆえに、真村氏に関しては、例外的に自由増減が適用されたのです。
このメモは、「池本メモ」と呼ばれ、後に裁判所へも「押し紙」政策の証拠として提出されました。
貴社がYC広川に対して「自由増減」を宣告する前の時期、そもそも真村店主には自由に注文部数を決める権限がなかったわけですから、貴社が「注文部数」を決めていたことになります。従ってYC広川の残紙は、貴社が真村氏の意思とは無関係に、販売政策に従って部数を決めた結果発生した「押し紙」にほかなりません。この事実ひとつを見ても、貴社の販売政策は独禁法の新聞特殊指定に抵触しております。
実際、福岡高裁判決は、「池本メモ」について次のように貴社の優越的地位の濫用を認定しております。
「池本は、同一審原告に対し、今後、新聞供給は継続すること、注文部数その他につき自由に増減できること、増紙業務は依頼しないこと、読売会活動には不参画とすること、業務報告は不要であるし、池本ら担当員も訪店を遠慮すること、平成14年1月からは増紙支援をしないこと、所長年金積立は中止し、従業員退職金の補助等をしないこと、セールス団関係は、一審原告真村が直接処理すべきこと、特別景品は可能な限り辞退されたいこと、などを申し渡した。」
真村店主は「池本メモ」を突きつけられ、貴社の「鎖」を解かれ、貴社による「押し紙」を柱としたビジネスモデルの歯車から除外されたわけです。従って貴社本来の販売政策は、「押し紙」を前提としたものであるという結論になります。
以上が、本件記事の中でわたしが「この裁判で裁判所は、新聞紙上初めて、押し紙の存在を認定した」と記した理由です。
◇PC上の架空の配達地区
なお、貴殿も抗議書の中で言及されているように、裁判所が判決の中で真村氏による虚偽報告を批判しているのは事実です。「押し紙」を経理処理するためにPC上の「帳簿」に26区と呼ばれる架空の配達地区を設けていたのも事実です。
しかし、それは貴社を独禁法違反から守るために行った「押し紙」隠しの行為にほかなりません。事実、裁判所もこの点を批判した上で、次のような重要な記述を追加していますが、貴殿は最も肝心なこの追加部分を抗議書の中では故意に隠しています。それは次の記述です。判決は、真村店主の虚偽報告を批判した上で、次のように述べています。
「しかしながら、新聞販売店が虚偽報告をする背景には、ひたすら増紙を求め、減紙を極端に嫌う一審被告の方針があり、それは一審被告の体質にさえなっているといっても過言ではない程である。」
ここでも貴社の部数至上主義を上段にかかげた体質が厳しく批判されております。
なお、福岡高裁判決は、貴社に対して真村氏へ慰謝料200万円を支払うように命じています。この200万円という額が慰謝料としていかに破格の高額であるかは、貴社の顧問弁護士にご確認ください。裁判所が高額な慰謝料支払いを命じた背景には、貴社の「押し紙」政策など、優越的地位の濫用によって真村店主が多大な損害を受けたことを裁判所が認めた事情があることは論を待ちません。
◇「一般の読者の普通の注意と読み方」が基準
ちなみに「押し紙」の定義について、参考までに補足しておきます。一般の人々は「押し紙」、あるいは「積み紙」という業界用語の背景にある特殊なビジネスモデルのからくりを知るよしもありません。従って彼らは、販売店の残紙を広義に「押し紙」と呼んでいます。新聞以外の商取引では、売り手が販売予定のない商品を購入する状況はおおよそ想像できず、商品が店舗に多量に余っていれば、それはすなわち「押し売り」の結果と判断するのが自然だからです。それが社会通念です。
貴殿は抗議書の中で、「本件記述は全く事実に反する誤った内容であり、読売新聞の名誉を著しく毀損しています」と述べておられますが、「ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである(31年7月20日、最高裁第二小法廷判決)となっており、一般の読者が「押し紙」という言葉が狭義に定義する意味を理由に、名誉毀損を主張するのはまったく的外れです。
たしかに「押し紙」というその字面、その語感から「押し売り」を連想する人は多いですが、一般の人々が問題にしているのは、販売店で過剰になっている新聞の存在そのものです。従って販売店主に批判の矛先が向けられることもあります。
「押し紙」とは、社会通念上では、漠然と残紙全般を意味しており、業界の特殊用語としての狭義の「押し紙」とは若干区別しなければなりません。
たとえ残紙が狭義の「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、広告主を欺いている事実に変わりはありません。
貴社の販売店、たとえばYC久留米文化センター前やYC大牟田中央、それにYC大牟田明治に約40%から約50%の残紙があった事実は、裁判のプロセス中でも明らかになっております。確かにこれらの残紙は狭義の「押し紙」とは認定されていませんが、少なくとも残紙であることは事実であり、広告主に対する貴社の責任は免れません。
第2次真村裁判について、わたしは本件記事の中ではまったく言及しておりません。それにもかかわらず貴殿の抗議書には、第2次真村裁判に関する記述があります。しかし、2つの裁判を繋ぐうえで不可欠な論理的な整合性が完全に欠落しております。
◇第2次真村裁判
それを踏まえたうえで、ここでは真村氏の名誉のために、次の点にだけ言及しておきます。第2次真村裁判は、真村氏が起こした裁判であることは事実ですが、その原因はすべて貴社にありました。貴殿は、このあたりの事情を正確に取材されたでしょうか。あまりにも事実認識が誤っています。
2007年12月に第1次真村裁判の判決が最高裁で確定した半年後、貴社は真村氏が「黒薮」に読売の販売政策に関する情報を提供したなどと言いがかりをつけて、YC広川を強制改廃しました。これに対して真村氏は再び貴社に対して地位保全裁判を提訴せざるを得ませんでした。そして裁判は、つい先日まで続いたのです。
何の権力も持たない無辜の一個人を法廷に15年近く法廷に縛り付け、人生を台無しにした貴殿たちの行為は、司法制度を濫用した著しい人権侵害です。それを言論機関が断行したことは、日本の新聞史の大きな汚点として記録されています。
貴殿も周知のように、第2次真村裁判は、仮処分申立てと本訴が同時進行しました。仮処分は1審から4審まで真村氏の勝訴でした。裁判所は貴社に対して、YC広川の営業を再開するように命じました。ところが貴社は、この司法命令に従わず、1日に3万円の間接強制金を徴収される事態となりました。資金力で司法命令を踏み倒したのです。
一方、本訴は地裁から最高裁まで貴社の勝訴でした。しかし、仮処分裁判の判決内容と本訴の判決内容が、正面から対立する不可解な現象が裁判記録として書面で残っております。たとえば仮処分裁判の第2審と本訴高裁判決のケースはその典型といえるでしょう。仮処分裁判の第2審で木村元昭裁判長は、真村氏を全面勝訴させました。
その直後、木村判事は、なぜか沖縄県の那覇地裁に転勤になりました。そして再び福岡市へ戻ってくると、今度は福岡高裁へ異動となり、なぜか真村裁判の本訴第2審の裁判長に、裁判長交代のかたちで就任しました。そして今度は、真村氏の主張を情け容赦なく切り捨てたのです。
当然、木村判事が仮処分裁判で書いた判決と本訴で書いた判決を対比し、検討してみると、同じ人物が書いたものとはとても思えないまったく正反対の記述内容となっております。矛盾だらけで支離滅裂の論理性、仮処分判決と本裁判決との整合性などどこにも確認することができません。それが記録として、福岡地裁に永久保存されております。
しかし、この点に関しては、貴殿が抗議書で指摘され、名誉毀損を主張されている本件記事の記述とはまったく関係がないことなので、ここでは言及を避けます。同様に、第1次真村裁判の福岡高裁判決で西裁判長が貴社の「押し紙」を認定した事実と、第2次真村裁判で木村裁判長が、「押し紙」に対する自分の見解を示したことを、貴殿が抗議書の中で無理やりに関連付けられたことも、整合した論理の欠落と言わなければなりません。
本件記事でも書いたように、2007年に福岡高裁が初めて「押し紙」が認定された事実を削除することは出来ません。
つまり第1次真村裁判で初めて狭義の「押し紙」政策が認定されたのは、客観的な事実であり、この事実は、第2次真村裁判で木村裁判官が認定した「押し紙」に関する見解により、変化する性質のものではありません。
貴殿の事実認識の方法が極めて主観的で、事実認識の方法が誤っているというのが、わたしの見解です。
以上が抗議書に対するわたしの回答です。繰り返しになりますが、不明な点などありましたら、真村裁判の裁判資料をもとに、分かりやすく説明しますのでご連絡ください。
読売新聞のABC部数が800万部台に下落、朝日バッシングで部数が減ったという幻想
かつて1000万部の発行部数を誇っていた読売新聞が900万部を切ったことが、2016年4月度の新聞のABC部数で明らかになった。最新のABC部数は、899万8789部である。「読売1000万部」の時代は、事実上、終わったと見て間違いない。
前年同月差では、読売は約11万部の減少である。
一方、朝日新聞の部数は、661万部。前年同月差では、約19万部の減少である。
中央紙各社のABC部数は次の通りである。
朝日:6,606,562(-191,631)
読売:8,998,789(-111,356)
毎日:3,115,972(-185,819)
産経:1,633,827(-30,863)
日経:2,730,772(-8,937)
◇朝日バッシングで部数が減ったという誤解
ABC部数の減少は、一般的には読者離れと解釈されがちだが、新聞販売店を取材した限りでは、新聞社の側が自主的に「押し紙」を減らした可能性の方が高い。新聞社にとって「押し紙」が負担になってきたのだ。
「押し紙」が新聞社に負担になってきたと書くと、不思議に感じる読者も多いかも知れない。販売店にとって「押し紙」が負担になるのであれば、理解できるが、新聞社にとって「押し紙」が負担になるとはどういう意味なのかと?
答えは単純だ。「押し紙」の負担を相殺する手段は、折込広告の水増しである。ところが折込広告の需要が落ち込んで、「押し紙」の負担が相殺できなくなってきた。こうなると新聞社は、販売店に補助金を支給せざるを得ない。さもなければ戸別配達制度が崩壊するからだ。
補助金を支給する代わりに「押し紙」を減らすと、ABC部数が落ちるので、これも簡単には出来ない。ABC部数を維持して紙面広告の媒体価値を維持する必要がある。
さらに2014年4月から消費税が5%から8%に上がった。「押し紙」は販売部数として経理処理されるので、「押し紙」にも消費税がかかる。本来は販売店が支払う税金だが、経営が悪化しているので、これについても新聞社は補助金を提供せざるを得ない。
◇自作自演の可能性も
従軍慰安婦問題の「誤報」と「朝日バッシング」で朝日は、大幅に読者離れを起こしたことになっているが、これは間違いで、朝日新聞の側が「誤報」「朝日バッシング」を逆手に取って、これを理由として「PR」し、みずから「押し紙」を減らしたのだ。わたしが取材した限り、「誤報」による部数減は朝日の自作自演である。
不祥事なしに大幅に「押し紙」を切ると、ABC部数が激減して、広告主が不信感を抱くからだ。どうしても理由が必要だったのだ。
事実、朝日がみずから「誤報」を宣言するという奇妙な行動に出たのは、2014年8月。この時期は、消費税が5%から8%になったわずか4カ月後である。3%の税率アップで、「押し紙」が大きな負担になってきた結果だ。他社も同じ事情があったとわたしは見ている。
事実、新聞業界は今、消費税の軽減税率を5%にするように政界工作を続けている。
ちなみに新聞購読を長年の習慣にしてきた人が、「朝日バッシング」程度で購読を中止することはほとんどない。
佐賀新聞の元店主が「押し紙」裁判を提起、約7100万円の損害賠償を請求、法廷で審理されるABC部数「偽装」の手口、読売・真村訴訟の弁護団が代理人に

「押し紙」で損害を受けたとして、佐賀新聞の元販売店主が6月3日、佐賀新聞社を相手どって約7100 万円の損害賠償を請求する裁判を佐賀地裁で起こした。元店主は、「押し紙」の負担で販売店経営が悪化し、佐賀新聞に対して執拗に「押し紙」の中止を求めていた。新聞社の「押し売り」問題が法廷で審理されることになった。
「押し紙」の実態と損害は次のPDFに示した通りである。
「押し紙」率は、原告が店主になった2009年4月の段階では、10%だったが、ピーク時の2012年6月には19%に増えている。原告が年間に被った損害は、年度によって異なるが年間に、約460万円から約1000万円だった。多額の借金を背負わされて、昨年12月に廃業に追い込まれていた。
◇ABC部数「偽装」の恐るべき手口
訴状によると、佐賀新聞社は、「押し紙」部数を隠すために、ABC部数を偽装するための工作を原告に指示していた。これについて訴状は次のように述べている。
公査を受ける時期になると、被告佐賀新聞社から各販売店へ公査に備えるように連絡がされ、対象となる販売店には1~2日前にはABC協会が公査を告知するため、その販売店に対して被告佐賀新聞は次のような具体的な作業を指示する。
①足りない読者数を穴埋めするために過去の読者を現在の読者のようにみせかけたり、実在する人物を架空の読者に仕立て上げたりする。
②1年ないし半年分の架空の領収書を印刷させ、半券を切り取って破棄し、残った半証を過去の領収書の控えの間に挟ませ、各月の売上金額や配達料を支払った金額、配達部数などの数字もすべて作り変えさせる。
③あとは公査当日に店舗に残っている押し紙(残紙)を必要数以外は隠させ、前日のチラシの作業の終了時には定数近くまで折込機会のカウンターだけ回させる。
④日々の紙分けの作業に使う手板(各配達員に渡すべき部数を書く道具)の数字も各月ごとに不審な点が無いように作り変えさせる。
原告の店舗にABC協会の公査が入った平成23年5月のときも上記の具体的な指示を佐賀新聞より受けており、また被告佐賀新聞は普段から各販売店に上記の隠蔽工作を指導している。
◇新聞社サイドが「押し紙」減部数を指示
「押し紙」は1部も存在しないというのが、従来からの新聞社の主張である。しかし、訴状によると佐賀新聞社は、販売店に指示してABC部数を偽装させているうえに、2013年3月には、全販売店を対象に、全体で搬入部数を2000部減らしている。これは佐賀新聞社が搬入した新聞がすべて配達されていないことをみずから把握していた証拠にほかならない。
さらに翌2014年6月には、やはり全販売店を対象に、搬入部数を3000部減らしている。原告店主の販売店の場合は90部が減数の対象になった。
◇読売・真村訴訟の弁護団が代理人に
新聞社の「押し紙」が初めて司法による認定を受けたのは、2007年である。読売新聞社を相手に、販売店が提起した真村訴訟の判決で、福岡高裁が読売による「押し紙」政策を認定し、その後、判決は最高裁で確定した。
今回の佐賀新聞の「押し紙」裁判では、真村訴訟を担当した江上武幸弁護士らが原告の代理人を務める。
※なお、訴状は準備ができしだいメディア黒書で全文を公開する予定。
訴えた者勝ちで乱発される巨額訴訟 『日本の裁判』を問う、読売・亀田兄弟・SME
『紙の爆弾』(4月号)の記事をPDFで紹介しよう。タイトルは、「訴えた者勝ちで乱発される巨額訴訟 『日本の裁判』を問う」。執筆者は、メディア黒書の黒薮。このところ深刻な社会問題になっているスラップに関する記事である。
この記事で取り上げた裁判は次の通りである。
※作曲家・穂口雄右氏に対して2億円3000万円を請求したミュージックゲート裁判。原告は、レコード会社など31社。被告・穂口氏の和解勝訴。
※読売新聞社がわたしに対して提起した3件の裁判。請求額の総計は約8000万円。それに対する損害賠償裁判。
・著作権裁判:黒薮の完全勝訴(スラップの可能性が高い)
・名誉毀損裁判1:地裁・高裁は黒薮の勝訴。最高裁で読売が逆転勝訴。
・名誉毀損裁判2:読売の完全勝訴
・損害賠償裁判:黒薮の敗訴
※「池澤VS天野」裁判
・係争中
※亀田裁判
ボクシングの亀田興毅・和毅兄弟がフリーランスライターの片岡亮氏に2000万円を請求した裁判。亀田の勝訴。
スラップが多発する背景に、司法制度改革の失敗がある。弁護士活動の規制緩和が、訴訟ビジネスの台頭を招き、「人権派」を売り物にして、訴訟を勧める弁護士が増えているようだ。「営業」は禁止されているはずなのだが。
■「訴えた者勝ちで乱発される巨額訴訟 『日本の裁判』を問う」PDF
残念ながらスラップに対抗する方法は、反撃する以外にない。提訴されたことを逆手に取って、裁判の内容をインターネットなどで細部までおおやけにして、判決後も5年、10年と長期にわたる検証を続けることである。
被告にされた者が勝訴した場合は、損害賠償の訴訟を提起することが不可欠だ。
読売・平山事件の8周年、最高裁が逆転敗訴させた名誉毀損裁判の訴状を公開
3月1日は、読売新聞・平山事件8周年である。平山事件とは、福岡県久留米市の読売新聞久留米文化センター前店の店主だった平山春男さんを、読売が解任した事件である。この事件を機として、複数の裁判が始まることになる。
3月1日の午後、読売の江崎法務室長らは、事前の連絡もせずに平山さんの店を訪問した。そして対応に出た平山さんに解任を通告したのである。それから関連会社である読売ISの社員が、翌日に配布される予定になっていた折込広告を店舗から搬出した。
こうして平山さんの店は、あっけなく幕を閉じたのである。
前年の暮れに平山さんは、対読売弁護団(真村訴訟の弁護団)を通じて、「押し紙」(広義の残紙を意味する)を断った。弁護団がその後、作成したリーフレット『「押し紙」を知っていますか?』によると、2007年11月時点における平山店への新聞の搬入部数は2010部だった。このうち997部が配達されずに余っていた。
◇双方が提訴
この事件では、双方が相手に対して裁判を起こした。読売は、平山さんに店主としての地位が存在しないことを確認する裁判を、平山さんは地位保全の裁判をそれぞれ起こした。裁判は読売の勝訴で終わった。
平山さんは高裁で敗訴した後、病死された。
◇名誉毀損裁判も提起
平山事件の報道をめぐり、わたしも読売から裁判を起こされた。
事件が起きた3月1日、福岡県の販売店主から連絡を受け、わたしはその日のうちに新聞販売黒書(現・メディア黒書)に臨時ニュースを掲載した。その記事の中で、読売関係者が行った折込広告の搬出行為を「窃盗」と書いた。
予告することなく平山さんに解任を告げ、著しい精神的衝撃を与えた状態で、折込広告の搬出行為を行ったと推測されるので、「窃盗のように悪質」という意味の隠喩(メタファー)を使った表現を採用したのである。
事件から11日後の3月11日、読売の江崎法務室長らは、さいたま地裁に一通の訴状を提出した。被告は、わたしだった。「窃盗」は事実の摘示にあたり、事実に反するという主張等を前提に、2200万円(弁護士費用200万円を含む)の金銭等を要求する裁判を起こしたのである。
判決は、さいたま地裁、東京高裁はわたしの勝訴。しかし、最高裁が小法廷を使って口頭弁論を開催し、判決を東京高裁へ差し戻したのである。
そして東京高裁の加藤新太郎裁判長が、わたしに110万円の金銭支払いを命じたのである。
加藤氏はその後、退官。その後、大手弁護士事務所・アンダーソン・毛利・友常法律事務所に顧問として再就職した。なお、加藤氏が読売新聞に登場していたことが、後に判明する。次の記事である。
わたしは裁判の公平性という問題を考えざるを得なかった。高裁の事務局は担当裁判官の選任を間違ったのではないか?
なお、平山裁判とわたしの裁判に、読売の代理人として登場したのは、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。喜田村氏らは、「押し紙」の存在を否定してきた。
裁判官の不可解な人事異動-木村元昭・田中哲朗の両氏、対読売の真村裁判・平山裁判・黒薮裁判で
 2002年に福岡地裁久留米支部で始まった真村訴訟とそれに関連して派生した2つの裁判-平山裁判、黒薮裁判-でも、裁判長の不可解な人事異動が記録として残っている。
2002年に福岡地裁久留米支部で始まった真村訴訟とそれに関連して派生した2つの裁判-平山裁判、黒薮裁判-でも、裁判長の不可解な人事異動が記録として残っている。
真村訴訟というのは、YC(読売新聞販売店)と読売新聞西部本社との間で争われた地位保全裁判だ。読売がYCの真村店主に解任を通告したところ、真村氏(厳密には原告は3名)が起こしたものである。読売側の代理人には、喜田村洋一・自由人権協会代表理事らが就いた。
この裁判は真村氏の完全勝訴だった。争点となった「押し紙」政策の存在を裁判所が認定した。これについての詳細は、ここでは言及せず、福岡高裁判決の全文のみをリンクしておこう。
◇歴史に刻まれた木村元昭氏の名前
真村裁判の判決は2007年12月に最高裁で確定した。最高裁が真村氏の地位を保全したのだ。従って本来であれば、真村氏はYCの経営を持続できたはずだが、読売は判決が確定してから7カ月後に、真村氏を一方的に解任したのである。その結果、真村氏は再び地位保全裁判を起こさなければならなかった。これが第2次真村訴訟である。
第2次真村訴訟では、仮処分申立てと本訴が同時進行した。
仮処分の裁判では1審から最高裁での特別抗告まで、真村氏の勝訴だった。このうち第2審(福岡地裁・異議申し立て)を担当したのは、木村元昭裁判官だった。木村氏は、真村氏を勝訴させた直後、那覇地裁に転勤になった。
一方、本訴の審理も進み、福岡地裁の判決が出たのは、2011年3月15日だった。この時点で仮処分申立ては、第3審まで終わっていたので、地裁での本訴の敗訴は、第1次真村裁判が始まって以来、真村氏には初めての敗訴だった。
当然、真村氏は福岡高裁へ控訴した。が、控訴審がはじまってまもなく、裁判長が交代することになった。新しい裁判長は、那覇地裁から福岡に戻ってきた木村元昭氏だった。真村氏を仮処分申立ての第2審で勝訴させた判事だった。当然、真村氏は救われたような思いになった。
ところが控訴審の判決は、真村氏の敗訴だった。木村氏が執筆した2つの判決-仮処分の判決と本訴の判決-を読み比べてみると、実に興味深い。同じ人間が執筆したとは思えないほど正反対の判断をしているのだ。(詳細については、拙著『新聞の危機と偽装部数』の6章「人権問題としての真村裁判」に詳しい)
はからずも2010年代の裁判の不可解な実態が、「木村元昭」の名前と共に永久に記録されたのである。その意味では貴重な記録だ。
◇田中哲郎裁判官の登場
話は前後するが、第1次真村訴訟の判決が最高裁で確定したころから、読売はわたしに対する裁判攻勢に打ってでる。既に述べたようにわたしは、1年半の間に3件の訴訟を起こされ、約8000万円の金銭を要求されたのだ。読売の代理人弁護士として、この裁判の先頭に立ち、自分たちの主張の正当性を主張したのは、喜田村弁護士らだった。
そのころYC久留米文化センター前の平山春男店主も裁判に巻き込まれた。残紙を断った数カ月後に店主を解任されたのが原因だった。読売は平山氏に店主としての地位が存在しないことを確認する裁判を起こし、平山氏は地位保全裁判を起こした。この裁判でも喜田村弁護士が登場した。
平山裁判の裁判長に就任したのは、福岡地裁久留米支部から異動になった田中哲郎裁判官だった。実は、この裁判官は、第1次真村裁判の判決を下した人であった。真村氏を勝訴させた人である。その人物が平山裁判の裁判長に就任したのだ。
◇田中判事から木村判事へ判事へバトン
平山裁判が進行していた2011年の秋、わたしは読売を反訴した。さらにその後、読売がわたしに対して3件目の裁判を起こしたのを機に、わたしは読売に対する請求内容を変更し、3件の裁判が「一連一体の言論弾圧」であるという主張の裁判を起こした。請求額は5500万円だった。
ところがこの裁判は、途中から裁判長が田中哲郎氏に変更になった。
読者は、おそらく判決の結果を想像できるだろう・・・・。平山裁判も黒薮裁判も読売の勝訴だった。田中哲郎氏に至っては、わたしに対する本人尋問すら認めなかった。わたしの陳述書も最初は受け取ろうとはしなかったのだ。そのために江上弁護士ら弁護団は、田中氏に対する忌避を申し立てたのである。
わたしは福岡高裁へ控訴した。そこに登場したのは、木村元昭裁判官だった。木村氏がどのような判決を書いて、わたしを敗訴させたかは、別に述べる機会があるかも知れない。
読者は最高裁事務総局が決めた人事に不可解なものを感じないだろうか?