喜田村洋一弁護士が作成したとされる催告書に見る訴権の濫用、読売・江崎法務室長による著作権裁判8周年①
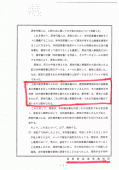 2008年2月25日に読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、東京地方裁判所にわたしを提訴してから、今年で8年になる。この裁判は、わたしが「新聞販売黒書」(現MEDIA KOKUSYO)に掲載した江崎氏名義のある催告書の削除を求めて起こされた著作権裁判だった。
2008年2月25日に読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、東京地方裁判所にわたしを提訴してから、今年で8年になる。この裁判は、わたしが「新聞販売黒書」(現MEDIA KOKUSYO)に掲載した江崎氏名義のある催告書の削除を求めて起こされた著作権裁判だった。
その後、読売はわずか1年半の間にわたしに対して、さらに2件の裁判を起こし、これに対抗してわたしの方も読売に対して、立て続けの提訴により「一連一体の言論弾圧」を受けたとして、約5500万円の損害賠償を求める裁判を起こしたのである。さらにこれらの係争に加え、読売の代理人・喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する懲戒請求を申し立てたのである。
喜田村氏は4件の裁判のいずれにもかかわった。
提訴8周年をむかえる著作権裁判は、対読売裁判の最初のラウンドだった。
読売・江崎氏の代理人には、喜田村弁護士が就任した。一方、わたしの代理人は、江上武幸弁護士ら9名が就いた。
しかし、この裁判の発端は、福岡県広川町にあるYC広川(読売新聞販売店)と読売の間で起こった改廃(強制廃業)をめぐる事件だった。当時、「押し紙」問題を取材していたわたしは、真村事件と呼ばれるこの係争を取材していた。
◇公募で新聞販売店主に
YC広川の店主・真村久三氏は、もともと自動車教習所の教官として働いてきたが、40歳で新聞販売店の経営を始めた。読売が販売店主を公募していることを知り、転職に踏み切ったのである。脱サラして自分で事業を展開してみたいというのが、真村氏のかねてからの希望だった。
幸いに真村氏は店主に採用され、研修を受けたあと、YC広川の経営に乗りだした。1990年11月の事だった。ところがそれから約10年後、読売新聞社との激しい係争に巻き込まれる。
その引き金となったのは読売新聞社が打ち出した販売網再編の方針だった。真村氏は、YC広川の営業区域の一部を隣接するYCへ譲渡する提案を持ちかけられたのだ。が、YC広川の営業区域はもともと小さかったので、真村氏は譲渡案を受け入れる気にはならなかった。それに自助努力で開業時よりも、読者を大幅に増やしていた。
読売の提案を聞いたとき真村氏は、自分で開墾した畑を奪い取られるような危機を感じたのだ。
当然、読売の提案を断った。これに対して読売は、真村氏との取引契約を終了する旨を通告した。その結果、裁判に発展したのだ。これが真村訴訟と呼ばれる有名な訴訟の発端だった。が、係争が勃発したころは、単に福岡県の一地方の小さな係争に過ぎなかったのだ。江上弁護士も、読売の実態をあまり知らなかったし、後にこの判決が「押し紙」問題の有名な判例になるとは予想もしていなかった。
真村事件の経緯は膨大なので、ここでは省略するが、結論だけを言えば、裁判は真村氏の勝訴だった。喜田村弁護士が東京からやってきて加勢したが及ばなかった。判決は、2007年12月に最高裁で確定した。
◇真村訴訟
わたしが読売との係争に巻き込まれたのは、真村訴訟の判決が最高裁で確定する数日前だった。真村氏が福岡高裁で勝訴したころから、YC店主が次々と江上弁護士に「押し紙」(残紙)の相談を持ちかけるようになった。店主のあいだで新しい店主会-新読売会を立ち上げる動きもあった。
こうした状況下で、読売も方針を転換したのか、それまで「死に店扱い」にして、訪店を控えていたYC広川への訪店を再開することにした。そしてその旨を真村氏に連絡した。
しかし、読売に対して不信感を募らせていた真村氏は即答を控え、念のために江上弁護士に相談した。訪店再開が何を意味するのか確認したかったのだ。江上弁護士は、読売の真意を確認するための内容証明郵便を送付した。これに対して、読売の江崎法務室長は、次の書面を送付した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、新聞販売黒書で係争の新展開を報じ、その裏付けとしてこの回答書を掲載した。何の悪意もなかった。しかし、江崎氏(当時は面識がなかった)はわたしにメールで次の催告書(PDF)を送付してきた。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
わたしは、今度はこの催告書を新聞販売黒書で公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権に基づいて、削除するように求めてきたのである。
が、催告書の作者は別にいたのだ。東京地裁と知財高裁は、喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフが本当の作者である可能性が極めて強いと認定して、江崎氏の訴えを退けたのだ。
彼らは催告書の名義人を「江崎」に偽って提訴し、法廷で著作者人格権を主張したのだ。もともと提訴権がないのに、虚偽の事実を前提に裁判を起こしたのである。
このあたりの事情については、弁護団声明を参考にしてほしい。弁護団は、この事件を「司法制度を利用した言論弾圧」と位置づけている。
◇怪文書・恫喝文書
さて、提訴8周年にあたる今年は、喜田村弁護士が執筆したとされる「江崎名義」の催告書の内容を検証しよう。著作権裁判では、とかく文章の形式が検証対象になり、書かれた内容には重きがおかれない傾向があるが、ジャーナリズムでは、書かれた内容そのものを検証する。
結論を先に言えば、これは怪文書である。あるいは恫喝文。しかも、それが自由人権協会の代表理事によって作成されたのだ。
繰り返しになるが、この催告書の作者は、催告書の中で、江崎氏が江上弁護士に送付した書面を新聞販売黒書から削除するように求めてきたのである。その送付された書面を再度引用してみよう。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
つまり催告書は、上に引用した書面が江崎氏の著作物なので削除するように求めているのだ。そしてそれに従わない場合は、民事訴訟か刑事訴訟も辞さない旨をほのめかしているのだ。
著作権法の知識に乏しいわたしは、著作権法でいう「著作物」の定義を調べてみた。すると次のような記述があった。
一 、著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
江崎氏が江上弁護士に送付した書面は、どの角度から見ても、著作物ではない。念のために複数の専門家に問い合わせみたが、この書面が著作物だとする人はひとりもいなかった。
それにもかかわらず催告書は、江上弁護士へ送られた書面は江崎氏の著作物なので、それを削除しなければ、民事訴訟か刑事訴訟も辞さない旨を述べているのだ。わたしは、この文書を怪文書・恫喝文書としか評価できなかった。それゆえにそれを新聞販売黒書に載せたのだ。読売の法務室長が奇妙な文書を送ってきたという思いで。これ自体が大きなニュースだった。
◇喜田村弁護士が言及した著作物の定義
その後、わたしは著作物に関する喜田村弁護士の言動を注視するようになった。と、2013年の5月になって宝島社から『佐野真一が殺したジャーナリズム』という本が出版された。この本に、喜田村弁護士が「法律家がみた『佐野眞一盗用問題』の深刻さ」と題する一文を寄せた。
その中ではからずも喜田村氏が著作物の定義に言及していることが分かった。取材の協力者のひとりが情報を寄せてくれたのだ。同書の中で、喜田村弁護士は「著作物」について、次のように記している。
(略)まず、著作物は「表現」でなければならないから、「思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など」で、表現でないものは、著作物になりえない。
たとえば、「○月○日、△△で、AがBに~と言った(AがBを手で殴りけがをさせた)」いうような事実ないし事件そのものは、表現ではないから、著作権法の対象ではない。同様に、「ある事件についての見方」とか、「ある事件を報じるにあたっての方法」といったアイデアに属するものも、表現ではないから、著作権法の保護は受けられない。
また、創作性がなければならないから、ごく短い文章で、誰が書いても同じようになるようなものであれば、これも著作物ではない。(略)
裁判所は、催告書の作者が喜田村弁護士である高い可能性を認定したが、たとえ作者が名義人の江崎氏であっても、代理人弁護士の喜田村氏が、催告書の内容を確認していないはずがない。読めば、内容それ自体がデタラメであることが分かったはずだ。なぜ、訴訟を思いとどまらせなかったのだろうか。なぜ、催告書の内容が間違っていることを指摘しなかったのだろうか。
これが訴権の濫用でなくして何だろうか?
著作権裁判の検証は、これから9年目に入る。
