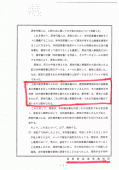読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、喜田村洋一・自由人権協会代表理事を代理人として、わたしに対して著作権裁判を起こして8年が過ぎた。「戦後検証」は、係争の発端から8年目に入る。2007年12月21日、江崎氏はEメールでわたしに対してある催告書を送りつけてきた。(判決文、弁護士懲戒請求・準備書面のダウンロード可)
◇新聞販売黒書に掲載した2つの書面
発端は福岡県広川町で起こった読売新聞社とYC広川(読売新聞販売店)の間で起こった強制廃業をめぐるトラブルだった。当時、新聞販売の問題を取材していたわたしは、この事件を取材していた。
幸いに係争は解決のめどがたち、2007年の末に読売はそれまで中止していたYC広川に対する担当員の定期訪問を再開することを決めた。しかし、読売に対する不信感を募らせていたYC広川の真村店主は、読売の申し入れを受け入れるまえに、念のために顧問弁護士から、読売の真意を確かめてもらうことにした。
そこで代理人の江上武幸弁護士が書面で読売に真意を問い合わせた。これに対して、読売は江崎法務室長の名前で次の回答書を送付した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、新聞販売黒書でこの回答書を紹介した。すると即刻に江崎氏(当時は面識がなかった)からメールに添付した次の催告書が送られてきたのである。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。
貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
回答書が自分の著作物なので削除するように求めているのだ。(回答書の著作物性については後述する)
わたしは、回答書の削除を断り、逆に今度はこの催告書を新聞販売黒書(現在のメディア黒書)で公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権(注:後述)に基づいて、削除するように求めてきたのである。
が、催告書の作者は江崎氏ではなく、代筆者がいたのだ。少なくとも、後日、裁判所はそう判断したのだ。
◇喜田村洋一・自由人権協会代表理事が登場
わたしは催告書を削除するように求める江崎氏の申し出を断った。その結果、江崎氏は仮処分を申し立ててきた。ここで江崎氏の代理人として登場したのが、名誉毀損裁判や著作権裁判のスペシャリスト、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。
仮処分は代理人なしに臨み、わたしの敗訴だった。そこで本訴になったのである。わたしの代理人には、江上弁護士ら福岡の販売店訴訟弁護団がついた。
著作権裁判では、通常、争点の文書、この裁判の場合は江崎氏の催告書が著作物か否かが争われる。著作物とは、著作権法によると、次の定義にあてはまるものを言う。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
改めて言うまでもなく、争点の文書が著作物に該当しなければ、著作権法は適用されない。
わたしの裁判でも例外にもれず、争点の催告書が著作物か否かが争われた。催告書の著作物性を争った裁判は、日本の裁判史上で初めてではないかと思う。ちなみに、新聞販売黒書に掲載した肝心の回答書の方は、争点にならなかった。
◇意外な決着
裁判は意外なかたちで決着する。裁判所は、「江崎名義」の催告書の著作物性を判断する以前に、そもそも江崎氏が催告書の作成者ではないと判断したのである。つまりもともと江崎氏には著作者人格権を根拠とした「提訴権」がないにもかかわらず、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴に及んでいたと判断したのである。
なぜ、裁判所はこのような判断をしたのだろうか。詳細は判決に明記されているが、ひとつだけその理由を紹介しておこう。催告書の書式や文体を検証したところ、喜田村弁護士がたまたま「喜田村名義」で他社に送っていた催告書とわたし宛ての催告書の形式がそっくりであることが判明したのだ。同一人物が執筆したと判断するのが、自然だった。
つまり催告書を執筆していたのは喜田村弁護士だった。それにもかかわらず江崎氏は、自分が著作権者であることを主張したのだ。認められるはずがなかった。そもそも提訴権すらなかったのだ。
当然、江崎氏は門前払いのかたちで敗訴した。東京高裁でも、最高裁でも抗弁は認められず、江崎氏の敗訴が確定した。
◇だれが作者なのかという問題
おそらく読者の大半は、著作権という言葉を聞いたことがあるだろう。文芸作品などを創作した人が有する作品に関する権利である。その著作権は、大きく著作者財産権と著作者人格権に分類されている。
このうち著作者財産権は、作品から発生する財産の権利を規定するものである。たとえば作者が印税を受け取る権利である。この権利は第3者にも譲渡することができる。
これに対して、著作者人格権は、作者だけが有する特権を規定したものである。たとえば未発表の文芸作品を公にするか否かを作者が自分で決める権利である。第3者が勝手に公表することは、著作者人格権により禁じられている。
著作者人格権は、著作者財産権のように他人に譲渡することはできない。「一身専属」の権利である。
代理人は、既に述べたように、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。
裁判所は判決の中で、催告書を執筆したのは喜田村弁護士か彼の事務所スタッフであった高い可能性を認定した。
◇弁護士懲戒請求
弁護士職務基本規程の第75条は、次のように言う。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
喜田村弁護士は、問題になった「江崎名義」の催告書をみずから執筆していながら、江崎氏が書いたという前提で裁判の準備書面などを作成し、それを裁判所に提出し、法廷で自論を展開したのである。
当然、弁護士職務基本規程の第75条に抵触し、懲戒請求の対象になる。わたしが懲戒請求に踏み切ったゆえんである。
◇弁護士倫理の問題
なお、裁判の争点にはならかなったが、喜田村弁護士に対する懲戒請求申立ての中で、わたしが争点にしているもうひとつの問題がある。ほかならぬ催告書に書かれた内容そのものの奇抜性である。
著作権裁判では、とかく催告書の形式ばかりに視点が向きがちだが、書かれた内容によく注意すると、かなり突飛な内容であることが分かる。怪文書とも、恫喝文書とも読める。端的に言えば内容は、江崎氏がわたしに送付した回答書が江崎氏の著作物なので、削除しろ、削除しなければ、刑事告訴も辞さないとほのめかしているのだ。
回答書は、本当に著作権法でいう著作物なのだろうか?再度、回答書と著作権法の定義を引用してみよう。
【回答書】 前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
【著作物の定義】 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
誰が判断しても、著作物ではない。しかも、この内容の催告書を書いたのは、著作権法の権威である喜田村弁護士である。回答書が著作物ではないことを知りながら、催告書には著作物だと書いたのだ。
弁護士として倫理上、こうした行為が許されるのか疑問がある。が、日弁連はこの懲戒請求を喜田村弁護士を調査することなく却下した。
わたしは今でも、この判断は間違っていると考えている。
■知財高裁判決
■参考資料:懲戒請求申立・準備書面(1)
 読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、2008年に起こした著作権裁判の検証の2回目である。この裁判では、江崎氏が書いた次の文章が著作物であると述べた催告書が争点になった。
読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、2008年に起こした著作権裁判の検証の2回目である。この裁判では、江崎氏が書いた次の文章が著作物であると述べた催告書が争点になった。