読売「押し紙」裁判、喜田村洋一(自由人権協会代表理事)らが勝訴判決の閲覧制限を申し立て、大阪高裁は3日付けで閲覧制限を認める

読売新聞「押し紙」裁判の続報である。読売の代理人を務める自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士らが、大阪高裁判決(読売勝訴)の閲覧制限を大阪高裁に申し立てていたことが分かった。
これを受けて、読売勝訴の判決を執筆した大阪高裁の長谷部幸弥裁判長が、3日付けで、早々とそれを認める決定を下した。
閲覧制限が認められた記述の中には、読売の残紙の実態を摘示する箇所も含まれている。
読売が申し立てた「押し紙」裁判の判決文に対する閲覧制限事件①、その後の経緯と自由人権協会代表理事・喜田村弁護士への疑問

読売新聞の「押し紙」裁判(大阪地裁、濱中裁判、読売の勝訴)の判決文に対して、読売新聞が閲覧制限を申し立てた件について、その後の経過を手短に説明しておこう。既報したように発端は、メディア黒書に掲載した『読売新聞「押し紙」裁判(濱中裁判)の解説と判決文の公開』と題する記事である。この記事は、文字通り読売「押し紙」裁判についてのわたしなりの解説である。
この記事の中で、わたしは判決全文を公開した。ところがこれに対して読売(大阪本社)の神原康行法務部長から、書面で判決文の削除を要求された。理由は、読売が判決文の閲覧を制限するように裁判所に申し立てているからというものだった。法律上、閲覧制限の申し立てがなされた場合、裁判所が判決を下すまでは、当該の文書や記述を公開できない。神原部長の主張には一応道理があるので、わたしはメディア黒書から判決文を削除した。
※ただし、ジャーナリズムの観点からは、はやり公開を認めるべきだと思う。「押し紙」という根深い問題を公の場で議論する上で大事な資料になるからだ。
ここまでは既報した通りである。その後、裁判所は読売の申し立てを認めた。法律を優先すれば、判決文は公開できないことになる。しかし、裁判所が判決文全文の閲覧を制限したのか、それとも読売にとって不都合な記述だけに限定して閲覧を制限したのかは不明だ。そこでわたしは、読売の神原部長に対して、判決文全文の非公開を希望しているのか、それとも部分的な記述だけに限定した非公開を希望しているのかを問い合わせた。
現在、その回答を待っている段階だ。
◆◆
 この閲覧制限の手続きを行ったのは、喜田村洋一弁護士ら6人の弁護士である。喜田村弁護士は、日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事を務めている。古くから読売の代理人として働いてきた人で、読売の販売店訴訟を処理するために福岡地裁へも頻繁に足を運んでいた。元店主に対して家屋の差し押さえの手続きなどを行ったこともある。
この閲覧制限の手続きを行ったのは、喜田村洋一弁護士ら6人の弁護士である。喜田村弁護士は、日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事を務めている。古くから読売の代理人として働いてきた人で、読売の販売店訴訟を処理するために福岡地裁へも頻繁に足を運んでいた。元店主に対して家屋の差し押さえの手続きなどを行ったこともある。
読売は喜田村弁護士を代理人に立て、わたしに対しても2008年から1年半の間に3件の裁判を起こしている。請求額は、約8000万円。(このうちの1件は、新潮社とわたしの両方が被告)。
3件のうち最初の裁判は、わたしが読売の法務室長から受け取った催告書(ある文書の削除を求める内容)を、わたしがメディア黒書で公開したことである。法務室長が書いた催告書をわたしが無断で公開したというのがその建前だった。法務室長は、催告書の著作権人格権が自分に属していることを根拠として裁判を起こしたのだ。
 ところが裁判の中で、この催告書は法務室長名義になっているものの、実際の執筆者は喜田村弁護士である高い可能性が判明した。著作権人格権は他人の譲渡することはできない。つまり法務室長には、著作権人格権を根拠として裁判を起こす資格がなかったことが判明したのだ。当然、読売の法務室長は門前払いのかたちで敗訴した。
ところが裁判の中で、この催告書は法務室長名義になっているものの、実際の執筆者は喜田村弁護士である高い可能性が判明した。著作権人格権は他人の譲渡することはできない。つまり法務室長には、著作権人格権を根拠として裁判を起こす資格がなかったことが判明したのだ。当然、読売の法務室長は門前払いのかたちで敗訴した。
催告書の執筆者である喜田村弁護士は、法務法務室長による提訴が成立しないことを知りながら、訴状を作成し、この裁判の代理人として働いたのである。
この裁判の判例は、裁判提起により「押し紙」報道の弾圧を試みて失敗した例と、わたしは考えている。参考までの判決(知財高裁)の全文を紹介しておこう。
◆◆
 さて「押し紙」問題はすでに周知の事実になっている。「押し紙」とは何かという定義の議論は決着しておらず、それゆえに「押し紙」裁判が複雑化しているわけだが、俗にいう残紙が大量に発生している事実だけは否定できなくなっている。
さて「押し紙」問題はすでに周知の事実になっている。「押し紙」とは何かという定義の議論は決着しておらず、それゆえに「押し紙」裁判が複雑化しているわけだが、俗にいう残紙が大量に発生している事実だけは否定できなくなっている。
実際、濱中裁判でも大量の残紙があった事自体は認定されている。濱中さんが敗訴したとはいえ、一時期に限定して読売による独禁法違反も認定された。
残紙の責任が販売店にあるにしろ、新聞社にあるにしろ残紙が発生していることは、紛れのない事実なのである。
これは読売に限ったことではなく、日本の新聞社に共通した暗部である。それが生み出している利益を試算すると驚異的な数字が浮かび上がってくる。
日本全国で印刷される一般日刊紙の朝刊発行部数は、2021年度の日本新聞協会による統計によると、2590万部である。このうちの20%にあたる518万部が「押し紙」と想定し、新聞1部の卸卸価格を1500円(月額)と仮定する。この場合、「押し紙」による被害額は77億7000万円(月額)になる。この金額を1年に換算すると、約932億円になる。
旧統一教会による被害額が35年間で1237億円であるから、この金額と「押し紙」による被害額を比較するためには、1年間の「押し紙」による被害額932億円を35倍(35年分)すれば、その金額が明らかになる。結論を言えば、32兆6200億円である。
この莫大な金額に公権力機関が着目すれば、メディアコントロールが可能になる。公権力機関は、「押し紙」政策の取り締まりを控えさえすれば、暗黙のうちに新聞社を配下に置くことができる構図になっている。それにゆえに「押し紙」問題は、ジャーナリズムの根幹にかかわる問題なのである。単に商取引の実態だけを問題としているのではない。
◆◆
何人もの販売店主とその家族が、「押し紙」により人生を無茶苦茶にされてきた。喜田村弁護士は、そのことを想像してみるべきではないか。自由と人権の旗をかかげるのであれば、プライバシーに配慮した上で判決文を公開して、「押し紙」問題を議論する方向で動くべきではないか。それが多くのメディア企業がかかわっているこの問題を解決するための道筋である。
読売・大門駅前店の「押し紙」裁判、19日に大阪地裁で尋問、喜田村洋一・自由人権協会代表理事が出廷か?

読売新聞・大門駅前店の元店主が2018年8月に約4100万円(後に約1億2500万円に増額)の損害賠償を求めた「押し紙」裁判の尋問が、1月19日に大阪地裁で開かれる。スケジュールは次の通りである。
日時:2023年1月19日、午前10時~夕方
場所:大阪地裁1007号法廷(本館の10階)
証人:原告本人と被告会社の販売局員
だれでも傍聴できる。
注目すべき点は、裁判所が「押し紙」の定義をどう判断するのかと裁判所の指示に従って読売が提出した文書類の評価である。また、原告が「押し紙」の受け入れを断ったことを裏付けるショートメールが裁判所に提出されており、これをどう評価するかも注目される。
読売の代理人弁護士として喜田村洋一・自由人権協会代表理事が出廷する可能性が高い。
「押し紙」裁判は、このところ新聞社側(産経、読売、日経)が3連勝しているが、新聞離れが急激に進み、「押し紙」が販売店の大きな負担になっている状況の下で、裁判所が判断を変更する可能性もある。春には判決がでる見込みだ。
裁判所が「押し紙」の定義の明確化を求める、読売の代理人は喜田村洋一・自由人権協会代表理事、残紙率50%の読売・濱中裁判の第1回口頭弁論

読売新聞・YC門前駅前店の元店主・濱中勇志さんが8月に、読売新聞大阪本社に対して起こした「押し紙」裁判の第1回口頭弁論が、10月22日の午後、大阪地裁で開かれた。
原告の訴状、それに対する被告・読売新聞の答弁書の提出を確認した後、池上尚子裁判長は原告に対して、「押し紙」の定義をより具体的に示すように求めた。これは読売側が、答弁書の中で釈明を求めている事柄でもある。
今後の裁判の進行については、口頭弁論(公開)の形式で行われることになった。
「押し紙」裁判は、これまで弁論準備(非公開)のかたちで行われることがよくあったが、マスコミが注目している裁判なので公開での審理を希望すると原告が表明したのを受けて、読売もそれに同意した。
読売の代理人は、喜田村洋一・自由人権協会代表理事ら5人の弁護士が務める。喜田村弁護士は、かねてから読売には「押し紙」は1部も存在しないと主張してきた経緯がある。読売新聞も日本新聞協会も同じ見解である。
読売は、濱中裁判でも基本的に同じ主張を展開する可能性が高い。
原告の代理人は、江上武幸弁護士ら6人が務める。江上弁護士は、「押し紙」を水面下の問題から、表舞台に出した2度に渡る真村裁判の弁護団長を務めた。第1次訴訟では、福岡高裁が、読売による「押し紙」政策を認定(2007年)した経緯がある。この判決を受けて、『週刊ダイヤモンド』などの雑誌が次々と「押し紙」問題を提起した。
しかし、読売が『週刊新潮』とわたしに対して名誉毀損裁判を起こしたあと、「押し紙」報道は下火になった。
第2回の口頭弁論は12月17日の11:45分から行われる。
◆読売の「求釈明」
 読売は答弁書の「求釈明」の節で中で、「押し紙」の定義と具体的な「押し紙」の証拠を示すように釈明を求めている。次のくだりである。
読売は答弁書の「求釈明」の節で中で、「押し紙」の定義と具体的な「押し紙」の証拠を示すように釈明を求めている。次のくだりである。
原告の主張する「必要部数」、「押し紙」、「仕入れ単価」などの根拠及びその証拠を示すよう(黒薮注:原告に)求めるとともに、被告が上記①(黒薮注:下記参考)ないし③の行為(黒薮注:下記参考)を行ったことについて、だれが、いつ、どこで、なにを、どのように行ったのかという詳細についての具体的な主張及び証拠を示すように求める」
①と②は以下と通りである。
①原告がその経営上真に必要であるとして実際に販売している部数にいわゆる予備紙等(被告代理人註:この「予備紙等」との表現の「等」に何が含まれているのかは不明である。)を加えた部数(必要部数)を超えて供給する方法(注文部数超過行為)
③2280部という定数を定めて当該部数を仕入れるように指示する方法(注文部数指示行為)
【「押し紙」裁判の解説】
従来の「押し紙」は、今年の5月に販売店勝訴の判決が下りた佐賀地裁のケースを除いて、販売店で残紙になってた部数が、「押し紙」なのか、それとも「積み紙」なのかが最大の争点になってきた。
「押し紙」というは、簡単に言えば、新聞社が押し売りした部数のことである。これに対して「積み紙」というのは、販売店がみずから注文した部数のことである。販売店がみずから過剰な部数を注文する場合がある背景には、新聞の搬入部数に対して折込広告の搬入枚数が決まる基本原則があることや、残紙を含む搬入部数に対して新聞社が補助金の額を決めるなどの事情がある。
しかし、最近は広告主が自主的に折込広告の発注部数を減らすことが多く、「新聞の搬入部数=折込広告の搬入部数」の原則が崩れているというのが、常識的な見方である。PR手段が多様化する中で、折込広告の需要は大幅に下落している。
ただし、地方自治体の広報紙については、この不正な商慣行が依然として維持されている。
「押し紙」の定義は、裁判所が残紙の性質を判断するための前提条件になる。過去の判例では、残紙の性質が「押し紙」なのか、それとも「積み紙」なのかの判断で、判決の明暗も分かれてきた。残紙の存在は認定するが、その中身は「積み紙」と判断した判例が多い。
しかし、2010年ごろから、残紙の性質を「押し紙」と認定した上で、販売店が和解勝訴するケースが増えている。
佐賀新聞の「押し紙」裁判では、裁判所は、新聞の実配部数に予備紙を加えたものを新聞販売店が真に必要な部数とした上で、それを超える部数は理由のいかんを問わず、「押し紙」と認定した。残紙は、「積み紙」ではないと判断したのだ。
「押し紙」の定義を明らかにして、それを前提に残紙の性質を検証しようというのが、これまでの裁判の共通した争点である。「押し紙」裁判は、販売店が損害賠償を求める裁判であるから、損害の有無の検証は当然である。
しかし、ジャーナリズムの視点からすると、それ以前の問題がある。残紙の性質が「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、大量の残紙そのものが社会通念からして、公共の秩序を乱しているとする視点である。濱中裁判のケースでは、搬入されていた新聞の約50%が残紙になっていた。なぜ、このようなビジネスモデルが放置されきたのか?
新聞のビジネスモデルそのものが公序良俗違反に該当する可能性が高い。公序良俗違反について、民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と明記している。
原告は、裁判の中で公序良俗違反を主張するものと見られる。
この裁判を通じて、日本の新聞社のビジネスモデルを考える必要があるだろう。
【資料】
カルロス・ゴーンとグレッグ・ケリーの代理人を務める自由人権協会の2人の弁護士、弘中惇一郎と喜田村洋一 、過去には武富士や読売の代理人
日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役が逮捕されてのち、2人の著名な弁護士が登場した。弘中惇一郎弁護士と喜田村洋一弁護士である。
二人には、薬害エイズ事件の安部英被告の代理人を務めて無罪を勝ち取った経歴がある。ロス疑惑事件では、三浦和義被告を無罪にした。
弘中弁護士について言えば、サラ金の武富士の代理人を務めて、フリーランスライターや出版社を攻撃し続けた経歴がある。一方、喜田村弁護士は、読売新聞の代理人を務め、「『押し紙』は1部も存在しない」と主張してきた。もともと提訴の資格を欠くにもかかわらず、書類(催告書)の名義を偽って、裁判を起こした事実もある。
両人とも人権擁護団体、自由人権協会の重鎮である。喜田村氏は、現在の代表理事で、弘中氏も過去に代表理事を務めたことがある。【続きはウェブマガジン】
自由人権協会代表理事の喜田村弁護士らが起こした2件目の裁判、「窃盗」という表現をめぐる攻防③

喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)らが、催告書の名義を「江崎」に偽って著作権裁判を起こしたのは、2008年2月25日だった。その2週間後の3月11日に、喜田村氏らは黒薮に対して2件目の裁判を起こした。メディア黒書の記事が読売と江崎氏ら3人の読売社員の名誉を毀損したとして、2200万円を請求してきたのである。このなかには喜田村氏が受け取る予定の弁護士費用200万円が含まれていた。
訴因は、メディア黒書の記事だった。この年の3月1日に、読売の江崎氏らは、久留米市のYC久留米文化センター前店を、事前の連絡もなく訪店して、対応にでた店主に対し同店との取引中止を宣告した。強制改廃である。その直後に、読売ISの社員が店内にあった折込広告(翌日に配布予定だった)を搬出した。
久留米の別の店主から連絡を受けたわたしは、メディア黒書で速報記事を流した。その記事の中で、折込広告の搬出を「窃盗」と表現した。
◇2200万円の「お金」を要求
喜田村弁護士らは、この「窃盗」に注目して、名誉毀損裁判を起こしたのである。読売関係者は、店主の承諾を得て折込広告を搬出しており、記事は事実とは異なる、それにもかかわらず「窃盗」という事実を摘示したので、名誉毀損に該当するという論法であった。
裁判の舞台は、わたしの地元であるさいたま地裁だった。福岡の江上武幸弁護士ら弁護団が、著作権裁判と同様にこの裁判も無償で支援してくれたので、わたしは弁護士料はもとより、福岡からの交通費も、コピー代も一切負担しなかった。訴訟が原因で文筆業を廃業に追い込まれることもなかった。とはいえ裁判にはかなりの時間を割かれた。海外取材も中止に追い込まれた。
幸いにさいたま地裁は、読売の訴えを棄却した。折込広告の搬出行為は、複数の人の面前で行われており、「窃盗」と表現していても、そのようには解釈されないので、名誉を毀損したことにはならない、などと判断したのである。ただ、「窃盗」という言葉は軽率な表現だという指摘もあった。
ちなみに裁判では争点にはならなかったが、わたしは文章の解釈は、部分的な表現についての評価をするだけではなく、文章全体の意図を把握した上で評価すべきだと考えている。「窃盗」という言葉だけを切り離すと、確かに「他人の所有物を無断で持ち出す」というニュアンスがあるが、日本語のレトリックという観点からすると、隠喩(いんゆ)表現にすぎない。
たとえば、「あの監督は鬼だ」、とか「この国は闇だ」といった表現方法である。この場合、前者は、「あの監督は鬼のように恐い」の意味で、「鬼」という事実を摘示しているわけではない。後者は「この国は闇のように不可解だ」の意味である。これも事実の摘示ではない。わたしは、読売関係者による折込広告の搬出行為を、「窃盗とかわらないほど悪質な持ち去り行為」の意味で使ったのである。
それというのも江崎氏らがいきなり販売店に足を運び、突然に店主に対して強制改廃を宣言し、頭部を鈍器で強打したような強い精神的衝撃を与えた上で、折込広告を搬出したと推測されたからだ。前ぶれもなく家業を奪われた瞬間、当事者には正常な判断力はないというのが、わたしの推測だ。頭は真っ白だったに違いない。
こうした事情を考慮せずに、喜田村弁護士らは、「窃盗」という言葉を捉え、名誉毀損だとして2200万円のお金を支払うように求めてきたのである。キャッシュで払ってほしいのか、銀行振り込みかは不明だが、とにかく高額な金銭を求めてきたのである。
◇天下りの集まり-TMI総合法律事務所
さいたま地裁での敗訴が原因かどうかは不明だが、喜田村弁護士は代理人を辞した。それに代わって読売の代理人になったのは、TMI総合法律事務所のメンバーだった。この法律事務所は、元最高裁判事をはじめ司法関係者の「天下り」を多数受け入れており、裁判の公平性と職業倫理いう観点からすると、問題が多い事務所である。メディア企業・読売がこうした法律事務所に仕事を依頼したことにわたしは驚いた。
しかし、控訴審でも読売は敗訴した。この時点でわたしは、勝訴判決が確定すると思った。最高裁が口頭弁論を開いて、判決の見直しを下級裁判所に指示することは、めったにないからだ。とはいえ心の片隅では不安もあった。なぜか読売が裁判にめっぽう強いからだ。
不安は的中して、最高裁でこの事件の口頭弁論が開かれることになった。わたしの周辺の人々は驚きを隠さなかった。最高裁は、判決を東京高裁へ差し戻した。そして東京高裁の加藤新太郎裁判長が、わたしに110万円の金銭支払いを命じたのである。しかし、このお金も、寄付ですぐに集まった。
加藤判事はその後、勲章を貰って退官。大手弁護士事務所・アンダーソン・毛利・友常法律事務所に顧問として再就職した。
なお、加藤判事が読売新聞に繰り返し登場していたことが、後に判明する。次の記事である。
■読売に登場していた加藤新太郎氏
加藤氏は、読売裁判にはかかわるべきではなかっただろう。
著作権裁判、名誉毀損裁判と喜田村氏らの裁判攻勢は続いたが、最高裁が口答弁論を開くまでは、福岡の弁護団にはまったく歯が立たなかったのである。
真村訴訟でも、やはり敗訴を続けていた。少なくとも10連敗はしている。
その後、さらに2009年7月、読売は黒薮に対して3件目の裁判を起こすことになる。そこで再び現れたのが喜田村弁護士だった。その他に、読売の代理人として藤原家康という名前も訴状にあった。両者とも自由人権協会の関係者である。
自由人権協会とは、何者なのか、わたしは暗い好奇心を刺激されるようになったのである。
喜田村弁護士に対する懲戒請求、第2東京弁護士会の秋山清人弁護士が書いた議決書の誤り②

■ 本稿の前編
喜田村洋一弁護士(自由人権協会)らが起こした黒薮に対する著作権裁判は、すでに述べたように、検証対象になった催告書に著作物性があるかどうかという著作権裁判の肝心な判断以前に、喜田村氏らが催告書の名義を偽って提訴していたとの判断に基づいて、棄却された。
念のために、喜田村氏らが著作物だと主張した文書と、それを削除するように求めた催告書を再掲載しておこう。2つの文書を並べるといかにデタラメかが判然とする。
【喜田村氏らが著作物だと主張した回答書】
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
【メディア黒書から回答書を削除するように求めた催告書】
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
なお、誤解を避けるためにあえて念を押しておくが、喜田村氏らが著作権裁判で削除を求めたのは、後者、つまり催告書の方である。催告書が読売・江崎法務室長の著作物であるから、著作者人格権に基ずいて、メディア黒書から削除するように求めたのである。しかし、東京地裁は著作物性の判断をする以前の問題として、喜田村氏らが催告書の名義を「江崎」と偽って、提訴していたとして、訴えを退けたのである。そもそも訴権などなかったのだ。
ただ、東京地裁は、参考までに、催告書に著作物性があるか否かの判断を示している。そして著作物性はないと判断した。
◇第2東京弁護士会の判断の誤り
さて、喜田村氏らが、提訴権がないのに、催告書の名義を偽ってまで裁判を提起した行為を、どう評価すべきなのだろうか。わたしは司法制度を悪用した悪質な言論妨害と判断して、喜田村氏が所属する第2東京弁護士会に対して、喜田村氏の懲戒を申し立てた。しかし、2年半後に申し立ては棄却された。議決書を書いたのは、秋山清人弁護士である。
決定書を再読してみると、論理の破綻が随所に見受けられるが、そのうち「除斥期間」に関する記述について意見を述べよう。
秋山弁護士は、わたしが期限内(3年)に申し立てを行わなかったから、棄却が妥当だとしているのだが、これは誤っている。
わたしが第2東京弁護士会に懲戒請求を申し立てたのは、2011年1月31日である。一方、江崎法務室長が、問題の催告書を送付したのは、2007年の12月21日である。従って、確かに催告書送付を起点として計算すると3年が過ぎており、審理の対象外になるとも考えうる。
しかし、わたしが懲戒請求の根拠としたのは、弁護士職務基本規定の第75条である。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
喜田村弁護士は、江崎氏が催告書を送付したのを受けて、東京地裁や知財高裁での裁判期間を通じて、「虚偽」の事実を知りながら、裁判所に次々と書面を提出し続けたのである。わたしはこの行為を問題にしているのである。
そして最高裁の判決が確定したのは、2010年である。懲戒請求に踏み切る前年である。この時点で、喜田村弁護士らによる裁判が、虚偽の事実を前提にしていたことが公式に認定され、懲戒請求の要件が整ったのである。
と、すれば懲戒請求の前提となった事実の起点は、判決の確定日である。起点をわざわざ2007年12月21日までさかのぼる理由はないはずだ。それは喜田村氏を救済するための措置だったとしか考えられない。。
このあたりの事情について、秋山弁護士はどのように考えたのだろうか。
第2東京弁護士会の議決を日弁連も追認した。つまり名義を偽って裁判を起こしても、なんら問題ないと判断したのである。これは司法制度に対する軽視にほかならない。自殺行為だ。秋山氏は、軽々しく重要文書を執筆すべきではなかった。文書は記録として残るからだ。当然、今後も検証対象になる。
事件の発生から10年が過ぎ、現役だった関係者の中には、これから定年退職を迎える人々もいるだろう。従って新しい真相究明の道が開けそうだ。
新聞崩壊の時代、検証は11年目に入る。
※決定書の全文は、PDF作業が終わり次第に公開します
喜田村洋一弁護士らによる著作権裁判提起から10年、問題文書の名義を偽って黒薮を提訴、日弁連はおとがめなし①

10年前の2007年12月21日、わたしはメディア黒書(当時は新聞販売黒書)に、一通の催告書を掲載した。読売(西部本社)の江崎徹志法務室長から、わたしに宛てた催告書である。
この催告書は「江崎」の名前で作成されているが、後になって、実は喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が作成していた高い可能性が、東京地裁と知財高裁で認定される。つまり名義を偽った文書だったのである。それがどのような意味を持つのかを説明する前に、まず、事件の全体像を紹介しておこう。
◇公募で新聞販売店主に
事件の発端は、2001年にまでさかのぼる。YC広川を経営していた真村久三氏と読売の係争が前段としてあった。
真村氏は、もともと自動車教習所の教官として働いてきたが、40歳で新聞販売店の経営を始めた。読売が販売店主を公募していることを知り、転職に踏み切ったのである。脱サラして自分で事業を展開してみたいというのが、真村氏のかねてからの希望だった。
幸いに真村氏は店主に採用され、研修を受けたあと、1990年11月からYC広川の経営に乗りだした。ところがそれから約10年後、読売新聞社との係争に巻き込まれる。
その引き金となったのは読売新聞社が打ち出した販売網再編の方針だった。真
村氏は、YC広川の営業区域の一部を隣接するYCへ譲渡する提案を持ちかけられた。しかし、YC広川の営業区域はもともと小さかったので、真村氏はこの提案を受け入れる気にはならなかった。それに自助努力で開業時よりも、読者を大幅に増やしていた事情もあった。
読売の提案を聞いたとき真村氏は、自分で開墾した畑を奪い取られるような危機を感じたのだ。
当然、真村氏は読売の提案を断った。これに対して読売は、真村氏との取引契約を終了する旨を通告した。その結果、裁判に発展したのだ。これが真村訴訟と呼ばれる有名な訴訟の発端だった。
しかし、係争が勃発したころは、単に福岡県の一地方の小さな係争に過ぎなかったのだ。真村氏の代理人・江上武幸弁護士も、読売の実態をあまり知らなかったし、後にこの判決が「押し紙」問題の有名な判例になるとは予想もしていなかった。
真村事件の経緯は膨大なので、ここでは省略するが、結論だけを言えば、裁判は真村氏の勝訴だった。喜田村弁護士が東京からやってきて加勢したが及ばなかった。判決は、2007年12月に最高裁で確定した。
◇真村訴訟
わたしが読売との係争に巻き込まれたのは、真村訴訟の判決が最高裁で確定する数日前だった。真村氏が福岡高裁で勝訴したころから、YC店主が次々と江上弁護士に「押し紙」(残紙)の相談を持ちかけるようになっていたのだが、こうした状況下で、読売も方針を転換したのか、それまで「死に店扱い」にしていたYC広川への訪店を再開することにした。そしてその旨を真村氏に連絡したのである。

しかし、読売に対して不信感を募らせていた真村氏は即答を控え、念のために江上弁護士に相談した。訪店再開が何を意味するのか確認したかったのだ。江上弁護士は、読売の真意を確認するための内容証明郵便を送付した。これに対して、読売の江崎法務室長は、次の書面を送付した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
◇回答書に続いて催告書を公表
わたしは、メディア黒書で係争の新展開を報じ、その裏付けとしてこの回答書を掲載した。何の悪意もなかった。しかし、江崎氏(当時は面識がなかった)はわたしにメールで次の催告書(PDF)を送付してきたのである。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
◇著作権裁判の開始
当然、わたしはメディア黒書から回答文書を削除することを断った。そして今度は、支離滅裂な内容の催告書を、怪文書としてメディア黒書に掲載したのである。こうして回答書も、その削除を求める催告書もネット上で閲覧が可能になったのだ。
読者は、この催告書を作成したのは、誰だと推測するだろうか?おそらく法律の素人と推測するだろう。ところがそれは喜田村弁護士だったのである。少なくとも東京地裁と知財高裁は、後にそういう判断を下すことになる。
さて、回答書が著作物だと強弁する催告書が、ネット上で公になったとすれば、催告書の名義が江崎法務室長になっていることもあり、読売の法務関係者の見識が嘲笑の的になりかねない。それが理由かどうかは不明だが、読売の江崎氏は催告書の削除を求めて、仮処分を申し立てた。喜田村弁護士の名前で、仮処分申立書を東京地裁へ提出したのである。
申立書の内容は、催告書の著作者は江崎氏なので、メディア黒書から催告書を削除するように求めたものだった。東京地裁は、江崎氏の仮処分申し立てを認めた。この命令に納得できなかったわたしは、本裁判を希望した。こうして2008年2月、東京地裁を舞台にして、わたしと江崎氏との著作権裁判が始まったのである。
◇催告書の作成者は喜田村弁護士だった
ところがこの裁判の途中で、前代未聞の疑惑が浮上する。催告書の著作権者は本当に江崎氏なのかという疑惑だった。「たとえ代筆にしろ問題はない」と考える読者も多いかも知れないが、法的に見ればそうではない。江崎氏らは、著作者人格権を根拠に裁判を起こしたからだ。
著作権法は著作者人格権と著作者財産権の2つの権利を保障している。このうち他人に譲渡できる権利は、著作者財産権である。これに対して、作品を公表する権利などを保障した著作者人格権の方は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできない。一身専属権なのである。
既に述べたように江崎氏らは、催告書の作者が江崎氏であり、著作者人格権が江
崎氏にあるという理由で、催告書を削除するように求めて裁判を起こしたのである。従って、催告書が喜田村弁護士の代筆であれば、著作者が江崎氏だという虚偽の事実をでっちあげて、わたしを提訴したことになる。
2009年3月、東京地裁で判決が下った。わたしの勝訴だった。判決は地裁から最高裁までわたしの勝訴だった。裁判所は、催告書が著作物かどうかを判断する以前に、催告書を執筆したのは、江崎氏ではなく、喜田村弁護士である高い可能性を認定し、読売を敗訴させたのだ。知財高裁判決から、核心部分を引用しておこう。
上記の事実認定によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は、原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)である可能性が極めて強い。
つまり催告書の作成者ではない江崎氏は、もともと提訴する権利がないのに、
強引に裁判を起こしたのである。喜田村弁護士も、提訴権がないことを知っていたのに、敢えて代理人を引き受けて、提訴に及んだのである。これが重大な訴権の濫用でないはずがない。こんな事件は、過去に一件もない。
なお、裁判所が喜田村弁護士を代筆者と判断するに至った根拠については判決で述べられているが、たとえば過去にマイニュースジャパンへ送付した喜田村名義の催告書の書式や構成がまったく同じだったことなどが上げられる。やたらに他人に催告書を送付していると、こんな失敗をするのだ。
地裁での勝訴を受けて、わたしの弁護団は、声明を発表した。弁護団は、この事件を「司法制度を利用した言論弾圧」と位置づけている。
判決は次の通りである。
◇弁護士懲戒請求
判決が確定した後、わたしは喜田村弁護士に対して弁護士懲戒請求を申し立てた。懲戒請求の準備書面2を掲載しておこう。事件の性質をコンパクトにまとめている。ただし、申し立ては認められなかった。
読売は、著作権裁判を提起した後、1年半の間に、わたしに対してさらに2件の裁判を提起した。請求総額は、約8000万円となった。(続)
自由人権協会・喜田村洋一代表理事に対する疑問、共謀罪には反対だが、一貫して読売新聞社をサポート、二枚舌の典型

自由人権協会が5月15日付けで共謀罪に反対する声明を出している。声明そのものは、ステレオタイプな内容で特に感想はないが、筆者はある大きな疑問を感じている。
同協会の代表理事を務めている喜田村洋一弁護士が、一貫して読売新聞をサポートしてきた重い事実である。読売新聞は、安倍首相が熟読を勧めた新聞で、改憲論を主導し、共謀罪法案でも旗振り人の役を演じている。公称で約800万部の部数を有し、大きな影響力を持っている。
喜田村氏はその読売新聞をサポートしながら、その一方では共謀罪法案に反対する声明を出しているのだ。
この人物が過去に何をやったのか、筆者は克明に記録してきた。喜田村弁護士が作成した資料(主に裁判関係)も永久保管している。それを基に手短にいくつかの事実を紹介しておこう。
◇2つの真村訴訟
周知のように喜田村弁護士は、ロス疑獄事件の三浦和義被告や薬害エイズ裁判の安倍英被告の代理人弁護人を務めて無罪を勝ち取ったことで有名だ。これらの判決については、様々な意見があるが、弁護士としての職能が優れていることは間違いない。
その職能を生かして読売新聞をサポートしてきたのである。たとえば、福岡県広川町のYC店主が2002年に起こした地位保全裁判-真村訴訟で、読売の代理人を務めた。この裁判は、2007年12月に最高裁で真村店主の勝訴で決着した。
ところがその半年後、読売は別の理由をつけて、一方的に真村店主を解任した。その結果、再び店主は地位保全裁判を提起せざるを得なかったのである。これら一連の動きの中で、喜田村氏が東京から福岡へ何度も出張して、「大活躍」したのである。
この2度目の真村訴訟は仮処分申立てと本訴の2本立てで行われた。最初に判決が出たのは仮処分だった。店主の勝訴だった。裁判所は読売に対して、店主を元の地位に戻すように命令を下した。ところが読売はこの命令に従わなかった。
そのために裁判所は読売に対して、店主へ間接強制金を支払うように命じた。読売はこれには従った。1日に確か3万円だったと記憶している。
しかし、間接強制金の累積が3600円円を超えたころ、本訴で読売が勝訴した。そのために店主は、それまで受け取っていきた間接強制金の返済を求められた。喜田村弁護士らは、確実に返済をさせるために、真村店主の自宅を仮差し押さえたのである。その後、間接強制金の返済を求めて、店主を裁判にかけている。
◇黒薮裁判
真村店主が2度目の地位保全裁判を起こした2008年は、読売が裁判を多発した年である。前年の福岡高裁で同社の「押し紙」政策が認定されており、その影響もあったのではないかと思う。
まず、2月に喜田村氏らは、筆者に対して2件の裁判を起こした。1件は、著作権裁判、もう1件は名誉毀損裁判である。
著作権裁判は筆者の勝訴だった。裁判の中で喜田村弁護士らが、虚偽の事実をでっちあげて裁判を起こしていた高い可能性が認定された。当時の法務室長と共謀したでっち上げだった。
名誉毀損裁判は、地裁、高裁が筆者の勝訴。しかし、最高裁が口頭弁論を開いて、判決を高裁へ差し戻し、高裁の加藤新太郎裁判官が筆者に110万円の支払を命じる判決を下した。その加藤裁判官が、読売新聞の紙面に2度にわたりインタビューで登場していたことが後に判明した。退官後には、勲章をもらい、大手弁護士事務所へ再就職している。
読売は2009年にも筆者に対して裁判を起こした。総括すると、わずか1年半の間に、3件の裁判を起こして、約8000万円を請求したのである。
当然、これら一連の裁判はスラップの典型ではないかという批判が上がった。そのために出版労連が筆者を全面支援してくれた。九州からは、真村訴訟の弁護団が駆けつけて、東京で無償の弁護活動を展開してくれた。
また、筆者は逆に読売に対して、3件の裁判が一連一体の言論弾圧にあたるとして、5500万円の賠償を求める裁判を起こした。喜田村弁護士については、著作権裁判におけるでっち上げを根拠として、弁護士懲戒請求にかけた。しかし、2年半後、日弁連は請求を棄却した。
次の準備書面で事件の本質を的確に指摘している。
◇平山裁判
さらに喜田村弁護士らは、別の事件も起こしている。
筆者が最初の裁判に巻き込まれた時期、「押し紙」を断った久留米市の店主を解任して、地位不存在を確認する裁判を起こした。平山裁判である。
この裁判は店主の平山氏の敗訴で終わった。店主を解任する際、読売は読者調査(新聞の配達先を調べる作業)を行ったのだが、その費用まで店主に請求したのである。
平山氏は裁判の途中で病死された。告別式の出棺時に、中学生の息子さんが肩を小刻みに震わせて泣いていたのが筆者の印象に残っている。裁判の本人尋問の中で、この息子さんが幼少のころ、読売の担当員にからまれている平山氏をみかねて、担当員に「もう帰れ」と怒鳴った証言があった。
その後、裁判は奥さんが引き継がれた。しかし、敗訴して1000万円を超える賠償金を支払わされたのである。
これら一連の読売裁判を担当したのが、喜田村弁護士である。
◇7つの森書館裁判、清武裁判
喜田村弁護士が担当したのは、販売店訴訟だけではない。周知のように、7つの森書館や元読売記者の清武英利氏の裁判でも、読売の代理人を務めている。これらの裁判についても、不当裁判という批判が多い。
犯罪者も含めてすべての人は人権を有しているわけだから、読売を弁護する行為をどう評価するかは難しいが、読売を支援するのであれば、共謀罪に反対する声明など出すべきではない。自由人権協会そのものがまったく訳の分からない団体ということになってしまう。
【写真】喜田村弁護士らが断行した仮差押えの証拠
■真村裁判・黒薮裁判・平山裁判については、拙著『新聞の危機と偽造部数』(花伝社))に詳しい。
読売・喜田村洋一・自由人権協会代表理事らによる口封じ裁判から9年目に、今後も検証は続く

12月21日は、読売新聞社(西部本社)の江崎徹志法務局長がメディア黒書(旧新聞販売黒書)に対して、ある文書の削除を求める仮処分を申し立てた日である。代理人弁護士は、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。2016年の12月21日は対読売裁判が始まって9年目にあたる。
江崎氏の申し立ては、わたしがメディア黒書に掲載した江崎名義の1通の催告書の削除を求めるものだった。しかし、江崎氏は法務室長という立場にあり、実質的には、江崎氏個人ではなく、読売新聞社との係争の始まりである。
事実、その後、読売から3件の裁判、わたしから1件の裁判と弁護士懲戒請求を申し立てる事態となった。
◇真村事件から黒薮裁判へ
この裁判の発端は、福岡県広川町にあるYC広川(読売新聞販売店)と読売の間で起こった改廃(強制廃業)をめぐる事件だった。当時、わたしは真村事件と呼ばれるこの裁判を熱心に取材していた。
係争の経緯については、長くなるので省略するが、2007年の12月に真村氏の勝訴が最高裁で決定した。日本の裁判では、地裁と高裁で連勝すれば、最高裁で判決が覆ることはめったにない。そのために最高裁の判断を待つまでもなく、高裁判決が出た6月ごろから真村氏の勝訴確定は予想されていた。
そのためなのか、読売も真村氏に歩み寄りの姿勢を見せていた。係争になった後、中止していた担当員によるYC広川の訪店を再開する動きがあった。そして江碕氏は、その旨を真村氏に連絡したのである。
しかし、読売に対して不信感を募らせていた真村氏は即答を控え、念のために代理人の江上武幸弁護士に相談した。訪店再開が何を意味するのか確認したかったのだ。江上弁護士は、読売の真意を確かめるために内容証明郵便を送付した。これに対して、読売の江崎法務室長は、次の書面を返信した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、メディア黒書で係争の新展開を報じ、その裏付けとしてこの回答書を掲載した。何の悪意もなかった。むしろ和解に向けた動きを歓迎していた。
しかし、江崎氏(当時は面識がなかった)はわたしにメールで次の催告書(PDF)を送付してきたのである。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
わたしは削除を断った。先に引用した、
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
と、いう回答書は著作物ではないからだ。催告書の形式はともかく、書かれた内容自体はまったくのデタラメだった。著作権法によると、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」。上記の回答書は、著作物ではない。催告書の内容そのものが間違っている。
そこで、今度はこの催告書をメディアで公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権に基づいて、削除するように求めてきたのである。
そして喜田村弁護士を立てて、催告書の削除を求め、仮処分を申し立てたのである。(回答書の削除は求めてこなかった。)
こうして江崎氏名義の催告書が、著作物かどうかが争点となる係争が始まったのだ。書かれた内容の評価とは別に、催告書が著作物かどうかという点に関しては、一応は議論の余地があった。書かれている内容そのものがデタラメであっても、それに著作物性があるかどうかは、別問題である。
結論を先に言えば、仮処分申立は、江崎氏の勝訴だった。催告書が著作物と認めれらたのだ。
判決に不服だったわたしは、本訴に踏み切った。代理人は江上弁護士ら、真村裁判の弁護団が無償で引き受けてくれた。わたしは東京・福岡間の交通費もふくめて、1円の請求も受けなかった。
◇重大な疑惑の浮上
本訴の中で重大な疑惑が浮上した。
既に述べたように、この裁判は、江崎氏が書いたとされる奇妙な内容(例の回答書が著作物であるという内容)の催告書が争点だった。内容が奇妙でも催告書が江崎氏の著作物であると認定されれば、わたしは削除に応じなければならない。
仮処分では負けたわたしだが、裁判の途中から様相が変わってきた。特に江崎本人尋問を機に流れが変わった。
確かに催告書の名義は江崎氏になっているが、催告書は喜田村弁護士が作成したものではないかという疑惑が浮上してきたのだ。
著作者の権利は、著作権法では、「著作者人格権(公表権などが含まれる)」と「著作者財産権」に別れるのだが、前者は他人に譲渡することができない。一身専属権である。
江崎氏は、著作者人格権を根拠に、わたしを提訴したのである。と、なれば江碕氏が催告書の作者であることが、提訴権を行使できる大前提になる。仮に他人が書いたものなら、それはたとえば、わたしが村上春樹氏の作品を自分のものだと偽って、著作者人格権による権利を求める裁判を起こすのと同じ原理である。
催告書の本当の作成者が喜田村弁護士だとすれば、喜田村氏らは催告書の名義を「江碕」偽り、それを前提にして、著作者人格権を主張する裁判を起こしたことになる。
◇東京地裁・知財高裁の判決
東京地裁は、わたしの弁護団の主張を全面的に認めて、江崎氏の訴えを退けた。喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフが催告書の本当の作者である可能性が極めて強いと認定したのである。
このあたりの事情については、地裁判決直後の弁護団声明を参考にしてほしい。弁護団は、この事件を「司法制度を利用した言論弾圧」と位置づけている。
次の引用するのは、知財高裁判決の重要部分である。催告書の名義人偽り疑惑について、次のように言及している。
上記の事実認定によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は、原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)である可能性が極めて強い。
繰り返しになるが、江崎氏は、元々、著作者人格権を主張する権利がないのに、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴し、それを主張したのである。
喜田村弁護士は、自分の行為が弁護士としてあるまじき行為であることを自覚していたはずだ。弁護士職務基本規定の第75条は、次のようにこのような行為を禁止している。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
ところが名義を偽った催告書を前提にして、裁判所へ資料を提出し、自己主張を展開したのだ。
裁判が終わった後、今度はわたしの方が攻勢に転じた。喜田村弁護士が所属する第2東京弁護士会に対して、喜田村弁護士の懲戒請求を申し立てた。2年後に、申し立ては却下されたが、多くの法律家が前代未聞のケースだとの感想を寄せた。弁護士会の判断は誤りだと話している。現在、再審を検討している。
曖昧な決着はしないのが、わたしの方針だ。
参考までに、懲戒請求の中身を次の書面で紹介しておこう。
今後も検証は続く。
喜田村洋一弁護士が作成したとされる催告書に見る訴権の濫用、読売・江崎法務室長による著作権裁判8周年①
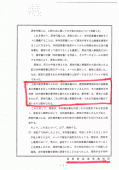 2008年2月25日に読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、東京地方裁判所にわたしを提訴してから、今年で8年になる。この裁判は、わたしが「新聞販売黒書」(現MEDIA KOKUSYO)に掲載した江崎氏名義のある催告書の削除を求めて起こされた著作権裁判だった。
2008年2月25日に読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、東京地方裁判所にわたしを提訴してから、今年で8年になる。この裁判は、わたしが「新聞販売黒書」(現MEDIA KOKUSYO)に掲載した江崎氏名義のある催告書の削除を求めて起こされた著作権裁判だった。
その後、読売はわずか1年半の間にわたしに対して、さらに2件の裁判を起こし、これに対抗してわたしの方も読売に対して、立て続けの提訴により「一連一体の言論弾圧」を受けたとして、約5500万円の損害賠償を求める裁判を起こしたのである。さらにこれらの係争に加え、読売の代理人・喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する懲戒請求を申し立てたのである。
喜田村氏は4件の裁判のいずれにもかかわった。
提訴8周年をむかえる著作権裁判は、対読売裁判の最初のラウンドだった。
読売・江崎氏の代理人には、喜田村弁護士が就任した。一方、わたしの代理人は、江上武幸弁護士ら9名が就いた。
しかし、この裁判の発端は、福岡県広川町にあるYC広川(読売新聞販売店)と読売の間で起こった改廃(強制廃業)をめぐる事件だった。当時、「押し紙」問題を取材していたわたしは、真村事件と呼ばれるこの係争を取材していた。
◇公募で新聞販売店主に
YC広川の店主・真村久三氏は、もともと自動車教習所の教官として働いてきたが、40歳で新聞販売店の経営を始めた。読売が販売店主を公募していることを知り、転職に踏み切ったのである。脱サラして自分で事業を展開してみたいというのが、真村氏のかねてからの希望だった。
幸いに真村氏は店主に採用され、研修を受けたあと、YC広川の経営に乗りだした。1990年11月の事だった。ところがそれから約10年後、読売新聞社との激しい係争に巻き込まれる。
その引き金となったのは読売新聞社が打ち出した販売網再編の方針だった。真村氏は、YC広川の営業区域の一部を隣接するYCへ譲渡する提案を持ちかけられたのだ。が、YC広川の営業区域はもともと小さかったので、真村氏は譲渡案を受け入れる気にはならなかった。それに自助努力で開業時よりも、読者を大幅に増やしていた。
読売の提案を聞いたとき真村氏は、自分で開墾した畑を奪い取られるような危機を感じたのだ。
当然、読売の提案を断った。これに対して読売は、真村氏との取引契約を終了する旨を通告した。その結果、裁判に発展したのだ。これが真村訴訟と呼ばれる有名な訴訟の発端だった。が、係争が勃発したころは、単に福岡県の一地方の小さな係争に過ぎなかったのだ。江上弁護士も、読売の実態をあまり知らなかったし、後にこの判決が「押し紙」問題の有名な判例になるとは予想もしていなかった。
真村事件の経緯は膨大なので、ここでは省略するが、結論だけを言えば、裁判は真村氏の勝訴だった。喜田村弁護士が東京からやってきて加勢したが及ばなかった。判決は、2007年12月に最高裁で確定した。
◇真村訴訟
わたしが読売との係争に巻き込まれたのは、真村訴訟の判決が最高裁で確定する数日前だった。真村氏が福岡高裁で勝訴したころから、YC店主が次々と江上弁護士に「押し紙」(残紙)の相談を持ちかけるようになった。店主のあいだで新しい店主会-新読売会を立ち上げる動きもあった。
こうした状況下で、読売も方針を転換したのか、それまで「死に店扱い」にして、訪店を控えていたYC広川への訪店を再開することにした。そしてその旨を真村氏に連絡した。
しかし、読売に対して不信感を募らせていた真村氏は即答を控え、念のために江上弁護士に相談した。訪店再開が何を意味するのか確認したかったのだ。江上弁護士は、読売の真意を確認するための内容証明郵便を送付した。これに対して、読売の江崎法務室長は、次の書面を送付した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、新聞販売黒書で係争の新展開を報じ、その裏付けとしてこの回答書を掲載した。何の悪意もなかった。しかし、江崎氏(当時は面識がなかった)はわたしにメールで次の催告書(PDF)を送付してきた。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
わたしは、今度はこの催告書を新聞販売黒書で公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権に基づいて、削除するように求めてきたのである。
が、催告書の作者は別にいたのだ。東京地裁と知財高裁は、喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフが本当の作者である可能性が極めて強いと認定して、江崎氏の訴えを退けたのだ。
彼らは催告書の名義人を「江崎」に偽って提訴し、法廷で著作者人格権を主張したのだ。もともと提訴権がないのに、虚偽の事実を前提に裁判を起こしたのである。
このあたりの事情については、弁護団声明を参考にしてほしい。弁護団は、この事件を「司法制度を利用した言論弾圧」と位置づけている。
◇怪文書・恫喝文書
さて、提訴8周年にあたる今年は、喜田村弁護士が執筆したとされる「江崎名義」の催告書の内容を検証しよう。著作権裁判では、とかく文章の形式が検証対象になり、書かれた内容には重きがおかれない傾向があるが、ジャーナリズムでは、書かれた内容そのものを検証する。
結論を先に言えば、これは怪文書である。あるいは恫喝文。しかも、それが自由人権協会の代表理事によって作成されたのだ。
繰り返しになるが、この催告書の作者は、催告書の中で、江崎氏が江上弁護士に送付した書面を新聞販売黒書から削除するように求めてきたのである。その送付された書面を再度引用してみよう。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
つまり催告書は、上に引用した書面が江崎氏の著作物なので削除するように求めているのだ。そしてそれに従わない場合は、民事訴訟か刑事訴訟も辞さない旨をほのめかしているのだ。
著作権法の知識に乏しいわたしは、著作権法でいう「著作物」の定義を調べてみた。すると次のような記述があった。
一 、著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
江崎氏が江上弁護士に送付した書面は、どの角度から見ても、著作物ではない。念のために複数の専門家に問い合わせみたが、この書面が著作物だとする人はひとりもいなかった。
それにもかかわらず催告書は、江上弁護士へ送られた書面は江崎氏の著作物なので、それを削除しなければ、民事訴訟か刑事訴訟も辞さない旨を述べているのだ。わたしは、この文書を怪文書・恫喝文書としか評価できなかった。それゆえにそれを新聞販売黒書に載せたのだ。読売の法務室長が奇妙な文書を送ってきたという思いで。これ自体が大きなニュースだった。
◇喜田村弁護士が言及した著作物の定義
その後、わたしは著作物に関する喜田村弁護士の言動を注視するようになった。と、2013年の5月になって宝島社から『佐野真一が殺したジャーナリズム』という本が出版された。この本に、喜田村弁護士が「法律家がみた『佐野眞一盗用問題』の深刻さ」と題する一文を寄せた。
その中ではからずも喜田村氏が著作物の定義に言及していることが分かった。取材の協力者のひとりが情報を寄せてくれたのだ。同書の中で、喜田村弁護士は「著作物」について、次のように記している。
(略)まず、著作物は「表現」でなければならないから、「思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など」で、表現でないものは、著作物になりえない。
たとえば、「○月○日、△△で、AがBに~と言った(AがBを手で殴りけがをさせた)」いうような事実ないし事件そのものは、表現ではないから、著作権法の対象ではない。同様に、「ある事件についての見方」とか、「ある事件を報じるにあたっての方法」といったアイデアに属するものも、表現ではないから、著作権法の保護は受けられない。
また、創作性がなければならないから、ごく短い文章で、誰が書いても同じようになるようなものであれば、これも著作物ではない。(略)
裁判所は、催告書の作者が喜田村弁護士である高い可能性を認定したが、たとえ作者が名義人の江崎氏であっても、代理人弁護士の喜田村氏が、催告書の内容を確認していないはずがない。読めば、内容それ自体がデタラメであることが分かったはずだ。なぜ、訴訟を思いとどまらせなかったのだろうか。なぜ、催告書の内容が間違っていることを指摘しなかったのだろうか。
これが訴権の濫用でなくして何だろうか?
著作権裁判の検証は、これから9年目に入る。
やしきさくら氏の代理人に、喜田村洋一・自由人権協会代表理事、曖昧な名誉毀損の賠償額、300万円もあれば10万円も

名誉毀損裁判で敗訴した場合の損害賠償額が、かつてに比べて高額化している。その一方で極めて低額な賠償命令も下っている。わたしの知るケースでは、前者が300万円で、後者が10万円である。
たとえば『スポーツ報知』(2015年10月28日)は、やしきたかじん氏の妻・やしきさくら氏が、たかじん氏の元弟子を提訴した裁判で、大阪地裁が300万円の支払いを命じたことを伝えている。
昨年1月に亡くなった歌手でタレントのやしきたかじんさんの妻、さくらさんが、たかじんさんの元弟子・打越元久氏(57)に名誉を傷つけられたとして、1000万円の慰謝料を求めた訴訟で大阪地裁は28日、打越氏に300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
訴えによると、打越氏は昨年11月、インターネットラジオの番組に出演し、作家・百田尚樹氏(59)がたかじんさんの闘病生活を描いた「殉愛」の内容が真実ではないと指摘。遺産相続などをめぐって事実とは異なる発言をしたと主張していた。
ちなみに作家・百田尚樹氏(59)が出版した『殉愛』(幻冬舎)に対する意見や評論などに対して、出版社などが入り乱れて複数の裁判が起きている。
このうち、さくら氏は、300万円の判決が下った上記の裁判の他に、フリーランスライターを訴えている。この裁判では、喜田村洋一・自由人権協会理事が、さくら氏の代理人を務めている。
喜田村弁護士は、薬害エイズ事件で起訴された安部英氏やロス疑惑事件の三浦和義氏を断罪から救済した手腕を持つ。「押し紙」に関しては、読売には1部も存在しないと主張し、それを司法認定させた。
■「押し紙」回収の現場(隠し撮り)-画像は本文とは関係ありません。
◇著作権裁判で前代未聞の判例
しかし、わたしとの著作権裁判では、門前払いのかたちで敗訴した。この裁判では、虚偽を前提に提訴に及んでいたことが認定された。争点となった文書の作成者が、その文書の名義人本人ではく、喜田村氏であった高い可能性が認定されたのである。裁判史上でも珍しい判例だ。
わたしは同氏を懲戒請求したが、日弁連はそれを認めず、喜田村氏は現在も活動を続けている。
■自由人権協会:日本を代表する護憲派の人権擁護団体。サラ金の武富士の代理人を務めた弘中惇一郎弁護士ら、名誉毀損裁判にかかわっている弁護士が多い。(詳細)
さくら氏が起こした裁判で300万円の賠償が下った判例のほかにも、わたしがこのところ取材している事件で2件も300万円の賠償を命じた判例がある。法人に対する賠償であればともかくも、個人に対する賠償額としては、尋常ではない。
◇「統合失調症」という表現
その一方、メディア黒書でたびたび紹介してきた市民運動家で最高裁事務総局の不可解さを厳しく追及している志岐武彦氏が、歌手で作家の八木啓代氏を訴えた裁判では、敗訴した八木氏に対する賠償命令の額はたったの10万円だった。
■(参考)歌手で作家・八木啓代氏のツィートを裁判所はどう判断したのか、裁判所作成の評価一覧を公開
この判決で示された基準からすれば、ネット上で投稿者がある人物を統合失調症であるというまったく事実とは異なる評価をツィートしても名誉毀損とは認定されないことになる。
名誉毀損裁判では、「一般読者の普通の注意と読み方を基準として」、それが社会的地位を低下させたかどうかを判断する。おそらく裁判官は、ツィッターで相手を統合失調症と評しても、それを本気で信じ込むひとはいないと判断したのではないか。その意味では、裁判にありがちな机上の思考ではない。
◇読売が約8000万円のお金を請求
わたし自身は、2008年から2009年にかけて、読売新聞社からたて続けに3件の裁判を起こされた。請求額は約8000万円。このうち2件目の裁判は、メディア黒書の記事が名誉毀損に問われた。請求額は2230万円。読売代理人は、地裁では喜田村洋一・自由人権協会代表理事で、高裁からはTMI総合法律事務所の升本喜郎弁護士らだった。
一方、わたしの代理人は、江上武幸弁護士ら9名だった。無報酬の弁護活動だった。
結果は、さいたま地裁と東京高裁はわたしの勝訴だったが、最高裁が口頭弁論を開いて、判決を東京高裁へ差し戻した。そして東京高裁の加藤新太朗裁判長は、わたしに対して110万円の金銭支払いを命じた。後に加藤氏が、読売新聞に少なくとも2度、単独インタビューで登場していたことが判明した。
この裁判は、最高裁でわざわざ口頭弁論を開いて、読売を逆転勝訴させるほどの事件なのか、今も再考しているが、とにかくわたしが敗訴したのである。野球でいえば、甲子園の決勝で9回の裏、読売に逆転されて負けたのだ。
◇曖昧な日本の名誉毀損裁判
今、ここにあげた何件かの裁判を見る限り、わたしは日本の名誉毀損裁判の判断基準がどこにあるのか分からない。名誉毀損裁判では、「一般読者の普通の注意と読み方を基準」にすることになっているが、判決の結果はばらばらだ。一貫性がない。
たとえばツィッターやフェイスブックをやっている裁判官であれば、これらのメディアの言語は比較的自由で、相手に向かって「統失」(八木裁判)と書こうが、「人格障害」(やしきさくら氏の裁判)と書こうが、本気でそれを信じ込む人は、まず、一人もいないことを知っている。それが社会通念である。
判断基準が曖昧になっているということは、裁判官の気分ひとつで、どうにでも判決を書けることになる。このような司法運用の実態は、裁判を言論抑圧の道具に変質させる危険性を孕んでいる。
このところ日本は、言論活動を抑圧する方向へ進んでいる。そのことは、特定秘密保護法を含む、広義の戦争法案が成立した流れの中に顕著に見ることが出来るが、これに連動して名誉毀損裁判の賠償額が高額化している事実は、言論を統制しようとしている内閣の方針に、最高裁事務総局も追随していることを意味しないだろうか。「一般読者の普通の注意と読み方」という基準は極めて主観的で「凶器」に変わりやすい。危険な兆候だ。
とはいえ、日弁連はようやく、名誉毀損裁判やスラップを問題視し始めたようだ。
読売・江崎法務室長による著作権裁判、「戦後処理」係争開始から8年、事件と喜田村弁護士に対する懲戒請求を再検証する

読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、喜田村洋一・自由人権協会代表理事を代理人として、わたしに対して著作権裁判を起こして8年が過ぎた。「戦後検証」は、係争の発端から8年目に入る。2007年12月21日、江崎氏はEメールでわたしに対してある催告書を送りつけてきた。(判決文、弁護士懲戒請求・準備書面のダウンロード可)
◇新聞販売黒書に掲載した2つの書面
発端は福岡県広川町で起こった読売新聞社とYC広川(読売新聞販売店)の間で起こった強制廃業をめぐるトラブルだった。当時、新聞販売の問題を取材していたわたしは、この事件を取材していた。
幸いに係争は解決のめどがたち、2007年の末に読売はそれまで中止していたYC広川に対する担当員の定期訪問を再開することを決めた。しかし、読売に対する不信感を募らせていたYC広川の真村店主は、読売の申し入れを受け入れるまえに、念のために顧問弁護士から、読売の真意を確かめてもらうことにした。
そこで代理人の江上武幸弁護士が書面で読売に真意を問い合わせた。これに対して、読売は江崎法務室長の名前で次の回答書を送付した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、新聞販売黒書でこの回答書を紹介した。すると即刻に江崎氏(当時は面識がなかった)からメールに添付した次の催告書が送られてきたのである。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。
貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
回答書が自分の著作物なので削除するように求めているのだ。(回答書の著作物性については後述する)
わたしは、回答書の削除を断り、逆に今度はこの催告書を新聞販売黒書(現在のメディア黒書)で公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権(注:後述)に基づいて、削除するように求めてきたのである。
が、催告書の作者は江崎氏ではなく、代筆者がいたのだ。少なくとも、後日、裁判所はそう判断したのだ。
◇喜田村洋一・自由人権協会代表理事が登場
わたしは催告書を削除するように求める江崎氏の申し出を断った。その結果、江崎氏は仮処分を申し立ててきた。ここで江崎氏の代理人として登場したのが、名誉毀損裁判や著作権裁判のスペシャリスト、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。
仮処分は代理人なしに臨み、わたしの敗訴だった。そこで本訴になったのである。わたしの代理人には、江上弁護士ら福岡の販売店訴訟弁護団がついた。
著作権裁判では、通常、争点の文書、この裁判の場合は江崎氏の催告書が著作物か否かが争われる。著作物とは、著作権法によると、次の定義にあてはまるものを言う。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
改めて言うまでもなく、争点の文書が著作物に該当しなければ、著作権法は適用されない。
わたしの裁判でも例外にもれず、争点の催告書が著作物か否かが争われた。催告書の著作物性を争った裁判は、日本の裁判史上で初めてではないかと思う。ちなみに、新聞販売黒書に掲載した肝心の回答書の方は、争点にならなかった。
◇意外な決着
裁判は意外なかたちで決着する。裁判所は、「江崎名義」の催告書の著作物性を判断する以前に、そもそも江崎氏が催告書の作成者ではないと判断したのである。つまりもともと江崎氏には著作者人格権を根拠とした「提訴権」がないにもかかわらず、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴に及んでいたと判断したのである。
なぜ、裁判所はこのような判断をしたのだろうか。詳細は判決に明記されているが、ひとつだけその理由を紹介しておこう。催告書の書式や文体を検証したところ、喜田村弁護士がたまたま「喜田村名義」で他社に送っていた催告書とわたし宛ての催告書の形式がそっくりであることが判明したのだ。同一人物が執筆したと判断するのが、自然だった。
つまり催告書を執筆していたのは喜田村弁護士だった。それにもかかわらず江崎氏は、自分が著作権者であることを主張したのだ。認められるはずがなかった。そもそも提訴権すらなかったのだ。
当然、江崎氏は門前払いのかたちで敗訴した。東京高裁でも、最高裁でも抗弁は認められず、江崎氏の敗訴が確定した。
◇だれが作者なのかという問題
おそらく読者の大半は、著作権という言葉を聞いたことがあるだろう。文芸作品などを創作した人が有する作品に関する権利である。その著作権は、大きく著作者財産権と著作者人格権に分類されている。
このうち著作者財産権は、作品から発生する財産の権利を規定するものである。たとえば作者が印税を受け取る権利である。この権利は第3者にも譲渡することができる。
これに対して、著作者人格権は、作者だけが有する特権を規定したものである。たとえば未発表の文芸作品を公にするか否かを作者が自分で決める権利である。第3者が勝手に公表することは、著作者人格権により禁じられている。
著作者人格権は、著作者財産権のように他人に譲渡することはできない。「一身専属」の権利である。
代理人は、既に述べたように、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。
裁判所は判決の中で、催告書を執筆したのは喜田村弁護士か彼の事務所スタッフであった高い可能性を認定した。
◇弁護士懲戒請求
弁護士職務基本規程の第75条は、次のように言う。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
喜田村弁護士は、問題になった「江崎名義」の催告書をみずから執筆していながら、江崎氏が書いたという前提で裁判の準備書面などを作成し、それを裁判所に提出し、法廷で自論を展開したのである。
当然、弁護士職務基本規程の第75条に抵触し、懲戒請求の対象になる。わたしが懲戒請求に踏み切ったゆえんである。
◇弁護士倫理の問題
なお、裁判の争点にはならかなったが、喜田村弁護士に対する懲戒請求申立ての中で、わたしが争点にしているもうひとつの問題がある。ほかならぬ催告書に書かれた内容そのものの奇抜性である。
著作権裁判では、とかく催告書の形式ばかりに視点が向きがちだが、書かれた内容によく注意すると、かなり突飛な内容であることが分かる。怪文書とも、恫喝文書とも読める。端的に言えば内容は、江崎氏がわたしに送付した回答書が江崎氏の著作物なので、削除しろ、削除しなければ、刑事告訴も辞さないとほのめかしているのだ。
回答書は、本当に著作権法でいう著作物なのだろうか?再度、回答書と著作権法の定義を引用してみよう。
【回答書】 前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
【著作物の定義】 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
誰が判断しても、著作物ではない。しかも、この内容の催告書を書いたのは、著作権法の権威である喜田村弁護士である。回答書が著作物ではないことを知りながら、催告書には著作物だと書いたのだ。
弁護士として倫理上、こうした行為が許されるのか疑問がある。が、日弁連はこの懲戒請求を喜田村弁護士を調査することなく却下した。
わたしは今でも、この判断は間違っていると考えている。
