【書評】ドライサー著『シスター・キャリー』、米国資本主義の悲劇
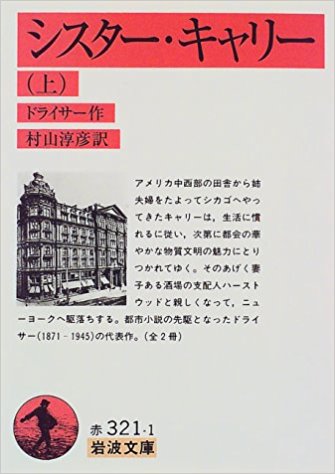
海外の違った文化圏に定住して、改めて外部から日本を観察してみると、それまで見えなかった社会の断面が輪郭を現すことがある。それと同じ思考方法を小説が提供してくれる場合がある。しかも、後者の方は、時代の壁を軽々と飛び越えて、ひとつの時代、ひとつの社会を客観視させてくれる。
1990年に米国の作家・ドライサーが発表した『シスター・キャリー』(岩波文庫)は、米国資本主義が内包していた理不尽な構図を描いている。ドライサーの代表作『アメリカの悲劇』に劣らない名作である。
田舎町からシカゴへ出てきた娘・キャリーは、妻子もちの男とニューヨークへ駆け落ちする。しかし、男は事業に失敗。どんぞこへと落ちぶれていく。これに対して、キャリーは演劇の才能を認められ、アメリカンドリームを象徴するような出世の階段を昇る。女優として成功したのだ。
やがて経済的な格差が原因で2人の関係は破綻する。
男は生活もままならなくなり、鉄道労働者のストライキが勃発すると、鉄道会社に雇われて機関士となる。スト破りに協力したのである。が、それもつかの間のことで、一文無しのホームレスーになる。
こうした弱肉強食の社会の中で、唯一の救いの手は、キリスト教の慈善運動によって差し伸べられる。下層階級に落ちぶれてしまうと、それに頼る以外に生きる道は閉ざされているのだ。
幸運と才能さえあれば巨額の富に手にできる一方で、アメリカンドリームに失敗すれば、社会の底辺に突き落とされる。公的な支援はなにもない。人間の良心だけが、わずかな救済になる社会。それが1990年代の米国資本主義だったのである。
男は、最後に自殺して共同墓地に埋葬される。
この小説は、プロレタリア文学ではないが、スト破りの実態がかなり克明に描かれている。ドライサーの先見性を物語っている。当時としては、極めて珍しい視点だったのではないか。
タイトル: シスター・キャリー
版元:岩波書店
著者:セオドア・ドライサー(村山淳彦訳)
