読売新聞押し紙訴訟 福岡高裁判決のご報告 ‐モラル崩壊の元凶「押し紙」‐
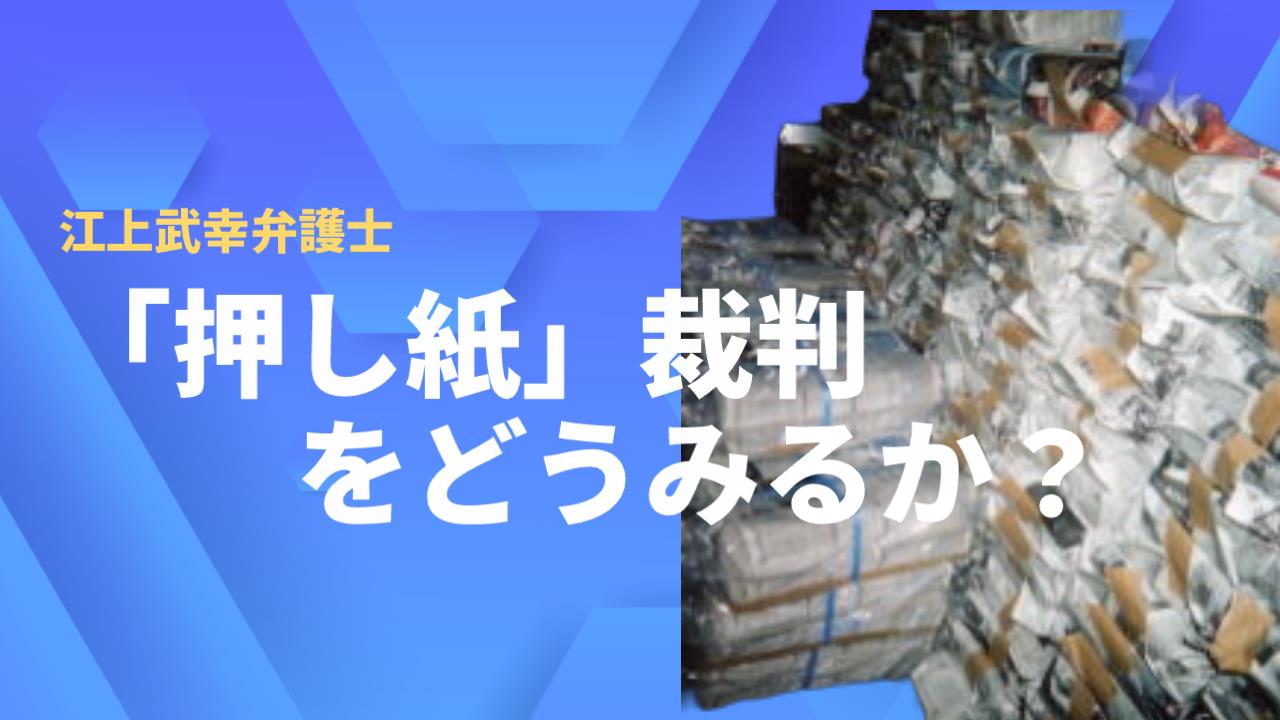
福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)
2024(令和6年)5月1日
長崎県佐世保市の元読売新聞販売店経営者が、読売新聞西部本社に対し、押し紙の仕入代金1億5487万円(控訴審では、金7722万に請求を減縮)の損害賠償を求めた裁判で、4月19日、福岡高裁は控訴棄却の判決を言い渡しました。
* なお、大阪高裁判決の報告は、2024年4月13日(土)付「押し紙の実態」に掲載されていますのでご一読ください。
「バブル崩壊の過程で、私たちは名だたる大企業が市場から撤退を迫られたケースを何度も目の当りにしました。こうした崩壊劇にはひとつの共通点があります。最初はいつも小さな嘘から始まります。しかし、その嘘を隠すためにより大きな嘘が必要になり、最後は組織全体が嘘の拡大再生機関となってしまう。そして、ついに法権力、あるいは市場のルール、なによりも消費者の手によって退場を迫られるのです。社会正義を標榜する新聞産業には、大きな嘘に発展しかねない『小さな嘘』があるのか。それともすでに取り返しのつかない『大きな嘘』になってしまったのでしょうか・・・・。」(新潮新書2007年刊・毎日新聞元常務河内孝著「新聞社破綻したビジネスモデル」の「まえがき」より)。
大阪高裁と福岡高裁の判決をみると、裁判所は平成11年の新聞特殊指定の改定(1999年)を機に、押し紙については黙認から積極的容認に姿勢を転じたように見受けられます。
 今回の福岡高裁判決の「当裁判所の判断」部分は、わずか2頁にすぎません。しかし、頁数が極端に少ないため、かえって裁判所の押し紙問題についての基本的立ち位置や考え方がわかりやすくなっています。以下、とりあえず福岡高裁判決を読んだ感想を述べさせていただきます。
今回の福岡高裁判決の「当裁判所の判断」部分は、わずか2頁にすぎません。しかし、頁数が極端に少ないため、かえって裁判所の押し紙問題についての基本的立ち位置や考え方がわかりやすくなっています。以下、とりあえず福岡高裁判決を読んだ感想を述べさせていただきます。
新聞社の社会的影響力と広告媒体力は発行部数によって決まります。新聞社は、発行部数を大きくするために、優越的地位を背景にして販売店に対し実配数を超過する新聞(以下、「押し紙」といいます。)を仕入させようとします。販売店は新聞社の意向に逆らうことが出来ませんので、押し紙を引き受けざるを得ません。新聞社にとって、押し紙は販売店への売上増に直結しており、紙面広告単価を高く設定することができ、社会的影響力も大きくできるという一石三鳥のメリットがあります。しかし、販売店にとっては、廃棄するか無代紙・サービス紙として無償配布するかしかない無駄な新聞です。
そのため、新聞社は販売店に押し紙を仕入れさせるために、押し紙にも折込広告収入が得られるようにしたり、不足分は補助金を支出するなどの施策を講じています。このような押し紙を中核に据えた新聞経営のことが「新聞社のビジネスモデル」と呼ばれるものです。
読売新聞1000万部・朝日新聞800万部・毎日新聞300万部といわれた時代がありましたが、その内、実際に配達される新聞がいかほどあるかについては公表されていません。表向きは販売店の実配数を新聞社が知らないことにされていますが、実際は、大量の押し紙が含まれていることを世間に知られないようにするための嘘です。小さな嘘ではなくとてつもなく大きな嘘です。
これまで、日本新聞販売協会・公正取引委員会・ABC協会などの公的組織によって押し紙の調査が為されたことがありますが、正確な部数や割合は不明なままでした。その後、押し紙訴訟や折込広告料返還訴訟が提起されるようになり、本ブログの主催者である黒薮哲哉さんのもとに販売店経営者から多くの内部資料が寄せられるようになったことから、次第に押し紙の部数や割合が明らかになってきました〔黒薮哲哉著・「新聞と公権力の暗部-押し紙問題とメディアコントロール-」(鹿砦社刊)参照)〕。
* ネットで「押し紙」を検索していただければ、大量の新聞や折込チラシが古紙回収業者のトラックに積み込まれている現場の様子を見ることができます。
押し紙は、1955年(昭和30年)の独占禁止法新聞特殊指定の制定によって禁止されるようになり、1964年(昭和39年)と1999年(平成11年)の二度の改正を経て現在に至っています。新聞の発行部数は、人口の高齢化と少子化・景気の悪化・ネット社会の普及などの様々な要因で、2000年(平成12年)の5370万部から23年後の2023年(令和5年)には2860万部と約半分近くまで減少しています。このままでいけば、10数年後には発行部数がゼロになるような減少スピードです。
元朝日新聞東京本社販売局管理部長の畑尾一知氏は「新聞社崩壊」(新潮新書・2018年(平成30年)発行)に、「今の新聞社は薄氷の上を渡るソリのようである。ソリの水没は避けられないものだろうか。」との現状認識を示した上で、「紙の新聞には今でも数十パーセントの支持率があり、今は年々減っているとはいえ、新聞自体が生まれかわれば過去の支持者が戻ってくるはずである。新聞社は亡んでも新聞は生き残り得る。」との希望的観測を述べていますが、果たして新聞は生き残ることが可能でしょうか。大いに疑問です。
畑尾氏は、「権力側にとって不都合な情報を公開されたくないのは、ごく自然なことである。情報の公開度は大衆の支持を背景にジャーナリズムがどれだけ頑張るかにかかっている。パリに本部を置く『国境なき記者団』の報道の自由度ランキングの2016年(平成28年)の日本のランキングは72位だった。年々ランクを下げ先進諸国の中では最低に位置している。第二次安倍政権(注:2012年(平成24年)12月~2020年(令和2年)9月まで)になってからは、政権基盤の強化がますます進むのに対し、新聞やテレビは購読者・視聴者が減っていくに連れて、弱体化が顕著になっている。不都合な事実を隠したい権力側の圧力はますます強くなっていくだろう。」と書いています。
また、「2014年(平成26年)に神戸新聞が兵庫県議会議員の政務活動費不正使用問題を発掘し報道したのがきっかけで、各新聞社が全国の地方議会における議員の政務活動費の使途について調査し、多くの不正が発覚した。」との記載もありました。この箇所を読んでいて、新聞は、国会議員の裏金問題については、何故、目を向けなかったのだろうか、何故、調査しなかったのだろうかという疑問にとらわれました。
黒薮さんのブログに、2006年(平成18年)の参議院予算委員会で、当時の安部晋三国務大臣が押し紙問題について国会答弁をしていることが紹介されており、安倍氏が新聞社の押し紙問題を新聞経営陣の取り込みに利用したのではないかと考えるようになりました。
また、安倍内閣発足以降、自民党政権がテレビの報道番組に次々と圧力を加えるようになり、政権批判の有力なコメンテーターが次々と番組から降板していきましたが、その背後にもテレビ局の親会社である新聞社の押し紙問題が隠されていたのではないかとの疑念をもつようになりました。
 黒薮さんは、1999年(平成11年)の新聞特殊指定が改訂された年に、特に着目したいと述べられております。今後の調査および報道に期待しているところです。
黒薮さんは、1999年(平成11年)の新聞特殊指定が改訂された年に、特に着目したいと述べられております。今後の調査および報道に期待しているところです。
冒頭に紹介した毎日新聞元常務の河内孝氏の著書に、1981~82年(昭和56~7年)当時、読売新聞の巌専務取締役販売局長だった丸山巌氏(渡邉恒雄氏と次期読売社長のライバル候補と目された良識ある方です。)の、「本社(読売新聞社)が販売店に送りつける押し紙で、配達もされずに梱包のまま残紙屋に回収される残紙が、なんと年間300億円にもなる。こんな無駄が許されるわけがない」との発言と、朝日新聞の販売担当常務取締役の古屋哲夫氏の、「内部努力ではもうだめ。公権力が入ってこざるを得ない。そこまで販売乱戦の危機は深刻化している。これが最後のチャンス」との発言が記載されています。
この時期に、両氏のような良識ある大手新聞社の役員クラスが、一致結束して押し紙の廃止に取り組んでおれば、報道の自由度ランキング世界第72位にみるような新聞が政治権力に取り込まれる惨憺たる状況にはならなかったのではないかと思います。朝日に追いつけ追い越せの大号令のもと、1000万部体制を目指して、なりふり構わず部数拡張路線を突っ走ってきた経営者の罪の大きさを実感します。
黒薮さんは、「新聞と公権力の暗部」で、旧統一協会による霊感商法の被害額が35年間で1237億円であるのに対し、押し紙による被害金額は32兆6200億円に及ぶとの試算を示しておられます。
新聞各社は、国有地の払い下げや、第3種郵便物・再販制度・消費税の軽減税率の適用、あるいは記者クラブ室の提供など様々な優遇措置を受けているだけでなく、戦後の読売新聞と朝日新聞の最高責任者は、いずれもアメリカの協力者(手先・スパイ)だったことが米国の公文書で明らかになっています。従って、日本の新聞社は本来の意味でのジャーナリズム精神はそもそも持ちあわせていなかったのではないかとの疑念があります。ソビエトや中国、あるいは軍事独裁政権の例を持ち出すまでもなく、新聞やテレビは本来に国家権力機構の一部であると割り切ってしまえば、わが国で、押し紙が政治権力によって見逃され、マスコミ統制の道具に利用されてきたとしても不思議ではありません。
しかし、以前は、経営と記事は別物だと割り切り、憲法の保障する国民の知る権利を実現するために取材活動に命をかけていた記者がたくさんいたように思います。朝日新聞阪神支局の若い記者が何者かによって殺害された衝撃的事件のことは、宣明に記憶しています。
しかし、押し紙問題が販売局以外の編集部の記者達にも知られるようになり、押し紙により高収入を得てきたことを知った時、真からの正義感に燃えて権力の不正を追及する取材・報道に専念することが果たして出来るのか、はなはだ疑問です。新聞社の経営と自らの家族と生活の生殺与奪の権が、権力に握られていることを知った時、記者のメンタルにどのような影響を及ぼすか、想像に難くありません。
本来、押し紙判決の言渡しの期日には、記者席には新聞記者が満席状態で座っていてしかるべきですが、記者席には新聞記者の姿は一人もいないのが現実です。もちろん、押し紙問題について新聞やテレビが取り上げることもありません。
 日本新聞協会の公正取引協議委員会は、「モデル細則」を策定して、全国11地区の地区公正取引協議会に、「押し紙」の具体的定義を示して押し紙の自主解決の徹底をはかろうとしたことがあります。公正取引委員会もこの取組を全面的にバックアップする姿勢を示しました。1985年(昭和60年)頃のことです。
日本新聞協会の公正取引協議委員会は、「モデル細則」を策定して、全国11地区の地区公正取引協議会に、「押し紙」の具体的定義を示して押し紙の自主解決の徹底をはかろうとしたことがあります。公正取引委員会もこの取組を全面的にバックアップする姿勢を示しました。1985年(昭和60年)頃のことです。
平成9年に北國新聞社が販売店にあらかじめ注文部数を指示して押し紙禁止規定の脱法行為をはかるという事件が発生しました。この事件について、公正取引委員会は史上初めて押し紙の本格的調査を行い、同社に排除勧告を発令します。ちなみに、公取委が押し紙の排除勧告を発令したのは、後にも先にもこの時の一回だけです。
北國新聞の押し紙事件については、インターネットで検索してもらうことにして、公取はこの事件をきっかけに、何故か、それまでの新聞業界による押し紙の自主規制(予備紙2%の自主的ルール)を免除する方針に転換します。その結果、新聞社は相互監視の役目を放棄し、他社の目を気にすることなく、予備紙2%自主ルールに反し、予備紙を際限なく増やしていくようになります。
更に、公取委は平成11年告示を改正し、従前の「注文部数を超えて」の文言を「注文した部数を超えて」という文言に変更します。この文言の変更の意味、経過については、別稿で報告することにします。
北國事件を契機とする公取の押し紙禁止規定の取り締まり方針の大転換の表向きの理由は、押し紙の規制を新聞業界の自主性に委ねていたのではいつまでも解決出来ないので、爾後、公取委が直接厳しく取締に乗り出すことにするというものです。
しかし、公正取引委員会の人員や予算の規模からして、全国100社を超える新聞社とその系列の販売店の押し紙問題を公取委の力で解決するのが出来ないことは歴然としています。公取委がこの方針転換は、新聞社に対し押し紙問題は今後不問にすることを宣言したに等しいものです。
平成11年告示の「注文部数」の文言の改定の結果、裁判所は「新聞社が販売店の注文した部数を超える新聞を供給しなければ、注文した部数にどれだけの予備紙が含まれていようとも押し紙にはならない」との解釈をとることが出来ようになりました。
長々と、述べてきましたが、今回の福岡高裁と大阪高裁の判決は、新聞業界が自主的に決めた予備紙の上限規制2%のルールについて、平成11年告示改正により撤廃され法的拘束力を失ったとの判断を示し、仮に、実配数1000部の販売店が2000部あるいは3000部、論理的には1万部の新聞を注文した場合でも、新聞社がその部数を越えて新聞を供給しない限り押し紙には該当しないという立場に立つことを明言しています。独禁法新聞特殊指定の押し紙禁止規定を事実上廃棄するに等しい判断です。
最高裁判所の違憲立法審査権はともかくとして、下級裁判所には、法令の廃止に等しい法律解釈を行う権限はないにもかかわらず、地裁・高裁を問わず、押し紙の敗訴判決を下した裁判官はみな等しくこのような法令解釈を採用しています(注:もちろん、そのような裁判官ばかりではありません・・・)。
今般の自民党国会議員の「裏金問題」に端を発した衆議院の補欠選挙における自民党の全敗は、日本社会の根底からの地殻変動を予感させる出来事です。
将来に希望を失わず、正義感にあふれる裁判官との出会いを楽しみに、今後も押し紙裁判を続けていきますので、引き続きご支援とご協力のほどをよろしくお願いします。
草々
