『スキャンダル大戦争③』の再評価、2003年にはすでに弘中弁護士らによるデタラメな訴訟ビジネスを問題視していた
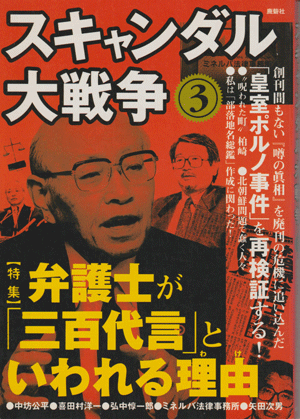
雑誌なりテレビなりが過去に取り上げたテーマを歴史の時間軸にさかのぼって検証する作業は、ジャーナリズムを正当に評価する上で欠くことができない。それによりメディア企業の性質が輪郭を現わしてくる。
「訴訟ビジネス」とは、人権救済という弁護士本来の役割よりも、弁護活動によって得られる報酬を優先して、クライアントを選ぶ弁護活動を意味する。金さえ支払えば誰の弁護でも引き受ける弁護活動である。逆に貧乏人は対象外。1時間に5万円という相談料を弁護士から提示されたただけで、自分とは縁のないエリート達の世界であることを知る。
メディア黒書でも、度々、訴訟ビジネスを取り上げてきた。
ところがこの問題は、筆者が着目するよりも、かなり古くから存在し、しかも、あるメディアが徹底取材していたことが分かった。
2003年2月に発行された『スキャンダル大戦争③』(鹿砦社)が、「弁護士が『三百代言』といわれる理由」と題する特集を組んでいる。ここで批判されているのは、中坊公平、喜田村洋一、弘中惇一郎、矢田次男らの弁護士である。同誌が問題にしているのは、いわゆる弁護士の「2枚舌」である。
たとえば報道被害者の弁護をしながら、同時に報道加害者であるメディア企業の代理人として活動する。『スキャンダル大戦争③』が指摘したケースをいくつか引用してみよう。
〔喜田村洋一弁護士〕
文藝春秋、NHK、読売新聞社の顧問、『噂の眞相』の弁護をしながら三浦和義側の代理人をした。
〔弘中惇一郎〕
『噂の眞相』の「和久・西川刑事裁判」の弁護をしながら、三浦和義、野村抄知代、叶姉妹の対メディア裁判を務めた。
〔林陽子弁護士〕
文藝春秋の顧問弁護士だが、三浦和義対メディア裁判の一部の代理人を務めた。
〔飯田正剛〕
テレビ朝日の顧問弁護士をしながら、作家・柳美里の小説『石に泳ぐ魚』
でモデルとして描かれ、プライバシーを侵害されたとして訴えられていた原告女性の代理人をしていた。
◇「無罪請負人」
筆者に言わせれば、対立する双方の弁護を展開する弁護士は、人間性や人格そのものに問題がある。信用できない。嘘つきそのものだ。金銭目的で活動しているとしか思えない。
ところがこのような活動スタイルに徹している弁護士の人間性を異常とは感じない世論が形成されている。
たとえば、弘中弁護士がカルロス・ゴーンの代理人に就任すると、多くのメディアが「無罪請負人」の活躍に期待する視点から報道を展開した。過去にサラ金の武富士や先物投資会社・エーシーイー・インターナショナルの代理人を務めていた事実を伝えるメディアは皆無だ。ゴーンを勝訴させるためには、平気で嘘をつくのではないかというのが、筆者の見方だ。
ここ数年、訴訟ビジネスが急速に広がっている。その萌芽期は、実は『スキャンダル大戦争③』が発売された16年前の時代だった。小泉純一郎を長とする司法制度改革の時代である。長い歳月を挟んで、改めて過去のジャーナリズムを検証するとき、『スキャンダル大戦争』は単なる「読み捨て」雑誌ではなかったことが分かる。
しかし、過去にミニコミ誌が発掘したテーマを、その後、大メディアが引き継ぐことはなかった。このあたりに日本のジャーナリズムの深刻な問題がある。
