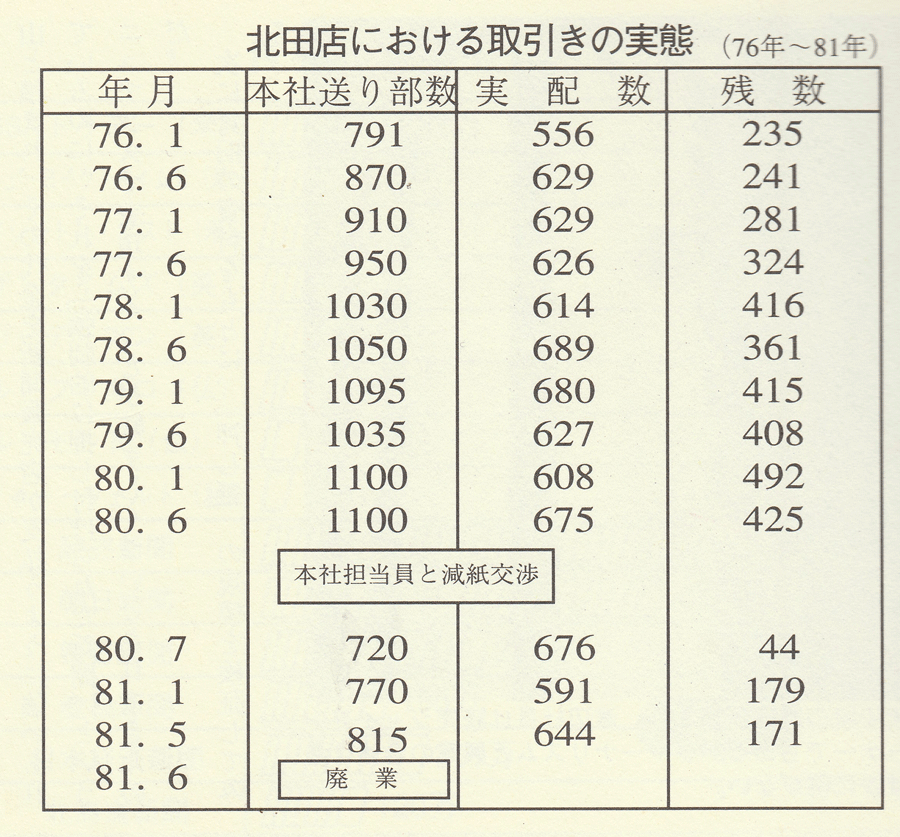出版社に忍び寄る読売新聞の影、懇親会に出版関係者240人、ジャーナリズム一極化への危険な兆候
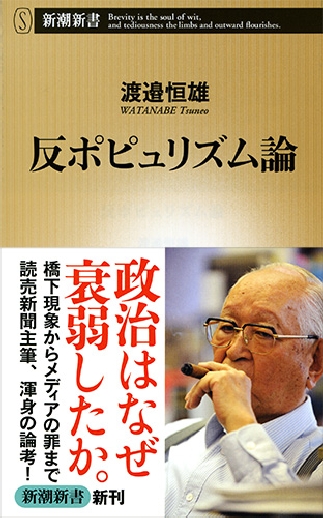
新聞社と放送局の間にある癒着が語られることがあるように、新聞社と出版社のグレーゾーンを薄明りが照らし出すことがある。
今年の5月11日、読売新聞社は「出版懇親会」と称する集まりをパレスホテル東京で開催した。読売新聞の報道によると、約240人の出版関係の会社幹部を前に、渡辺恒雄主筆は、「日頃の出版文化について情報交換していただき、率直なご意見を賜りたい」とあいさつしたという。
出版関係者にとって新聞社はありがたい存在である。と、いうのも新聞が書評欄で自社の書籍を取りあげてくれれば、それが強力なPR効果を生むからだ。新聞の読者が老人ばかりになり、部数が減っているとはいえ、中央紙の場合は100万部単位の部数を維持しているうえに、図書館の必需品にもなっているので、依然として一定の影響力を持っている。そんなわけで読売新聞社から懇親会への招待をありがたく受け入れた出版関係者も多いのではないか。
しかし、新聞販売現場の現場を25年にわたって取材してきたわたしの視点から新聞業界を見ると、新聞業界への接近は危険だ。書籍ジャーナリズムに、忖度や自粛を広げることになりかねない。同じ器に入るリスクは高い。新聞業界そのものが、欺瞞(ぎまん)の世界であるからだ。醜い裏の顔がある。
◆清水勝人氏の「新聞の秘密」
いまから半世紀前の1977年2月、雑誌『経済セミナー』で「新聞の秘密」と題する連載が始まった。執筆者は、清水勝人氏。連載の第1回のタイトルは「押し紙」である。
清水氏は、当時、『経済セミナー』だけではなく、他の雑誌でも新聞批判を展開していた。清水勝人氏の経歴についてはまったく分からない。聞くところによると、「清水勝人」というのはペンネームで、新聞社に所属していたらしい。実際、「新聞の秘密」を細部まで知り尽くしている。
連載の第1回原稿の劈頭(へきとう)で清水氏は、新聞業界の体質について次のように述べている。
「新聞という商品、新聞業界にとって最も不幸なことは、それが今日まで世論の批判の対象外-「批判の聖地」におかれてきたことではなかったかと思う。これまでごく少数の例外を除いては、新聞は自らの矛盾、誤りをみずからの手で批判したり、訂正しようとは決してしなかったし、第3者からの批判を率直に受け入れようともしなかつた。
新聞は今日まで厳しく監視する第3者を持たなかったためにどうしても、みずからの矛盾、誤り、時代錯誤に気付くのが遅れてしまいがちだったし、他人の批判にさらされないために規制力を失いがちであったといえるのではないかと思われる。」
清水氏は、「押し紙」によりABC部数をかさ上げして、紙面広告の媒体価値を高める新聞社のビジネスモデルを暴露した。わたしがここ25年ほど指摘してきた問題を、半世紀前にクローズアップしていたのである。おそらく問題をえぐり出せば、新聞人は過ちを認めて、方向転換するだろうと期待して、筆を執ったのだろう。
が、そうはならなかった。いつの間にかこの報道は消えてしまった。「無かったこと」にされたのである。
その後、1980年代になると、共産党、公明党、社会党が超党派で新聞販売の問題を取り上げるようになった。85年までに15回の国会質問を行った。新聞業界は批判の集中砲火を浴びたのである。「押し紙」も暴露された。
たとえば1982年3月8日に、瀬崎義博議員(共産党)が、読売新聞鶴舞直売所(奈良県)の「押し紙」問題を取り上げた。この質問で使われた資料は、後に「北田資料」と呼ばれるようになり、新聞販売の問題を考えるとひとつの指標となった。次に示すのが、鶴舞直売所の「押し紙」の実態である。
しかし、5年に渡る国会質問は何の成果も残さなかった。新聞業界は反省もしなければ、状況の改善もしなかった。もちろん報道もしなかった。再び「無かったこと」にされたのだ。
◆公正取引委員会を翻弄して「押し紙」を自由に
1997年になって新しい動きがあった。公正取引委員会が北國新聞社に対して「押し紙」の排除勧告を発令したのである。北國新聞社は朝刊の総部数を30万部にするために増紙計画を作成し、3万部を新たに増紙した。その3万部を新聞販売店に一方的に押しつけていた。夕刊についても、同じような方法で「押し紙」をしたというのが、公取委の見解である。
さらに公取委は、「他の新聞発行者においても取引先新聞販売業者に対し『注文部数』を超えて新聞を供給していることをうかがわせる情報に接した」として、日本新聞協会に対して改善を要請した。
さすがに新聞業界も「押し紙」を反省するかに思われたが、逆に公取委に対して驚くべき対抗策にでる。
当時、新聞業界は内部ルールで、表向きは「押し紙」を禁止していた。販売店に搬入する新聞の2%を予備紙と定め、それを超える部数を「押し紙」と定義していた。俗に「2%ルール」と言われていた規定である。
北國新聞に対する処分を機に公取委から「押し紙」問題を指摘された日本新聞協会は、驚くべきことに、この「2%ルール」を削除したのである。それにより販売店で過剰になっている新聞は、「押し紙」ではなく、すべて「予備紙」という奇妙な論理が独り歩きし始めたのだ。予備紙は、販売店が営業目的で好んで注文した部数ということになってしまったのだ。
「押し紙」裁判でも、こうした論理がまかり通るようになった。しかし、残紙に予備紙としての実態はなく、その大半は古紙回収業者によって回収されてきた。営業に使うのは「新聞」ではなく、ビールや洗剤といった景品だった。
◆裁判にはめっぽう強い読売新聞
新聞業界の内側を見る視点は、「押し紙」問題だけではない。
不思議なことに中央紙は、裁判となればめっぽう強い。たとえばわたしは2008年2月から1年半の間に、読売新聞社から3件の裁判(請求額は約8000万円)を起こされたことがあるのだが、2件目の裁判で壮絶な体験をした。最初の裁判は、わたしが勝訴したが、2件目で、「大逆転」された。野球でいえば、9回裏の2アウトからの逆転である。それぐらい新聞社は、なぜか裁判に強い。
発端は、「押し紙」を断った新聞販売店を読売新聞西部本社が強制改廃したことだった。江崎徹志法務室長ら数人の社員が、事前連絡することなく販売店に押しかけ、改廃を宣言した。その直後に読売ISの社員が、店舗にあった折込広告を搬出した。この行為をわたしが、「窃盗」と表現したところ、社員らが2200万円を請求する名誉毀損裁判を起こしたのだ。
わたしは、「窃盗」を文章修飾学(レトリック)でいう直喩として使ったのである。「あの監督は鬼だ」といった強意を際立たす類型のレトリックである。店主に強烈な精神的衝撃を与えた直後にさっさと折込広告を運び出したから、「窃盗」と表現したのである。それだけのことである。だれも本当に窃盗が発生したとは思っていない。
この裁判で読売新聞社の代理人として登場したのは、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士だった。改憲論をリードしている読売新聞社が、護憲派の自由人権協会の弁護士を依頼する行為に違和感を感じた。軽薄なものを感じた。
さいたま地裁で行われた第1審は、わたしの勝訴だった。東京地裁での第2審もわたしの勝訴だった。ところが最高裁が口頭弁論を開き、判決を東京高裁に差し戻した。そして東京地裁の加藤新太郎裁判官は、わたしに110万円の支払いを命じたのである。後に加藤新太郎裁判官について調べてみると、読売新聞に少なくとも2回登場していることが分かった。
◆政界との癒着、874万円の政治献金
新聞業界と政界の距離は近い。癒着の度合いは首相との会食ぐらいではすまない。
新聞業界は、販売店の同業組合を通じて、政治献金を送ってきた事実がある。目的は、再販制度の維持、新聞に対する軽減税率の維持などである。最近は、学習指導要領の中に学校での新聞の使用を明記させることにも成功している。新聞記事を模範的な「名文」と位置づけて、児童・生徒に熟読させる国策を具体化したのだ。
2017年度、新聞業界は874万円を献金している。内訳は、主要な議員21人(述べ人数)に対して、「セミナー参加費」の名目で、総計234万円。この中には、とよた真由子(自民)、漆原良夫(公明)といった議員(当時)が含まれている。
セミナー参加費とは別に、「寄付」の名目で、128人の議員に対して640万円を献金している。金額としては1人に付き一律5万円で高額とはいえないが、政治献金であることには変わりがない。挨拶がわりに金をばら撒いているのだ。
裏付け資料は次の通りである。
他の年度についても、政治献金を繰り返してきた。
◆進むジャーナリズムの一極化
出版業界は、新聞の帆を立てた船に乗り込まないほうが懸命だ。ジャーナリズムの一極化は、最終的には自分に跳ね返ってくる。
日本の新聞業界は、清水氏の内部告発を無視し、5年にわたる国会質問を無視し、公正取引委員会の指導を逆手に取って、自由に「押し紙」を増やせる体制を構築した。昔から何も変わっていない。反省もなければ、対策もない。
1936年8月15日付け『土曜日』は、新聞業界について次のように書いている。太平洋戦争を挟んで現在まで、権力構造に組み込まれた新聞の本質は何も変わっていない。
「新聞の仲間にはヘンな協定があって、新聞同士のことはお互いに書くまいということになっている。これはいくつ新聞があっても、どれもこれも何かの主義主張があるのではなく、みんな同じ売らん哉の商品新聞ばかりで、特ダネの抜きっこ、販売拡販競争から起こった事で相手を攻めれば、その傷はやがて戻ってきて痛むのを知っているからである。これはもう新聞が完全に社会の木鐸でなくなったことを示すもので、ただただ商品であるだけから起こった仁義なのである」