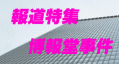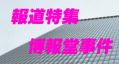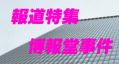 「置き引き」という行為がある。空港などで足元に荷物をおいて搭乗手続きをしている時など、ちょっと目を離したすきに、さっと荷物をさらっていく手口である。ネズミ小僧も顔負けの早業だ。
「置き引き」という行為がある。空港などで足元に荷物をおいて搭乗手続きをしている時など、ちょっと目を離したすきに、さっと荷物をさらっていく手口である。ネズミ小僧も顔負けの早業だ。
筆者が博報堂の取材をはじめたのは、今年の3月であるから、開始から半年が過ぎた。最初は折込広告の水増し疑惑程度に考えていたが、その後、取材が進むにつれて、アスカコーポレーションが被った被害額の大きさもさることながら、騙しの手口が多様でさまざまな分野に被害が及んでいることがわった。
スキがあれば、そこに付け込んでくる。まさに置き引きを連想させる手口なのだ。経済事件の取材には、怒りや悲壮感が付きものなのだが、今回は、ブラックユーモアがある。
たとえば、2010年に福岡市の大濠公園でイルミネーションイベントが行われ、アスカは主催者にはならなかったものの、特別協賛企業として3000万円の予算を限度として、イベントをサポートしたのだが、イベントが終わってみると、イベントを仕切った博報堂側から5,500万円も請求された。しかも、警備費やらPR費やら、事務局対応費やら、わけのわからない請求が並んでいたという。(この事件については、日を改めて記述する機会があるかも知れない)。
不正は、アスカが過去の調査を強化するにつれて、次々と「発見」されている。もちろん、「置き引き」レベルよりも遥かに悪質な不正、たとえばCMの番組提案書に嘘の視聴率を書き込んで、番組枠を買い取らせた疑惑で、約48億円を請求されている大事件もあるが、不正の手数と言う点からすると、「置き引き」のレベルが多い。
最高検察庁から松田昇氏が人物が天下りしている事実と不正の多さが整合しない。本来、検察人脈を使って、不正を「取り締まる」のが松田氏の任務なのだが、何をやっているのだろうか。が、これでも博報堂DYメディアパートナーズは東証の上場企業である。
半年の取材を経て、次に考えなくてはならないのは、天下り問題も含めた企業体質である。博報堂事件を考えるうえで、特に留意しなければならない過去の事件がある。それは2008年ごろから明るみに出てきた郵政関連の事件である。ちょうどこの同じ時期に、博報堂は同じ「指揮官」の下で、アスカのPR業務を独占するようになったのである。そして、今にして思えば「置き引き」を連想させる不正を繰り返していたのだ。
この郵政関連の事件には博報堂の体質がよく現れている。
続きを読む »