金竜介弁護士らが金銭請求している5億8,000万円に道理はあるのか? 892人を被告とする損害賠償裁判、弁護士大量懲戒請求事件、東京地裁も困惑か?

3月初旬、わたしは2人の弁護士が起こした損害賠償訴訟で、被告にされたAさん(男性)を取材した。この訴訟の背景には、一時期、メディアがクローズアップした一連の弁護士大量懲戒請求事件がある。現在では報道は消えてしまったが、しかし、水面下で事件は形を変えて続いている。
被告・Aさんによると、自らが被告にされた裁判では、被告の人数が892人にもなるという。Aさんは、その中の1人である。
この裁判を起こしたのは、金竜介弁護士(写真:出典=出典=台東協同法律事務所HP)と金哲敏弁護士の2名である。2人の原告の代理人は高橋済弁護士である。訴状は、2021年4月21日に東京地裁で受理された。
請求額は約5億8,000万円である。まもなく提訴から1年になるが、未だに口頭弁論が開かれていない。わたしが3月に東京地裁に問いあわせたところ、担当書記官は、「何もお答えできることはありません」とあいまいな返事をした。Aさんも、自分の答弁書を提出したが、その後、裁判所からの連絡はない。他の被告がどのような対応をしているのかも、知りようがない。
わたしは東京地裁で裁判資料の閲覧を求めたが、これも認められなかった。理由はわからない。
◆大量懲戒請求への道
事件の発端は、インターネット上のサイト「余命三年時事日記」に特定の弁護士に対して懲戒請求を働きかける記事が掲載されたことである。同ウエイブサイトからは懲戒請求のために準備した書式がダウンロードできたという。その書式に自分の住所や名前などを記入して、「まとめ人」に送付すると、集団による大量懲戒請求の段取りが整う。
高橋弁護士が作成した訴状によると、「少なくとも平成29年(2017年)11までに」は懲戒請求を働きかける記事が掲載されていたという。懲戒請求の理由は、次のとおりである。訴状から引用する。
「違法である朝鮮人学校補助金支給請求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。
利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成させるコリアン弁護士会との連携も過過できるものではない。
この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである」
このような主張自体は、国境が消滅しはじめて言語なども多様化してきた現代の感覚からすれば時代錯誤だ、というのがわたしの考えだ。国際感覚が欠如した「島国根性」にほかならない。
しかし、懲戒請求者の全員が懲戒理由を吟味して、懲戒請求書を「まとめ人」に送ったわけではない。Aさんも深くは考えなかったという。
訴状によると、2018年4月19日ごろに、「東京弁護士会の綱紀委員会は、本件懲戒請求についての調査開始をした」。しかし、翌日に「事案の審査を求めない、との議決をした」。さらにその後、弁護士会としても「被調査人を懲戒しない」ことを決定した。そして、27日に金竜彦弁護士と金哲敏弁護士にその旨を通知した。
2人は「この議決書及び決定書の送達があった日に、自らが懲戒請求を受けたことを知った」のである。
◆個々人、別々に金銭を請求
金銭請求の内訳は、被告1名に付き慰謝料30万円、弁護士費用3万円である。(ただし、内金については控除)。金銭請求の総額は約5億8,000万円になる。
実は、被告をひとまとめにして金銭を請求する代わりに、被告個々人に対して個別に金銭請求する方法も一般化している。たとえばわたし自身の経験になるが、2008年、読売新聞社がわたしに対して2230万円の賠償を求める名誉毀損裁判を起こしたことがある。この裁判の原告は、3人の読売社員と法人としての読売新聞社だった。読売の代理人の喜田村洋一・自由人権協会代表理事は、3個人と1法人に対して、個々の金銭請求額を提示してきた。その結果、わたしの年収の10倍近い金銭請求額を突きつけれたのである。
※裁判の結果は、地裁、高裁はわたしの完勝。最高裁が高裁判決を差し戻し、最終的には読売が劇的逆転勝訴を勝ち取った。わたしが、読売とその社員3人に約110万円の現金を払うことになった。
改めて言うまでもなく、個々人に対して金銭請求をしても、違法行為ではない。実際、金竜介弁護士と金哲敏弁護士は、この方法で約5億8,000万円というとてつもない金銭を請求したのである。
◆精神的苦痛による損害
しかし、損害金を請求するというからには、具体的な損害が発生していることが前提になる。ところが2人の弁護士が自分たちを対象とする大量懲戒請求が起こされていたことを知ったのは、弁護士会が懲戒請求を却下した後である。従って、精神的にも経済的にも損害を受けていない可能性が高い。あえて言えば、この事実を知らされたときに驚きと憤りを感じたという程度ではないだろうか。その損害の程度と5億8,000万円の請求に合理的な整合性はあるのだろうか。
横浜副流煙裁判、反スラップ裁判、弁護士懲戒請求も必要

横浜副流煙裁判の被告・藤井将登さんが、来年早々に反スラップ裁判を起こす。原告には将登さんのほかに、妻の敦子さんも加わる。敦子さんが原告になるのは前訴の中で、非禁煙者であるにもかかわらず喫煙者として誹謗中傷されたからだ。
この事件は、将登さんが同じマンションの2階に住むAさん一家から、将登さんの副流煙が原因で、受動喫煙症に罹患したとして、4500万円の損害賠償を請求されたものである。しかし、第一審の横浜地裁も第二審の東京地裁も、Aさんらの請求を棄却した。第1審は、作田医師の医師法20条違反も認定した。
そこで藤井さん夫妻が反スラップ裁判を起こすことになった。しかし、この裁判は、Aさんらに対する反訴でも、Aさんの代理人・山田義雄弁護士親子に対する反訴ではない。Aさんら3人の診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長を被告とした損害賠償裁判である。訴外者に対する反スラップ裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】
横浜の副流煙裁判、地元住民が被告夫妻を支援する会を結成、Change.orgで国境を越えた署名活動を開始、反訴(損害賠償)と弁護士懲戒請求も視野に

横浜の副流煙裁判で、被告・藤井夫妻を支援するための署名活動が始まった。これは、今年になってから、すすきの団地の住民で結成された藤井夫妻を支援組織「理不尽なタバコ裁判に反対する会」が進めているもの。同会は、恫喝(どうかつ)の色調が強いこの事件の真実を伝えると同時に、「禁煙ファシズム」に警鐘を鳴らしている。
Change.orgに掲載されたアピール文は、次のように「禁煙ファシズム」を批判している。
本来であればこのような訴訟は日本たばこ産業や、それを認める国に対して行われることであり、「国で許可されたことをマナーを守って行っている個々人」に対し起こされるべき訴訟ではありません。
日本たばこ産業と日本政府は、日本禁煙学会を始めとする嫌煙団体が、個人に対し、このような「狙い撃ち」を行っていることをこのまま放置し続けるつもりなのでしょうか。こんなことをされれば、個人の生活が破綻します。
◇反訴と弁護士懲戒請求
今後、被告は反訴(損害賠償)も視野に入れて裁判を進める方針のようだ。
原告3人のうち1人(夫)は、提訴の約1年前までは喫煙者だった事実があり、副流煙が原因で体調を崩したというよりも、自分が吸ってきた煙によって体内に取り込まれた化学物質の蓄積が原因で体調を崩した可能性が高い。
原告の山田義雄弁護士らも、提訴前からこのあたりの事情を知っていた。
従って、虚偽の事実を前提とした裁判を禁止する弁護士職務基本規程75条に違反しており、3年以内に懲戒請求される可能性が高い。
※弁護士職務基本規程75条:弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
【事件の概要】
この裁判は、マンションの2階にすむ横山家(仮名)の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井家の家主・将登さんに4500万円の金銭支払いや喫煙の禁止などを請求したものである。
将登さんが自室で吸っていた煙草の副流煙が原因で、原告3人が化学物質過敏症になったというのが、提訴理由だ。原告は、将登さんの妻・敦子さんも、煙草を吸っていたと主張している。
この事件の最大の問題点は、化学物質過敏症がだれでもなる可能性のある病気であり、その原因もイソシアネートなど、多種多様であるにもかかわらず、藤井将登さんの煙草の副流煙と断定している点である。たとえ煙草の煙であっても、その煙草の発生源は分からないはずだ。団地内に自然発生的にできた「喫煙場」である可能性もあれば、藤井将登さんとは別の住民が吸った煙草の可能性もある。
原告は、戸別に「煙草を吸っているか否か」をアンケート調査したが、煙草をめぐるトラブルが発生している団地で、「煙草を吸っているか否か」を質問されたら、「吸っていない」と答えるのが常識だろう。アンケート調査は信憑性がない。
さらにマンションから50メートルほどのところに幹線道路があり、そこからの排気ガスも団地に流れ込む。原告の1人は、「宮田診断書」の中で「車の排気ガス」に反応(10段階で8評価)することを認めている。これが原因の可能性もある。
また、原告の陳述書からは、新築マンションに入居した生活歴(シックハウス症候群の疑惑)がある事実、医療機関に長期通院するなど日常的に化学物質に接してきた事実、携帯電話のユーザーである事実などが読み取れる。それが化学物質過敏症を引き起こした可能性もある。
もっと広い視野でみると、花粉も化学物質過敏症の引き金になる。
ちなみに横山家の家主・明さんは、元喫煙者だった。このことを昨年の10月まで、裁判所に報告していなかった。
つまり、化学物質過敏症の原因が藤井将登さんが肺から吐き出した煙であると断定することはできないのだ。原告の山田義雄弁護士は、明さんが元喫煙者であることも知っていた。それにもかかわらず原告3人の化学物質過敏症の原因が藤井将登さんの煙草にあると主張し、それを前提に裁判所へ資料を提出してきたのだ。
事件の舞台が団地ということもあり、原告の主張は、多くの住民の耳にも入っている。裁判を取り下げるべきだとの声も上がっている。
ちなみに化学物質過敏症の裁判は、化学メーカーなどを被告とした裁判は、過去に提起されているが、いずれも訴えが棄却されている。個人を、しかも、煙草の煙が化学物質過敏症の唯一の原因として訴えたケースは、横浜のケースがはじめてだ。原告3人が化学物質過敏症である可能性は高いが、何が原因なのかは特定できない。生活環境の悪化が原因で、化学物質過敏症を誘因する物質があまりにも多いからだ。その代表格のひとつが、芳香剤などのイソシアネートである。米国では大きな問題になり、規制が始まっているが、日本は野放し状態だ。
携帯電話の電磁波も大きな要因のひとつだ。その意味で、原告宅の近辺に携帯電話の基地局がないかどうかを確認する必要もある。また、高圧電線なども電磁波の発生源になる。
量産型懲戒請求を受けた小倉秀夫弁護士が第3者に対して起こした裁判、1人につき10万円、推定総額9600万円の請求額は妥当なのか

弁護士懲戒請求について考察させられるある訴訟が東京地裁で進行している。この裁判の原告は小倉秀夫弁護士。被告は東京都内に在住するAさんである。発端は別の次の事件である。
900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士
全国の弁護士会に大量の懲戒請求が出された問題で、東京弁護士会の弁護士2人が「不当な請求で業務を妨害された」として、900人超の請求者に各66万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことを決めた。請求者1人ごとに訴えるため、900件超の訴訟となる。まずは2日、6人を相手に提訴する予定だ。
訴訟を起こすのは北周士、佐々木亮の両弁護士。昨年以降、計4千件の懲戒請求を受けた両弁護士は今年4月、約960人の請求者を相手に訴訟を起こす考えをツイッターで表明。■出典
繰り返しになるが裁判の発端はこの事件である。この事件になぜ小倉弁護士が関係して、訴訟まで起こすことになったのだろうか。事件の経緯を追ってみよう。
 ◇ツィッターの社会病理
◇ツィッターの社会病理
ひとりの弁護士に大量の懲戒請求書を送付したケースは、過去にもあるが、頻発する現象ではない。そのために、ニュース性が高く、ネット上などで格好の話題になる。佐々木亮弁護士のケースもこうした社会現象を起こした。ツイッターなどで、この事件について自分の意見などを表明する「炎上」現象が起きたのである。その炎上に、小倉秀夫弁護士も巻き込まれた。
その結果、ツイッターでの小倉弁護士の発言をめぐり、今度は小倉弁護士に対して、960通の懲戒請求書が送付されたである。「余命三年時事日記」という右派系のブログが、この量産型懲戒請求を呼びかけた。
懲戒請求のひな型は「余命三年時事日記」が準備したものだった。不特定多数の人々が、署名の感覚で小倉弁護士に対する懲戒請求書を送付したのだ。
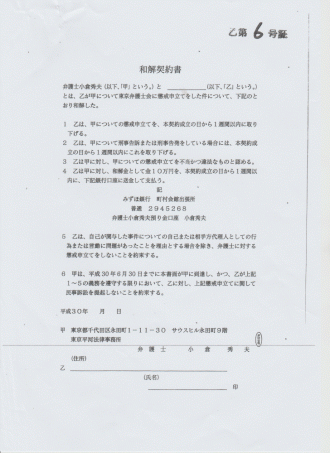 これに対して小倉弁護士は、「懲戒請求者に対して損害賠償請求をしようと考えた」(訴状)という。しかし、対象者が960人もいたので、個々の懲戒請求者に個別に損害賠償請求をすることは、大変な労力となる。そこで「自己のウェブサイト上で訴訟外の和解を呼びかけることとし、和解契約書のひな形を作成して自己のウェブサイトにアップロードした上で(甲第4号証)、本件量産型懲戒請求をしてしまった人々に対し、同ひな形を用いた和解契約の締結を申し込む内容のウェブページをアップロード」したのである。
これに対して小倉弁護士は、「懲戒請求者に対して損害賠償請求をしようと考えた」(訴状)という。しかし、対象者が960人もいたので、個々の懲戒請求者に個別に損害賠償請求をすることは、大変な労力となる。そこで「自己のウェブサイト上で訴訟外の和解を呼びかけることとし、和解契約書のひな形を作成して自己のウェブサイトにアップロードした上で(甲第4号証)、本件量産型懲戒請求をしてしまった人々に対し、同ひな形を用いた和解契約の締結を申し込む内容のウェブページをアップロード」したのである。
この請求方法に強い疑問を感じた第3者がいた。「余命三年時事日記」とは何の関係もないAさんだった。小倉弁護士が行ったウェブサイトを利用した量産型の和解提案が、弁護士としてあるまじき行為だと考え、ツイッターで何度か疑問を述べたのち、ある行動にでた。小倉弁護士に対する懲戒請求を行ったのである。
繰り返しになるがAさんは、「余命三年時事日記」の呼びかけに応じて、小倉弁護士に懲戒請求書を送付した一人ではない。「余命三年時事日記」の呼びかけが引き起こした量産型懲戒請求に対して、小倉弁護士がネット上で損害賠償を求めた行為が、弁護士としてあるまじき戦略だという観点から、懲戒請求に踏み切ったのである。
これに対して小倉弁護士は、Aさんに300万円の支払いを求める損害賠償裁判を起こしたのである。
◇最高裁の判例
この事件を検証するためには、大前提として、佐々木弁護士と「余命三年時事日記」の間にどのような論争があったのかを確認する必要がある。
「余命三年時事日記」が佐々木弁護士に対する量産型懲戒請求を呼びかけたところ、佐々木弁護士は、次のようにツイッターで応戦した。
ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(略)
これに対して「余命三年時事日記」は、ブログで、佐々木弁護士に対する刑事告訴と民事訴訟を予告した。その上で懲戒請求者の個人情報が外部にもれる懸念を示し、それを防ぐためには「早急に弁護士法の改正が必要だろう」と述べた。
これに賛同して、「炎上」渦中にいたひとりがツイッターで、「早急に弁護士法の改正が必要だろう」とツィートした。このツィートを見て、小倉弁護士が「虚偽告訴罪での告訴の対象なので、懲戒請求者の氏名・住所を秘匿する合理性がありません」とツィートした。
これに対して「余命三年時事日記」は、「この件は共謀による罪として別途告発されている事案である」などと反論。小倉弁護士に対する量産型懲戒請求を呼びかけるに至ったのである。
ちなみに弁護士法の第58条は、懲戒請求権について次のように述べている。
 第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
ただし、懲戒請求者が懲戒の事由がないことを知りながら、あえて懲戒請求した場合は、不法行為となる。次のような最高裁の判例も存在する。
懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あれて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成する
小倉弁護士は、この判例を根拠に「余命三年時事日記」の主張には根拠がないので、「日記」からの量産型懲戒請求に対する損害賠償請求は正当と主張した。それを前提に、Aさんから懲戒請求されたのは不当として、Aさんを提訴したのである。
◇Aさんが懲戒請求した理由
Aさんが小倉弁護士の量産型損害賠償請求を問題としたのは、それにより懲戒請求者が心理的圧迫を受ける点である。また、量産型懲戒請求が違法かどうかの司法判断を待たずに和解に向けた行動を取った事実である。また、和解後の懲戒請求行為に対して、一定の規制を求めてきたことである。さらにこうした事例が「詐欺のモデルケース」を作りかねない状況を生む懸念である。
ここでいう「詐欺のモデルケース」とは、ネットを利用して和解を呼びかけることにより、法的な知識を持たない大半の懲戒請求者の恐怖心を煽って、極めて合理的に金銭を徴収する行為であって、「振り込め詐欺」の類型とは異なる。
この裁判では、法律の専門知識を持たない普通の市民が、弁護士の行動に不信感を感じた場合、懲戒請求を申し立てることの是非が問われそうだ。最高裁の判例に照らし合わせてみると、共謀罪を懲戒事由にすることにはかなり無理があり、懲戒請求の根拠を欠いている可能性が高いが、だからと言って、法曹界に対する一般市民の疑問や不信感を、法解釈だけで切り捨てることができるのか?あるいは訴訟で対抗していいのか?このあたりがジャーナリズムの検証点になりそうだ。
◇ツィートと名誉毀損
ちなみに訴訟に至る前段で、Aさんがツィートした記述に対して、小倉弁護士は、名誉を毀損されたとして損害賠償を求めているが、筆者が見た限りでは、名誉を毀損しているとは思えない。
 確かに「悪徳弁護士」とか、「詐欺のモデルケースを作った北、島崎、小倉」といった表現はあるが、もともとツイッターの言語は、投稿者の感情を露呈することが前提になっており、罵倒をそのまま真実として受けとめる人はほとんどいないからだ。同じ表現が、たとえば『世界』とか、『文藝春秋』で使われていたら、名誉毀損になるだろうが、ツイッターの言語は信頼性そのものが低く「論争ゲーム」のレベルだ。
確かに「悪徳弁護士」とか、「詐欺のモデルケースを作った北、島崎、小倉」といった表現はあるが、もともとツイッターの言語は、投稿者の感情を露呈することが前提になっており、罵倒をそのまま真実として受けとめる人はほとんどいないからだ。同じ表現が、たとえば『世界』とか、『文藝春秋』で使われていたら、名誉毀損になるだろうが、ツイッターの言語は信頼性そのものが低く「論争ゲーム」のレベルだ。
ツイッター上のフェイクニュースの氾濫でも明らかなように信頼性そのものが極めて低い。そこで発せられた罵倒を名誉毀損とするのはおかしい。罵倒をそのまま鵜呑みにする人はほとんどいない。
言葉の評価は、どのような状況の中で発せられたかで変わるのである。固定的な評価はない。
◇和解契約書
小倉弁護士は、ネットで公開した和解契約書の中で、6つの条件を提示している。このうち検証する必要があるのは、次の3点である。
4、乙(黒薮注:懲戒請求者)は甲(黒薮注:小倉弁護士)に対し、和解金として金10万円を、本契約成立の日から1週間以内に、下記銀行口座に送金して支払う。(略)
5、乙は、自己が関与した事件について自己または相手方代理人としての行為または言動に問題があったことを理由とする場合を除き、弁護士に対する懲戒申立てをしないことを約束する。
6、甲は、平成30年6月30日までに本書面が甲に到達し、かつ、乙が上記1~5の義務を遵守する限りにおいて、乙に対し、上記懲戒申立てに関して民事訴訟を提起しないことを約束する。
◇背景に法曹界に対する不信感
まず、「4」に関してだが、一人の懲戒請求者につき10万円の和解金を求め、懲戒請求者の人数が960人であるから、総計9600万円の和解金を要求していることになる。1億円近い金額である。この金額が請求額として妥当なのか、検討してみる必要がある。もちろん高額請求が違法行為にあたるわけではない。
しかし、既にのべたように大半の懲戒請求者は法の素人である上に、署名の感覚で懲戒請求書を送付したに過ぎないのだ。「余命三年時事日記」に対して、たとえば30万円程度を請求するのであれば、まあ仕方がないか、という気にもなるが、「署名」に協力した人々も含めて一律に10万円という単価を設定するのは、無理があるような気がする。
それに960人もの人が「署名」に応じた背景には、法曹界に対する不信感があるからに違いない。反差別を口実に暴力を振るっている「ぐれん隊」を弁護士らが擁護したり、高額訴訟を推奨したり、事件を受認していながら手抜きをするなど、法曹界の対する評価が厳しくなっているのだ。
現に小倉弁護士も訴状の中で、弁護士会の実態について「弁護士は、その職務上、(黒薮注:懲戒申立で事件の)判断権者が判断を間違えることが相当数あることを経験的に知っており、自己が対象弁護士とされている懲戒申立で事件においてそのような誤審がなされるリスクのあることを認識している」と述べている。
◇懲戒請求に対するカウンターで莫大な賠償金
「5」の条項を認めてしまうと、あるまじき行為を働いている弁護士に遭遇しても、懲戒請求できなくなる。たとえば筆者の場合、弁護士を取材する機会が多いが、その中で事実を捏造し、それを根拠に裁判を起こしているケースに気づいたこともある。たとえば最近の例でいえば、煙草が原因で病気になっていながら、原告本人は煙草を吸っていなことにして、隣人の副流煙が原因だと事実関係を偽り、それを前提に高額訴訟を起こした例がある。
当然、懲戒請求の対象になるが、「5」の条項を受け入れれば、こうしたケースも放置せざるを得なくなる。当然、弁護士法58条とも整合しない。
「6」は、懲戒請求者が「1」から「5」の条件を受け入れれば、提訴しないことを約束したものである。和解においては、必要な記述に違いないが、逆説的に考えると、「1」から「5」を拒否した場合は、提訴すると言っているのだ。提訴行為が普通の市民にとっては、脅威と感じられるのはいうまでもない。
小倉弁護士にしても、佐々木亮弁護士にしても、懲戒請求に対するカウンターで莫大な賠償金を手にする可能性がある。筆者には、これが弁護士本来のありかたとは思えない。早急に訴訟を取り下げるべきだろう。
ツイッターがこれらの事件の引き金になっていることも間違いない。
弁護士に対する大量懲戒請求事件を考える、1億円に近い「和解金」が入る構図に

このところ、「弁護士から裁判提起をほのめかされたことがある」という情報提供が相次いで寄せられている。個々の件について調査中なので、いまの段階では、弁護士名の公表はひかえるが、武道の有段者が素人を恫喝しているような印象がある。
 柔道や空手の流派によっては、路上での武術の使用は禁止されているが、法律の専門家には規制がない。
柔道や空手の流派によっては、路上での武術の使用は禁止されているが、法律の専門家には規制がない。
この種の事件でいま問題になっているのは、弁護士が大量の懲戒請求を受けた件である。組織的に行われた「攻撃」である。一説によると懲戒請求の件数は、1人の弁護士につき900件を超えているという。懲戒理由は同じらしい。
これに対して、弁護士側は懲戒請求者全員に対して、損害賠償裁判を起こすことを宣言した。その方針を記者会見を開いて発表した弁護士もいる。ただし、実際に提訴に及ぶ前に和解に応じる旨も明らかにした。
その和解条件のひとつに、不当懲戒を認めて10万円を支払うというものがある。
◆莫大な和解金が入る構図
弁護士を軽々しく懲戒請求すること自体には問題がある。当然、正当な理由がなければ懲戒は認められるはずがない。弁護士であれば、そんなことは分かっているはずだ。懲戒請求の対象になるのは、懲戒理由の中身であって、量ではないからだ。署名を提出するのとは意味が異なるのだ。
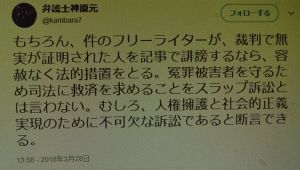 と、なれば懲戒対象弁護士は、答弁書を1枚作成して、それをコピーして書面を準備し、弁護士会へ提出するだけですむ話だ。
と、なれば懲戒対象弁護士は、答弁書を1枚作成して、それをコピーして書面を準備し、弁護士会へ提出するだけですむ話だ。
ところが懲戒請求された弁護士らは、懲戒請求者1人につき10万円の支払を提案しているのだ。それに応じなければ、提訴することも宣言している。
懲戒請求者が900人とした場合、全員が和解に応じれば、弁護士は9000万円もの和解金を得ることになる。訴訟をして弁護士が勝訴し、かりに20万円の損害賠償が認められた場合は、その判例を根拠にして、和解に応じなかった懲戒請求を提訴すれば、さらに莫大な額の金銭が入ってくることになる。
おそらく1億円を超えるだろう。
読者はこのような構図をどう考えるだろうか。構図がおかしいと感じないだろうか。
実際、おかしいと感じた人もいて、先に述べた戦術を選んだ弁護士の1人に対して、今年の5月、懲戒請求を申し立てた。この人は大量懲戒請求には加わっていない。無関係である。構図自体に問題があると考えて、懲戒請求したのである。
ところが、これに対して懲戒対象弁護士が選んだのは、やはり名誉毀損裁判だった。
◆軽々しい裁判提起
軽々しく裁判を提起したり、提訴をほのめかす風潮が生まれている。それが言論を委縮させていく。日本は、一歩ずつ言論の自由のない国へ近づいている。警察や政府がそれを主導しているのではない。「市民」の側が自分で自分の首を絞めはじめているのである。
神原元・自由法曹団常任幹事が公安警察との協力を示唆、ツィッターで意見表明、懲戒請求者のリストを提供か?
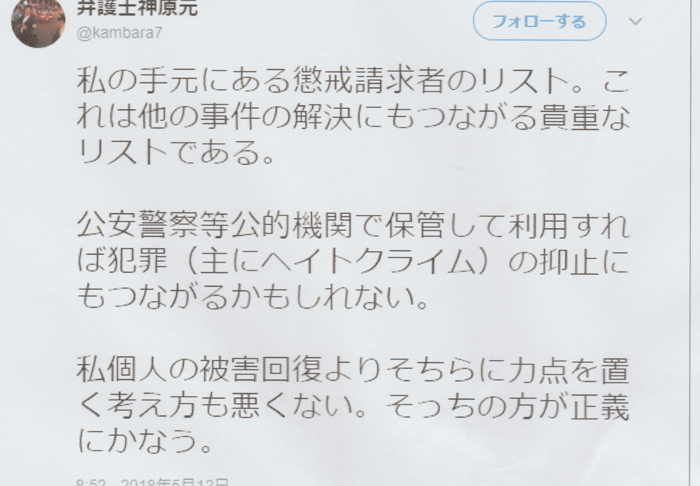
弁護士に対する集団による懲戒請求事件で、ただならぬな問題が浮上している。懲戒請求者の個人情報が、元「しばき隊」隊員で自由法曹団常任幹事の神原元弁護士から公安警察などに提供される可能性である。神原氏がツィッターでそれを示唆したのだ。
筆者がこの問題を知ったのは、猪野亨弁護士のブログによる。■出典
筆者は、知人から問題の「投稿」ツィートを入手した。(神原弁護士は、筆者のツィッターをブロックしている。)それによると、同弁護士は、5月12日に次のように「呟いて」いる。
私の手元にある懲戒請求者のリスト。これは他の事件の解決にもつながる貴重なリストである。
公安警察等公的機関で保管して利用すれば犯罪(主にヘイトクライム)の抑止にもつながるかもしれない。
私個人の被害回復よりそちらに力点を置く考え方も悪くない。そっちの方が正義にかなう。■出典
◇スパイ活動を展開
ところで公安警察とはどのような組織なのだろうか。ウィキペディアは次のように説明している。
国内的には、極左暴力集団、朝鮮総連、日本共産党、社会主義協会、学生運動、市民活動、新宗教団体、右翼団体などを対象に捜査・情報収集を行い、法令違反があれば事件化して違反者を逮捕することもある。さらには、同僚の公安警察官、一般政党、中央省庁、自衛隊、大手メディアなども情報収集の対象になっているとされる。

情報収集活動の手法は、たとえば特定の組織にスパイを送り込むことで、内部から情報を収集する。共産党員になりすまして、内部から党員のリストを盗み出すとか、宗教団体の信者になりすまして、やはり信者の個人情報を盗みだす。最近は、盗聴などにも熱心だと聞く。反政府系の集会やデモに紛れ込んで、「活動家」の顔写真を取るなどは日常茶飯となっている。
こうした尋常ではないスパイ活動を展開している公安警察に、神原弁護士は懲戒請求者のリストを提供して利用してもらうことを提案しているのだ。「私個人の被害回復よりそちらに力点を置く考え方も悪くない。そっちの方が正義にかなう」とまで述べている。
◇思想の破綻
神原弁護士のツィッターのプロフィールには、自由法曹団常任幹事と付されている。つまり、自由法曹団常任幹事の肩書で、前出のツィートを行ったことになる。
その自由法曹団は、日本共産党と親密な関係にある。自由法曹団の弁護士全員が共産党員ではないが、組織として両者が良好な関係にあることは間違いない。
改めて言うまでもなく、自由法曹団は人権擁護団体としても輝かしい実績がある。公安警察にとっては、当然、マークしたい団体に違いない。自由法曹団と公安警察は水と油のようになじまない存在なのだ。
その公安警察に自由法曹団の常任幹事の立場にある神原弁護士から、「懲戒請求者のリスト」なるものが提出される、あるいはすでに提出された可能性が浮上しているのだ。読者は、神原氏の自由法曹団常任幹事という立場と、公安警察に対する協力的なスタンスに、一貫した思想の破綻を感じないだろうか。
筆者はこうした人物が人権や反差別を叫んで、市民運動の内部に入っている事実に違和感を感じる。国会前の集会で、警察にデモ参加者を逮捕するように迫ったSEALDsの実像と重なってしまう。
集団による弁護士懲戒請求事件、「反訴」した弁護士側の請求方法に問題、被告を増やすことで賠償金の高額化を狙ったスラップまがい
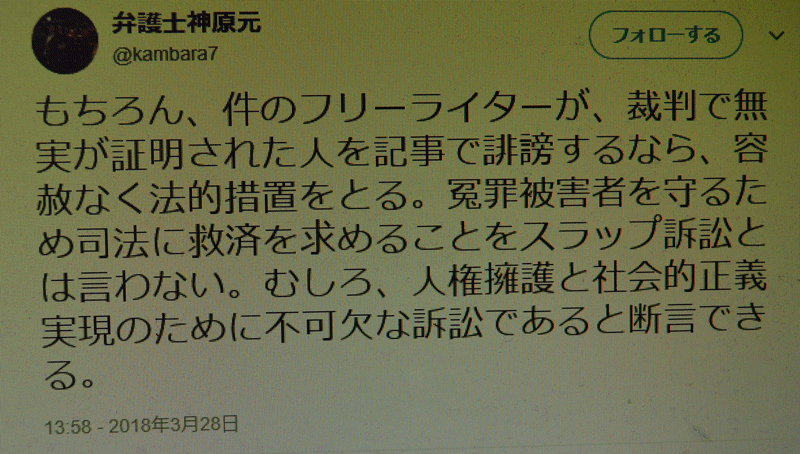
大量の懲戒請求書が特定の弁護士に送付された事件が話題になっている。次のような内容である。
とあるブログを発端として、各弁護士会に対し、大量の懲戒請求が届いた問題で提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も5月16日に記者会見し、6月下旬から訴訟を起こすことを明かした。
しかし、この問題で負担が生じているのは、請求を受けた弁護士だけでない。彼らが所属する弁護士会にも郵送費用などが発生している。■出典
この問題について筆者は、ある政治家の意見を聞く機会を得た。政治家の考えは次のようなものだった。事件を主導した者は別として、大半の懲戒請求者は、この種の「戦術」に深く考えることもなく協力した可能性が高い。懲戒請求の方法には、大きな問題があるが、被害を受けた弁護士は、事件の主導者だけに限定して裁判を起こすのが筋だというものである。
ちなみに原告の弁護士らは、懲戒請求者全員を提訴する方針らしい。すでに示談(金銭解決)で裁判を回避した被告もいるらしい。
◇喜田村弁護士の手口
この事件では、被告の数を増やすことで、請求額の総額をかさ上げしている可能性が高い。被告の数を増やすことによって、賠償金額を高くする手口は、実は筆者自身も体験している。
2008年3月、筆者は読売新聞西部本社から2200万円を請求する名誉毀損裁判を起こされたことがある。訴因は、販売店の改廃事件だった。読売の社員3名が、販売店で強制廃業を宣告した後、読売IS社の社員が店舗から翌日の折込広告を搬出した行為を指して、「窃盗」と書いたことを理由に、2200万円を請求されたのだった。
その際、請求の対象者が明確に指定されていた。読売新聞(西部本社)に対して500万円、3名の社員に対して、それぞれ別個に500万円。弁護士の喜田村洋一自由人権協会代表理事に対して弁護士費用として200万円というふうに。これにより喜田村弁護士らは、賠償額を高く設定したのである。
ここには、司法制度を基盤にして、お金を稼ぎ出す構図が浮彫になっているのだ。
【参考記事】喜田村洋一弁護士らによる著作権裁判提起から10年、問題文書の名義を偽って黒薮を提訴、日弁連はおとがめなし①
◇弘中惇一郎弁護士や弘中絵里弁護士のケース
これとよく似たケースで、弘中惇一郎や弘中絵里弁護士が原告代理人を務めた裁判がある。この裁判では、被告が行った表現行為をカテゴリー別に分類して、ひとつひつとの表現行為に対して「お金」を請求している。次のような分類だ。
ア 「■■のブログ」
名誉毀損・・・・・・・・・162記事 1620万円(単価10万)
名誉感情侵害・・・・・・・101記事 505万円(単価5万)
プライバシー権侵害・・・・・85記事 425万円(単価5万)
肖像権侵害・・・・・・・・・・5記事 25万円(単価5万)
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・2575万円
イ 「■■のホームページ」
名誉毀損・・・・・・・・・13記事 130万円(単価10万)
名誉感情侵害・・・・・・・11記事 55万円(単価5万)
プライバシー権侵害・・・・12記事 60万円(単価5万)
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・245万円
ウ 「■■のblog」
名誉毀損・・・・・・・・・・7記事 70万円(単価10万)
名誉感情侵害・・・・・・・・3記事 15万円(単価5万)
プライバシー権侵害・・・・・5記事 25万円(単価5万)
肖像権侵害・・・・・・・・10枚 50万円(単価5万)
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・160万円
エ「YouTube」
名誉感情侵害・・・・・・・・3動画 15万円(単価5万)
【参考記事】老夫婦が訴えられた名誉毀損裁判で、原告代理人の弘中惇一郎弁護士らが「抽象的概念」に対して請求単価を設定、417本の「記事」に3200万円
◇提訴により弁護士懲戒請求を抑制
改めていうまでもなく、先の2例は典型的な高額訴訟である。とりわけ筆者のケースでは、他に2件の裁判を提起されており、約1年半の間に3件、総額で約8000万円の請求を受けた。
今回の懲戒請求者全員に対する提訴にみる請求方法は、喜田村弁護士や弘中弁護士が選んだ請求方法と極めて類似している。請求金額の総計は、メディアでは公表されていないが、懲戒請求者の数から察して、莫大な額になるのでは。
いわゆる「訴権の濫用」(広義のスラップ)が問題になりはじめたのは、今世紀に入ってからである。いまや1億円の請求も珍しくない。筆者は、スラップを抑制するための運動にも参加してきた。仲間のライターと日弁連に対策を取るように申し入れたこともある。が、日弁連はまったく動かなかった。
喜田村弁護士に対しては、懲戒請求も行った。3件のうちの最初の裁判の中で、虚偽の事実を前提に提訴に及んでいたことが司法認定されたからである。が、日弁連は処分しなかった。つまり、原則として弁護士懲戒には応じないという姿勢があるのだ。弁護士の保護者なのだ。
と、すれば今回の懲戒請求をめぐる訴訟も、一方的に弁護士側に理解を示すわけにはいかない。懲戒請求などさらさら認められるはずがないことを、知った上で、みずからが受けた「被害」を強調して、提訴に及んだ可能性が高い。
弁護士懲戒に対する抑止効果を狙った高額訴訟としか考えられない。広義のスラップと同類なのである。相手が右翼だから、何をやっても正当化されることにはならないだろう。
法律の専門家が、法律という刀を振り回して、素人を切りまくっているような印象がある。剣道の有段者は、素人相手にやたらと剣を使うべきではないのだが。
◇ミュージックゲート裁判
参考までに、ミュージックゲート裁判の例を紹介しておこう。これも請求の方法が悪質な実例である。
【参考記事】
■ソニーなどレコード会社31社が仕掛けた2億3000万円の高額裁判に和解勝利した作曲家・穂口雄右氏へのロングインタビュー(上)
■ソニーなどレコード会社31社が仕掛けた2億3000万円の高額裁判に和解勝利した作曲家・穂口雄右氏へのロングインタビュー(下)
元「しばき隊」隊員で自由法曹団常任幹事の神原元弁護士が弁護士懲戒請求者らを提訴、エスカレートする差別をめぐる問題、訴訟社会の到来が言論の萎縮を招く危険性

ウエブサイト「弁護士ドットコム」が、9日、「『存在しない事実で懲戒請求された』神原弁護士が請求者を提訴」と題する記事を掲載している。
不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして、神奈川県弁護士会に所属する神原元弁護士が5月9日、懲戒請求をおこなった相手に対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、神原弁護士以外にも、大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートを配布していた。(略)
懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である」などと書かれていたという。(略)
最高裁の判例では、事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または普通の注意を払えば知りえたのに、あえて懲戒請求していれば不法行為にあたる、とされている。日弁連によると、2017年だけで組織的な懲戒請求は約13万件あり、その多くが問題のブログに起因するものとみられる。■出典
◇路上から法廷へ
この記事が伝えているように、集団で懲戒請求を申し立てたのは、いわゆる「在日特権」に反対している右派の人々である。これに対して神原弁護士は、彼ら右派に対抗して在日の人々に対する差別をなくす運動を展開している広義の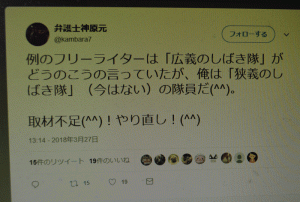
「しばき隊」を支援してきた。
神原弁護士自身も、「狭義の(元)しばき隊隊員」である。自由法曹団常任幹事でもあり、左派系の新日本出版社から著書も出版している。
今回、神原弁護士が提訴したことにより、敵対する2つの勢力の衝突の舞台が、路上から法廷にまで拡大したことになる。右派の人々は、集団による懲戒請求という手段により神原氏らに圧力をかけた。訴訟が多発する実態にヒントを得た戦略だと推測できる。
これに対して神原氏は、裁判という手段に打ってでた。
現段階では、懲戒請求者全員が被告にされたわけではないが、かりに神原氏が勝訴した場合、次々と同じ主張の裁判が起こされる可能性が高い。それにともなって、神原氏が次々と賠償金を受け取ることが出来る構図になる。
実際に、裁判がどう展開するかは、現段階では分からないが、少なくとも、訴訟の提起が弁護士を経済的に潤す構図が生まれはじめていることは否定しようがない。提訴の一次的な目的が原告の権利の回復にあるにしても、副次的には、損害賠償金が莫大な額になる可能性があるのだ。これにより裁判戦略がさらに広がる恐れもある。
大半の人々が認識しないうちに、法律で言論・出版ががんじがらめにされる社会がじわじわと近づいてきたのである。
その意味で、筆者はこの裁判を注目している。
◇人権擁護と社会的正義実現という口実
神原弁護士の過去のツィートを検証したところ、反対言論に対しては、積極的に訴訟を提起する方針のようだ。たとえば、広義のしばき隊による「M君リンチ事件」を取材し、記事化している筆者に対しては、次のようなツィートを発している。「黒薮」の名前は出していないが、ツィートが投稿された同じ時期に、神原氏を電話取材したので、「件のフリーライター」が筆者を指していることは間違いない。(注:現在、神原氏は筆者からのアクセスをブロックしている)
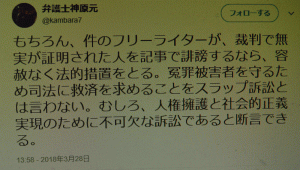 もちろん、件のフリーライターが、裁判で無実が証明された人を記事で誹謗するなら、容赦なく法的措置をとる。冤罪被害者を守るため司法に救済を求めることをスラップ訴訟とは言わない。むしろ、人権擁護と社会的正義実現のために不可欠な訴訟であると断言できる。
もちろん、件のフリーライターが、裁判で無実が証明された人を記事で誹謗するなら、容赦なく法的措置をとる。冤罪被害者を守るため司法に救済を求めることをスラップ訴訟とは言わない。むしろ、人権擁護と社会的正義実現のために不可欠な訴訟であると断言できる。
鹿砦社に対しても、4冊の本の販売中止を請求する裁判の原告(李信恵氏)の代理人を務めている。
【参考記事・メディア黒書】李信恵氏が鹿砦社を反訴、『カウンターと暴力の原理』など4冊の書籍の販売禁止などを求める、誰が言論出版の自由を殺すのか ?
名誉毀損裁判の多発は、メディア黒書でたびたび問題視してきた。何が問題かといえば、たとえ反対言論に対する対抗処置として裁判を提起するのであっても、それが言論の幅を司法の判断に委ねてしまう結果を招き、ひいては息苦しい社会の出現に繋がることである。しかも、司法判断が正しいかどうかの検証には、時間を要する。間違った司法判断を下していることも多いのだ。
筆者は、今回のような不幸な事件を引き起こした最大の原因は、小泉内閣が着手した司法制度改革だと見ている。これが引き金になって名誉毀損などを口実とした訴訟が広がったのである。そしてそれがさらに拡大している。
そこから経済的な利益を得るとすれば、本来の司法制度の目的が二の次になりかねない。
筆者はこの問題について、自由法曹団がどのような見解を持っているのか知りたいと考えている。
喜田村弁護士に対する懲戒請求、第2東京弁護士会の秋山清人弁護士が書いた議決書の誤り②

■ 本稿の前編
喜田村洋一弁護士(自由人権協会)らが起こした黒薮に対する著作権裁判は、すでに述べたように、検証対象になった催告書に著作物性があるかどうかという著作権裁判の肝心な判断以前に、喜田村氏らが催告書の名義を偽って提訴していたとの判断に基づいて、棄却された。
念のために、喜田村氏らが著作物だと主張した文書と、それを削除するように求めた催告書を再掲載しておこう。2つの文書を並べるといかにデタラメかが判然とする。
【喜田村氏らが著作物だと主張した回答書】
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
【メディア黒書から回答書を削除するように求めた催告書】
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
なお、誤解を避けるためにあえて念を押しておくが、喜田村氏らが著作権裁判で削除を求めたのは、後者、つまり催告書の方である。催告書が読売・江崎法務室長の著作物であるから、著作者人格権に基ずいて、メディア黒書から削除するように求めたのである。しかし、東京地裁は著作物性の判断をする以前の問題として、喜田村氏らが催告書の名義を「江崎」と偽って、提訴していたとして、訴えを退けたのである。そもそも訴権などなかったのだ。
ただ、東京地裁は、参考までに、催告書に著作物性があるか否かの判断を示している。そして著作物性はないと判断した。
◇第2東京弁護士会の判断の誤り
さて、喜田村氏らが、提訴権がないのに、催告書の名義を偽ってまで裁判を提起した行為を、どう評価すべきなのだろうか。わたしは司法制度を悪用した悪質な言論妨害と判断して、喜田村氏が所属する第2東京弁護士会に対して、喜田村氏の懲戒を申し立てた。しかし、2年半後に申し立ては棄却された。議決書を書いたのは、秋山清人弁護士である。
決定書を再読してみると、論理の破綻が随所に見受けられるが、そのうち「除斥期間」に関する記述について意見を述べよう。
秋山弁護士は、わたしが期限内(3年)に申し立てを行わなかったから、棄却が妥当だとしているのだが、これは誤っている。
わたしが第2東京弁護士会に懲戒請求を申し立てたのは、2011年1月31日である。一方、江崎法務室長が、問題の催告書を送付したのは、2007年の12月21日である。従って、確かに催告書送付を起点として計算すると3年が過ぎており、審理の対象外になるとも考えうる。
しかし、わたしが懲戒請求の根拠としたのは、弁護士職務基本規定の第75条である。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
喜田村弁護士は、江崎氏が催告書を送付したのを受けて、東京地裁や知財高裁での裁判期間を通じて、「虚偽」の事実を知りながら、裁判所に次々と書面を提出し続けたのである。わたしはこの行為を問題にしているのである。
そして最高裁の判決が確定したのは、2010年である。懲戒請求に踏み切る前年である。この時点で、喜田村弁護士らによる裁判が、虚偽の事実を前提にしていたことが公式に認定され、懲戒請求の要件が整ったのである。
と、すれば懲戒請求の前提となった事実の起点は、判決の確定日である。起点をわざわざ2007年12月21日までさかのぼる理由はないはずだ。それは喜田村氏を救済するための措置だったとしか考えられない。。
このあたりの事情について、秋山弁護士はどのように考えたのだろうか。
第2東京弁護士会の議決を日弁連も追認した。つまり名義を偽って裁判を起こしても、なんら問題ないと判断したのである。これは司法制度に対する軽視にほかならない。自殺行為だ。秋山氏は、軽々しく重要文書を執筆すべきではなかった。文書は記録として残るからだ。当然、今後も検証対象になる。
事件の発生から10年が過ぎ、現役だった関係者の中には、これから定年退職を迎える人々もいるだろう。従って新しい真相究明の道が開けそうだ。
新聞崩壊の時代、検証は11年目に入る。
※決定書の全文は、PDF作業が終わり次第に公開します
読売・江崎法務室長による著作権裁判、「戦後処理」係争開始から8年、事件と喜田村弁護士に対する懲戒請求を再検証する

読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、喜田村洋一・自由人権協会代表理事を代理人として、わたしに対して著作権裁判を起こして8年が過ぎた。「戦後検証」は、係争の発端から8年目に入る。2007年12月21日、江崎氏はEメールでわたしに対してある催告書を送りつけてきた。(判決文、弁護士懲戒請求・準備書面のダウンロード可)
◇新聞販売黒書に掲載した2つの書面
発端は福岡県広川町で起こった読売新聞社とYC広川(読売新聞販売店)の間で起こった強制廃業をめぐるトラブルだった。当時、新聞販売の問題を取材していたわたしは、この事件を取材していた。
幸いに係争は解決のめどがたち、2007年の末に読売はそれまで中止していたYC広川に対する担当員の定期訪問を再開することを決めた。しかし、読売に対する不信感を募らせていたYC広川の真村店主は、読売の申し入れを受け入れるまえに、念のために顧問弁護士から、読売の真意を確かめてもらうことにした。
そこで代理人の江上武幸弁護士が書面で読売に真意を問い合わせた。これに対して、読売は江崎法務室長の名前で次の回答書を送付した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、新聞販売黒書でこの回答書を紹介した。すると即刻に江崎氏(当時は面識がなかった)からメールに添付した次の催告書が送られてきたのである。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。
貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
回答書が自分の著作物なので削除するように求めているのだ。(回答書の著作物性については後述する)
わたしは、回答書の削除を断り、逆に今度はこの催告書を新聞販売黒書(現在のメディア黒書)で公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権(注:後述)に基づいて、削除するように求めてきたのである。
が、催告書の作者は江崎氏ではなく、代筆者がいたのだ。少なくとも、後日、裁判所はそう判断したのだ。
◇喜田村洋一・自由人権協会代表理事が登場
わたしは催告書を削除するように求める江崎氏の申し出を断った。その結果、江崎氏は仮処分を申し立ててきた。ここで江崎氏の代理人として登場したのが、名誉毀損裁判や著作権裁判のスペシャリスト、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。
仮処分は代理人なしに臨み、わたしの敗訴だった。そこで本訴になったのである。わたしの代理人には、江上弁護士ら福岡の販売店訴訟弁護団がついた。
著作権裁判では、通常、争点の文書、この裁判の場合は江崎氏の催告書が著作物か否かが争われる。著作物とは、著作権法によると、次の定義にあてはまるものを言う。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
改めて言うまでもなく、争点の文書が著作物に該当しなければ、著作権法は適用されない。
わたしの裁判でも例外にもれず、争点の催告書が著作物か否かが争われた。催告書の著作物性を争った裁判は、日本の裁判史上で初めてではないかと思う。ちなみに、新聞販売黒書に掲載した肝心の回答書の方は、争点にならなかった。
◇意外な決着
裁判は意外なかたちで決着する。裁判所は、「江崎名義」の催告書の著作物性を判断する以前に、そもそも江崎氏が催告書の作成者ではないと判断したのである。つまりもともと江崎氏には著作者人格権を根拠とした「提訴権」がないにもかかわらず、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴に及んでいたと判断したのである。
なぜ、裁判所はこのような判断をしたのだろうか。詳細は判決に明記されているが、ひとつだけその理由を紹介しておこう。催告書の書式や文体を検証したところ、喜田村弁護士がたまたま「喜田村名義」で他社に送っていた催告書とわたし宛ての催告書の形式がそっくりであることが判明したのだ。同一人物が執筆したと判断するのが、自然だった。
つまり催告書を執筆していたのは喜田村弁護士だった。それにもかかわらず江崎氏は、自分が著作権者であることを主張したのだ。認められるはずがなかった。そもそも提訴権すらなかったのだ。
当然、江崎氏は門前払いのかたちで敗訴した。東京高裁でも、最高裁でも抗弁は認められず、江崎氏の敗訴が確定した。
◇だれが作者なのかという問題
おそらく読者の大半は、著作権という言葉を聞いたことがあるだろう。文芸作品などを創作した人が有する作品に関する権利である。その著作権は、大きく著作者財産権と著作者人格権に分類されている。
このうち著作者財産権は、作品から発生する財産の権利を規定するものである。たとえば作者が印税を受け取る権利である。この権利は第3者にも譲渡することができる。
これに対して、著作者人格権は、作者だけが有する特権を規定したものである。たとえば未発表の文芸作品を公にするか否かを作者が自分で決める権利である。第3者が勝手に公表することは、著作者人格権により禁じられている。
著作者人格権は、著作者財産権のように他人に譲渡することはできない。「一身専属」の権利である。
代理人は、既に述べたように、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。
裁判所は判決の中で、催告書を執筆したのは喜田村弁護士か彼の事務所スタッフであった高い可能性を認定した。
◇弁護士懲戒請求
弁護士職務基本規程の第75条は、次のように言う。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
喜田村弁護士は、問題になった「江崎名義」の催告書をみずから執筆していながら、江崎氏が書いたという前提で裁判の準備書面などを作成し、それを裁判所に提出し、法廷で自論を展開したのである。
当然、弁護士職務基本規程の第75条に抵触し、懲戒請求の対象になる。わたしが懲戒請求に踏み切ったゆえんである。
◇弁護士倫理の問題
なお、裁判の争点にはならかなったが、喜田村弁護士に対する懲戒請求申立ての中で、わたしが争点にしているもうひとつの問題がある。ほかならぬ催告書に書かれた内容そのものの奇抜性である。
著作権裁判では、とかく催告書の形式ばかりに視点が向きがちだが、書かれた内容によく注意すると、かなり突飛な内容であることが分かる。怪文書とも、恫喝文書とも読める。端的に言えば内容は、江崎氏がわたしに送付した回答書が江崎氏の著作物なので、削除しろ、削除しなければ、刑事告訴も辞さないとほのめかしているのだ。
回答書は、本当に著作権法でいう著作物なのだろうか?再度、回答書と著作権法の定義を引用してみよう。
【回答書】 前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
【著作物の定義】 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
誰が判断しても、著作物ではない。しかも、この内容の催告書を書いたのは、著作権法の権威である喜田村弁護士である。回答書が著作物ではないことを知りながら、催告書には著作物だと書いたのだ。
弁護士として倫理上、こうした行為が許されるのか疑問がある。が、日弁連はこの懲戒請求を喜田村弁護士を調査することなく却下した。
わたしは今でも、この判断は間違っていると考えている。
裁判と言論・人権を考える(4)、読売裁判の判例と弁護士懲戒請求、催告書の名義を偽って提訴
高額訴訟ではないが、提訴のプロセスに問題が指摘された裁判の例を紹介しよう。わたし自身が被告にされた著作権裁判である。原告は、読売新聞社(西部)の法務室長・江崎徹志氏だった。江崎氏の代理人は、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士だった。
◇事件の発端
2007年の暮れに江崎氏は、わたしにEメールである催告書を送付してきた。その中で江崎氏は、わたしに対して、新聞販売黒書(メディア黒書の前身)のある記述を削除するように求めたのである。その資料とは、次の通知(記述)だった。YC(読売新聞販売店)に宛てたものだ。
前略
読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。
当社販売局として、通常の訪店です。
以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。
かりにこの文書を「回答書」と呼ぶことにする。
◇真村店主に対する差別
読売新聞社とYC広川の真村店主の間には、2001年ごろから係争が続いていた。係争の引き金は、読売が真村さんの営業区域の一部を返上させようとしたことである。当然、真村さんはこれを断った。
これに対して、読売は真村さんに販売店を改廃(強制廃業)することを言い渡した。この係争は地位保全を巡る裁判に発展した。
こうした状況の中で真村さんの店は「死に店」扱いにされた。飼い殺しであるから、当然、読売の担当員はYC広川を訪問しなくなった。補助金も大半をカット。差別的な待遇を受けるようになったのである。
しかし、2006年9月、福岡地裁久留米支部は、真村さんの地位を保全する判決を言い渡した。さらに2007年6月には、福岡高裁も真村さんに軍配を上げる。しかも、読売による「押し紙」など、優越的地位の濫用を厳しく批判した画期的な判決を下したのだ。
高裁判決を受けて、読売の態度に変化の兆しが現れた。YC広川に対する訪店を再開するための第一歩として、真村さんに訪店再開の意思を伝えたのである。
ところが真村さんは、係争中に積もりに積もった不信感のために、即答をさけた。そして代理人の江上武幸弁護士に依頼して、訪店再開の真意を読売側に問い合わせてもらったのだ。その回答として江上武幸弁護士が江崎法務室長から受け取ったのが、上記の回答書だった。それをわたしが、新聞販売黒書で公開したのである。
◇著作物には定義がある
これに対して江崎法務室長は、わたしに対し、削除を求める催告書を送ってきたのだ。
催告書の中で、江崎氏は上記の回答書が自分の著作物だと主張した。それを根拠に削除を求めたのである。しかし著作物と言うからには、著作権法の次の定義を満たさなければならない。
【思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。】
誰が解釈しても回答書が著作物でないことは明らかである。それにもかかわらず江崎氏は、催告書の中で回答書が自分の著作物であると述べ、わたしに削除を求めてきたのだ。しかも、わたしが回答書を掲載したことを、「民事上も刑事上も違法な行為」とした上で、次のように記していたのだ。
「貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を探ることになりますので、この旨を付言します。」
明らかに著作物ではないものを、著作物だと強弁して、削除に応じなければ、法的手段を探ると言ってきたのだ。しかも、刑事告訴までほのめかしていたのだ。
◇催告書を公開
もともと江崎氏の主張そのものに道理がないのであるから、わたしは回答書の削除には応じなかった。さらに対抗措置として、今度は催告書を新聞販売黒書でそのまま紹介した。恫喝文書と判断した結果でもあった。回答書が著作物であるというデタラメな内容の恫喝文が送られてきたことを重要ニュースと判断したのである。
これに対して、江崎氏は催告書を削除するように求めて、裁判を起こしたのである。(厳密には、仮処分の申し立てを経て本裁判へ進んだ。)
ところがおかしなことに、催告書でわたしに要求した回答書の削除は、裁判では要求してこなかった。催告書だけの削除を求めてきたのである。
◇催告書を作成したのは喜田村洋一弁護士
催告書の削除を求める著作権裁判の争点は、当然、催告書に著作物性があるかどうかという点になる。著作物性があり江崎氏の著作物と認められたならば、わたしは削除に応じなければならない。
ところが裁判は以外な展開を見せる。もともと江崎氏がこの裁判の前提としていたのは、催告書は江崎氏が自分で作成した著作物であるから、わたしには公表権がないという論法だった。ところが被告(黒薮)弁護団の追及で、催告書の執筆者は、江崎氏ではなくて、読売の喜田村洋一弁護士であることが判明したのだ。
厳密に言えば、喜田村弁護士か彼の事務所スタッフが催告書を作成した可能性が極めて高いと裁判所が認定したのである。
これは言葉を換えれば、江崎氏とは別の人物が作成した催告書を、江崎氏が自分で作成した文書であると偽って、わたしを裁判にかけたということである。つまり著作物であると主張していた催告書の名義を「江崎」に偽っていたことになる。
その結果、何が起こったのか?喜田村弁護士らは、催告書の名義を偽ったまま、著作者人格権を主張したのである。
ちなみに著作者人格権は、他人に譲渡することは認められていない。
【ウィキペディア:著作者人格権は、一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと解されており、日本の著作権法にもその旨の規定がある(59条)。また、日本法では一身専属性のある権利は相続の対象にはならないので(民法896条但書)、著作者人格権も相続の対象にはならず、著作者の死亡によって消滅するものと解されている。】
参考までに、知財高裁(東京)の判決から、上記の事実を認定した部分と弁護団声明を紹介しておこう。
なぜ、催告書の作成者を偽ってまでも、わたしを提訴したのだろうか。推測になるが、「押し紙」報道を抑制したかったからではないか?
◇弁護士懲戒請求
最高裁で判決が確定した後、わたしは「戦後処理」に入った。喜田村弁護士が所属する第2東京弁護士会に、喜田村弁護士に対する懲戒請求を申し立てた。根拠としたのは、『弁護士職務基本規定』の次の条項だった。
第75条:弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
私が提出した第1準備書面は次の通り。事件の性質を簡潔に伝えた。
日弁連が喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求を棄却、審査内容はブラックボックスのなか
11月17日付けで、日弁連はわたしが喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事で読売新聞社の代理人)に対して2011年1月に申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。申し立てから、最終的な決定まで、約4年の歳月を費やした。
審査のプロセスは次の通りである。
1,第2東京弁護士会による棄却
2,日弁連による棄却
3,綱紀審査(外部有識者)による棄却
この問題については、これから検証に入るが、わたしとしては到底納得できない。と、いうのも「1」の段階では、棄却理由が示されたものの、「2」と「3」では、実質的に理由が示されていないからだ。誰が審査したのかも、審査の長を除いてわからない。ブラック・ボックスの中である。
今後、公開質問状などのかたちで審査内容の開示を求めていく。
あえて理由として日弁連サイドがあげているのは、第2東京弁護士会の議決書の認定と判断に誤りがない、というものである。が、これは厳密な理由ではない。結論にすぎない。最初から棄却という結論を決めていたから、論理的な理由書が書けなかったのではないだろうか。
あるいは、まったく反論できないほど、わたしの主張が真っ当だったということである。審査に4年も時間がかかった原因もこのあたりにあるのでは。
この事件の詳細は、次の記事を読むとわかりやすい。「2」の段階で「メディア黒書」に掲載したものである。
袴田事件と類似した事件の構図、喜田村弁護士に対する懲戒請求、準備書面(1)を公開
次に示すのは、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する弁護士懲戒請求で、日弁連の綱紀審査委に提出する予定の準備書面(1)の全文である。
■準備書面(1)の全文
懲戒請求者:黒薮哲哉
対象弁護士:喜田村洋一
はじめに
準備書面(1)では、「1、排斥期間の起点について」と、「2、弁護士職務基本規定に照らし合わせた懲戒対象弁護士の言動」の2点について、説明する。
この事件は、捏造した証拠を前提に検察が有罪を主張した袴田事件の構図と類似している。しかし、袴田事件が刑事裁判であるのに対して、本件懲戒請求の主要な原因になっている本件著作権裁判は、民事裁判の場で争われた。
本件著作権裁判の訴因は本件催告書である。本件催告書は、「江崎徹志」の名が付されているが対象弁護士により作成された高い可能性が本件著作権裁判の判決で確定した。つまり対象弁護士が作者であるにもかかわらず、江崎名義で懲戒請求者に本件催告書を送り付け、これがウエブサイトで公表されると、本件著作権裁判を起こし、もともと江崎氏が持ち得ない著作者人格権を主張したのである。当然、それを前提として懲戒対象弁護士は書面を提出し、法廷で自らの主張を展開したのである。
しかし、裁判所はこうしたあるまじき行為を見破り、江崎・喜田村の両名を敗訴させたのである。
懲戒請求者は、懲戒対象弁護士が、虚偽の事実を設定して裁判を提起し、江崎氏に著作者人格権がないことを知りながら、裁判所に書面を提出し、自己の主張を展開したことを問題視している。袴田事件の類似性とは、こうした事件の性質を意味している。
1、排斥期間の起点について
第二東京弁護士会が作成し、日弁連が追認した本件決定書には、棄却理由として排斥期間の終了を理由とした次の記述がある。
「(1)本件催告書が作成された時期は、平成19年12月21日であるところ、本件懲戒請求書を第二東京弁護士会が受け付けたのが平成23年1月31日であるので、懲戒請求事由1の事実は既に3年間の排斥期間を過ぎており、懲戒手続きを開始することができない。
(2)そもそも、本件催告書を作成、送付したのは、対象弁護士ではなく、江崎であって、当該行為は対象弁護士に関する懲戒事由になり得ない。」
A 事実関係の誤りについて
(1)(2)の理由は的外れである。まず、事実関係の誤りから指摘する。 決定書は、「そもそも、本件催告書を作成、送付したのは、対象弁護士ではなく、江崎」であると述べているが、本件催告書の作成者、送付者につて知財高裁判決(平成21年[ネ]第10030号)は次のように認定している。
「上記認定事実によれば、本件催告書には読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告[黒薮注:江崎のこと]の名前が表示されているものの、その実質的な作成者は(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人[黒薮注:懲戒対象弁護士](又は同代理人事務所の者)である可能性が極めて高いものと認められる。」
「すなわち、?原告の著作権法や法的紛争の解決に関する知識経験の程度、?読売新聞西部本社と販売経営者との法的紛争の重要性に関する同社の認識の程度等、?原告及び原告代理人のいずれからも、本件催告書作成過程を示す客観的なデータは提出されていないこと等に照らすならば、本件催告書は、原告から相談を受けた、原告代理人事務所において、本件催告書を作成し、そのデータをメールに添付する方法により、原告に送信し、これを受信した原告が、被告に対して送信したものと認定することによって、辻褄が合うといえる 」
とはいえ、確かに第二東京弁護士会が棄却の根拠として全面的に採用している本件損害賠償裁判(平成24年[ネ]第794号)の判決は、「本件著作権裁判の内容や経過からすると、同人が、自分名義で出した文書は自分の著作物であると考えていることがうかがわれ、本件催告書の作成者を一義的に決めることは困難であったという事情にも照らせば、同人が故意に虚偽を並べて本件著作権仮処分を申し立てたと認めることは困難である」と、述べて必ずしも懲戒対象弁護士が本件催告書の作成者であるとは認定できないという判断を示している。
しかし、この記述は、出典である本件著作権裁判の判決を正しく解読せずに記されている。本件損害賠償裁判の判決は、「本件著作権裁判の内容や経過からすると・・・」と出典を明記したうえで、「本件催告書の作成者を一義的に決めることは困難」と述べているが、既に述べたように本件著作権裁判は、本件催告書の作成者を「原告代理人[黒薮注:懲戒対象弁護士](又は同代理人事務所の者)である可能性が極めて高いものと認められる」と、認定しているのである。
それが懲戒対象弁護士らが、敗訴した大きな要因だった。 本件損害賠償裁判の福岡高裁判決を書いた木村元昭裁判長は、本件著作権裁判の判決を精査・検証せずに、読売新聞社を勝訴させるために、恣意的に事実を捻じ曲げ判決を書いた可能性が高い。
B 問題にしているのは裁判期間中の懲戒対象弁護士の行為
第二東京弁護士会の本件決定書は本件催告書の作成日(それは同時に送付日でもある)にあたる平成19年12月21日を排斥期間の起点として、第二東京弁護士会が本件懲戒請求を受け付けた平成23年1月31日の時点では、すでに排斥期間の3年を過ぎているとして、本件懲戒請求を棄却している。この判断は2重に誤りをおかしている。
B-1
本件懲戒請求の対象となっているのは、改めて言うまでもなく、喜田村洋一弁護士であって、江崎氏ではない。と、すれば本件懲戒請求の対象者ではない江崎氏の行為を排斥期間の起点にすることは論理が破綻している。
かりに懲戒対象弁護士が本件催告書の作成者・送付者であることを、本件決定書が認定していれば、本件催告書の作成日・送付日を排斥期間の起点として検討する余地はあるが、本件決定書は江崎氏を本件催告書の作成者・送付者として認定しているのである。繰り返しになるが、そうであれば本件懲戒請求の対象外の人物の行為を排斥期間の起点とするのは誤りだ。
B-2
しかし、懲戒請求者が重大問題として審理を求めているのは、本件催告書の作成行為・送付行為そのものではない。本件催告書の作成過程から提訴に至る経緯が虚偽に満ちている上に、本件催告書に書かれた内容がまったくのデタラメであることを懲戒対象弁護士が知っていながら、ウソを前提として本件著作権裁判の進行中、裁判所に書面を提出し、みずからの主張を展開したことを問題視しているのである。
このような行為が懲罰の対象にならないとすれば、虚偽の事実を捏造して、袴田巌氏の半生を牢獄に閉じ込めた検察も罰せられないことになる。日弁連が袴田氏を支援してきたことを踏まえれば、捏造や虚偽を前提とした法廷での主張に対しては、厳しく罰するのが道理である。
B-3 ?
たとえ江崎氏による催告書の作成日・送付日を、排斥期間の起点とするとしても、そもそも懲戒対象弁護士らによるあるまじき行為が発覚したのは、2009年1月に、東京地裁で実施された江崎氏に対する本人尋問の場であり、それが最終的に最高裁で司法認定されたのは、2010年2月であるから、本件著作権裁判の判決確定を前提に提起した本件懲戒請求で、対象外の江崎氏が本件催告書を作成・送付した平成19年12月21日を排斥期間の起点にすることは、論理が破綻している。
繰り返しになるが懲戒請求者は、本件催告書の送付行為そのものを問題にしているのではなくて、本件催告書が孕む重大な諸問題を懲戒対象弁護士が認識していながら、あえてそれを隠し、虚偽を前提に書面を提出したり、法廷で自論を展開したことを問題にしているのである。
たとえ江崎氏が本件催告所の作成者であり、送付者であるとしても、少なくとも本件催告書の内容がデタラメであることを、江崎氏の代理人であり、著作権問題の権威である懲戒対象弁護士は、知る立場にあったわけだから、責任は免れない。
2、「弁護士職務基本規定」に照らした懲戒対象弁護士の行為
日弁連の弁護士倫理委員会が執筆・編集している『弁護士職務基本規定』は前文で次のように述べている。
「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。 その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。 よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規定を制定する。」
前文に謳われている理念に照らし合わせた場合、弁護士が虚偽の事実を前提に提訴にいたる行為を主導したり、幇助した場合、懲戒の対象になることは言うまでもない。懲戒対象弁護士は、次の条項に違反している。
「 1条:弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に務める。 」
「4条:弁護士は、司法の独立を擁護し、司法制度の健全な発展に寄与するように務める。」
?「10条:弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼者を誘導し、又は事件を誘発してはならない。」
「14条:弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。」
「31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。」
「74条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続きの実現に務める。」
「75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。」
日弁連が袴田事件委員会を設置して、検察の証拠捏造に端を発したこの冤罪事件の元容疑者を支援してきた経緯を踏まえると、虚偽を前提に裁判を起こす行為に対しては、刑事事件であれ、民事事件であれ、厳しく対処すべきである。
日弁連の過去の懲戒事例に照らし合わせても、懲戒対象弁護士が何の処分も受けずに、連日のように法廷に姿を見せている事実を踏まえたとき、司法界に正義はあるのかという疑問を抱かざるを得ない。
弁護士は国費で養成されているのであるから、不正に対しては厳しく対処すべきである。
